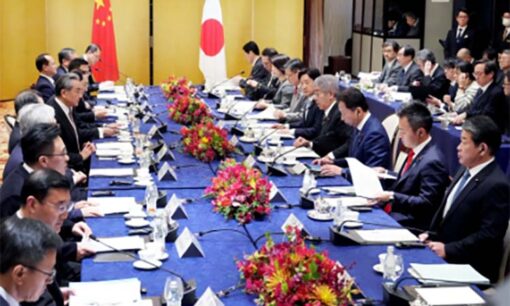テレビを持たず、スマートフォンやパソコンでNHK番組を視聴している人にも、受信料の支払い義務が生じる。そんな新制度の導入が決まった。月額1100円という金額や契約の条件、解約の可否など、制度に対する戸惑いや反発の声が広がる中、2025年10月から始まる「ネット受信料制度」の実態に迫る。
ネット視聴も受信契約の対象に 2025年10月から制度変更
日本放送協会(NHK)は2025年10月から、テレビだけでなくインターネットによる視聴も「受信契約」の対象とする制度変更を実施する。これは2024年に成立した改正放送法に基づき、NHKのインターネットサービス(同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信)が「必須業務」に格上げされたことを受けた対応である。
新制度では、ネット配信のみを利用する世帯に対し、テレビの地上契約と同額である月額1100円の受信料が発生する。沖縄県は従来通り月額965円とされている。すでに受信契約をしている世帯には追加の負担はない
「スマホやPCを持っているだけ」で契約義務は生じない
最も多く寄せられる疑問の一つが、「スマホやパソコンを持っているだけで契約義務が生じるのか」という点だ。NHKはこの点について、「一定の操作を行ってNHKのWEBサイトやアプリにアクセスし、配信の受信を開始した場合に限り契約義務が発生する」と明記している。
つまり、所有しているだけでは契約の対象にはならず、視聴の意思を明示した時点で受信契約が成立する。配信の利用開始には「視聴の意思確認」のため、ボタン操作などによる同意が必要であり、誤操作による契約成立を防止する仕組みも導入される予定だ。
契約単位は「世帯」 単身赴任・学生は別契約が必要
契約の単位は、従来のテレビ契約と同様に「世帯ごと」が基本となる。住居および生計をともにする家族であれば、1つの契約でカバーされる。一方、自宅を離れて暮らす単身赴任者や学生などは「別世帯」とみなされるため、それぞれで契約が必要になる。
たとえば、実家が受信契約を結んでいても、下宿先の学生がスマホでNHKの配信を視聴した場合は、別契約が求められる。ただし、このようなケースでは「学生免除」や「家族割引」の対象となる制度も用意されている。
事業所での利用は「設置場所」ごと スマホでも契約対象に
事業所やホテル、学校などでの視聴については、「設置場所ごと」に契約が必要とされる。特に、事業のために複数の人が利用するタブレットやチューナーレステレビなどがある場合には、それぞれ設置場所単位で契約を行う。
NHKは、配信の受信に関して「受信の本拠(使用される拠点)」の考え方を採用しており、たとえば会社の会議室で使う端末や、ホテルの客室で提供される配信も、契約対象となる可能性がある。
解約には「視聴の停止」と「設置なし」の届け出が必要
大きな論点の一つが「契約した後に本当に解約できるのか」という点だ。受信契約の解約には、単に「使っていない」と申し出るだけでは足りず、以下の要件を満たし届け出る必要がある。
- 本人および家族がNHKの配信を継続的に受信していないこと
- 通信端末機器の設置がないこと(もしくは廃止したこと)
この要件は、従来のテレビ受信契約と同様の考え方であり、スマホやパソコンの「廃止」や「非使用」を証明しなければならない。NHKは今後、一部の解約手続きについてインターネットでの受付を検討しているが、現段階では詳細な方法は明示されていない。
ネット配信の利用者数とNHKの想定
NHKは、ネット受信契約の開始に伴い、初年度となる2025年度下半期に約1.2万件、2026年度には2.4万件の新規契約を見込んでいる。これにより合計約3.6万件の契約となると推計している。この数字は、あくまでテレビを持たないネット視聴者層への普及が前提であり、利用促進とともに課題となるのが「視聴者の理解と納得」である。
「ネット受信料=サブスクではない」 わかりにくさが課題
ネット配信をサブスクリプションサービスとして運用しない点にも注目が集まる。NHKは「既存の受信料制度との整合性」を理由に、ネット配信においてもテレビと同様の「契約制」を採用する。月額制での契約だが、「使わない限り支払いは不要」「だが一度契約すれば解約が難しい」という仕組みは、サブスク的な柔軟性を欠くとも言える。
このため、SNSやネット上では「わかりにくい」「ワンクリックで契約されてしまうのでは」といった不安の声も上がっている。
まとめ:視聴者の理解と納得を得られる制度運用を
この制度はネット視聴が主流になりつつある時代の流れに沿ったものといえる。一方で、スマホやPCを持つことが日常となった現代において、契約の範囲や解約の要件があいまいであることは、制度への不信を招きかねない。求められるのは、「公共メディア」としての信頼を維持しつつ、わかりやすく納得感のある制度設計である。契約・視聴・解約のすべてにおいて、利用者の選択と判断が尊重される仕組みこそ、真の公共サービスと呼べるだろう。