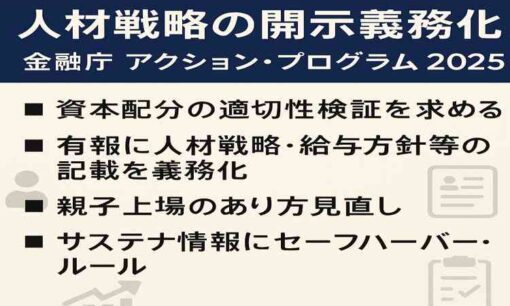寄付を経営目標の第一に掲げ、社会課題の解決に挑む株式会社MIYOSHI。
その独自の経営哲学と挑戦を同社、代表取締役佐藤英吉氏が語る。
地域密着企業MIYOSHIの技術革新と社会貢献への意志
株式会社MIYOSHIは、電子機器製造や監視用カメラのレンタル事業、LED照明の販売・施工といった多岐にわたる分野で事業を展開する企業だ。
同社が特に注目を集めるきっかけとなったのが、現場監視カメラ「G-cam」。この製品は、建設現場の防犯や安全管理、進捗管理を目的として開発され、全国で8500台以上が稼働している。
「G-cam」の最大の強みは、誰でも簡単に扱える点にある。電源に接続するだけで稼働し、特別な設定や操作を必要としない利便性は、建設現場など多忙な環境で高く評価されている。
また、最新モデル「G-cam 04」では、映像をクラウドに保存したり、ウェブで簡単に閲覧できる機能が追加され、さらなる進化を遂げた。
この製品が生まれた背景には、「誰かの困りごとを解決する」というMIYOSHIの経営スタイルがある。
建設現場からの依頼を受けた佐藤氏は、その課題に応えるべく迅速に開発を進めた。結果として他社に先駆けた製品となり、現在では同社の売上の9割を支える主力商品へと成長している。
しかしMIYOSHIの魅力は、革新的な製品を生み出す技術力だけに留まらない。
同社は、その活動を通じて地域社会と深く関わり、さまざまな社会貢献活動にも力を入れている。
たとえば、地元小学校の社会科見学を受け入れる活動や、アフガニスタンの子どもたちへランドセルを寄付するといった取り組みがその一例だ。
佐藤氏は、こうした活動を通じて「地域とともに成長し、社会全体に貢献することが企業のあるべき姿」と語る。
寄付は経営の数値目標の最上段「社会貢献型経営」
MIYOSHIの経営哲学には、他の企業にはないユニークな特徴がある。それは「寄付を経営の数値目標の最上段に掲げる」という姿勢だ。
同社では、売上や利益を単なるビジネスの成果として捉えるのではなく、寄付という形で社会に還元することを経営の核として据えている。佐藤氏は、この方針についてこう語る。

「寄付をすることは、単なる慈善活動ではありません。それは私たちが経済活動を通じてどれだけ社会に貢献できるか、その指標そのものです。売上や利益はもちろん重要ですが、私たちMIYOSHIにとって特に大事なのは、それをどれだけ社会に役立てられるかということ。だからこそ、私たちは経営の数値目標の最上段に年間『寄付1億円』を掲げています。この数字に到達するために社員一丸となって努力し、結果として社会に大きな力を与えられる。それが私たちの目指す『社会貢献型経営』なんです。」(佐藤氏)
佐藤氏が寄付活動を始めたのは、起業翌年の2003年。当時、父の会社の倒産という苦難を体験した佐藤氏は、多くの人から支えを受けた経験を通じて「恩返しをしたい」という想いを抱いたという。
「2001年に父の会社が倒産したとき、私自身も連帯保証で多額の借金を背負いました。その時に支えてくれたのが、母校の先生や同級生、そして地域の人々でした。厳しい状況の中での支援が本当にありがたく、助けていただいた恩は一生忘れられません。そこで私は考えたんです。自分が経営者として成功したら、その恩を寄付という形で社会に返していこうと。」(佐藤氏)
現在、MIYOSHIの寄付活動は累計3億円を超える規模にまで成長している。平和、教育、環境、福祉、文化、スポーツの6分野にわたる寄付を実施しており、その範囲は国内外に及ぶ。

さらに佐藤氏は、寄付を通じて得られる意義についても説明する。
「寄付をすることで得られるのは、単に感謝されることではありません。社会に役立つ自分たちの仕事に社員自身が誇りを感じ、会社全体が一つになるんです。コロナ禍の時にパーテーションを無償提供した際には、社員同士で『自分の仕事が誰かの希望になっている』という実感が湧いたと共有し合いました。このように寄付は、社会に貢献すると同時に社員のモチベーションや会社の一体感を育む役割も果たしているのです。」(佐藤氏)
「なぜ寄付をするのか?」と問われた際、佐藤氏は「なぜしないのか、と逆に問いたい」即答する。
この言葉には、社会の一員としての責任を果たし、同時に経済的成功を社会に還元するという経営哲学が凝縮されているのを感じた。
社員の心も動かす「寄付の精神」
MIYOSHIが掲げる「寄付を最上段に据える経営」。この理念は、経営者である佐藤氏だけではなく、社員一人ひとりの心にも根付いている。
「寄付という行為は、単にお金を渡すだけのものではありません。それは私たち自身の仕事や存在意義を問う行動でもあります。寄付という目標があるからこそ、社員一人ひとりが『自分の仕事が誰かの役に立っている』という実感を持てるのです。」(佐藤氏)
この言葉どおり、MIYOSHIの社員たちは寄付活動を単なる経営方針の一環として捉えるのではなく、自らの手で社会貢献を実現するプロセスにやりがいを感じている。
たとえば、コロナ禍において全国の飲食店がアクリルパーテーション不足に悩んでいた際、MIYOSHIは紙とプラスチック製のパーテーションを開発し、全国に1万3000枚を無償で提供した。
この取り組みには社員も積極的に関わり、外箱には、社員全員からの応援メッセージを入れた。
「お客様から泣きながら感謝の電話やお礼の手紙をいただきました。そのとき社員全員でその手紙を共有し、私たちの仕事が誰かの人生に大きな影響を与えていることを実感しました。このような経験が、寄付が単なる会社の方針ではなく、社員自らの意義ある行動として根付くきっかけになったのです。」
また、MIYOSHIでは地域の小学校と連携し、役目の終わったランドセルをアフガニスタンの子どもたちへ寄贈する”マゴコロ・ランドセル・プロジェクト”を企画し、検品や発送作業にも関わった。
さらに、社会科見学の受け入れなど、地域の子どもたちと触れ合う機会を大切にしている。
ある小学校で行われたプレゼンの最後には、児童たちが「微力だけど無力じゃない。心が変われば行動が変わる」という言葉を送ってくれたという。
この言葉は社員にも深い感銘を与え、日々の活動への意識をさらに高めるきっかけとなったという。
「社員は寄付活動に関わることで、ただ仕事をするだけでは得られない充実感や誇りを感じています。寄付をするために稼ぐ、という意識が、社員一人ひとりの姿勢を変え、会社全体をポジティブに動かしているのです。」(佐藤氏)
社員全員が人のために火をともす「寄付の精神」。これがMIYOSHIの強さの根源であり、社会貢献型経営を支える土台となっている。

次なるテーマは核廃絶。社会課題の解決で目指す平和な未来
MIYOSHIが掲げる社会貢献型経営は、寄付や地域社会との連携にとどまらず、さらに大きなテーマへの挑戦を始めている。それが「核廃絶」という壮大な目標だ。
2024年9月、佐藤氏は「核廃絶株式会社」を設立。この新たな会社は、核兵器のない世界を目指す活動をビジネスとして実現することを目的としている。
「核兵器廃絶を推進する事業を立ち上げようというのは、ある19歳の学生との出会いがきっかけでした。彼女が『核兵器をなくすことが私の夢です』と話してくれたとき、その情熱に心を打たれました。ならば、私たちが彼女の夢を具体的な事業として支えようと決意したんです。」(佐藤氏)
佐藤氏は、この会社を「儲けることそのものが社会貢献に繋がる、新しい事業モデル」と位置づけている。核廃絶株式会社は、核兵器廃絶を目的とし、そのプロセスで収益を上げる仕組みを目指している。
現在のところ事業計画は議論の段階にあるが、佐藤氏はこの挑戦を通じて、企業としての新たな価値を生み出したいと語る。
「寄付はもちろん大切ですが、事業そのものが社会課題の解決に直結するという形を作りたいのです。核廃絶は非常に大きなテーマではありますが、だからこそ取り組む価値があります。私たちは企業として、核兵器の問題に正面から向き合い、この地球規模課題に挑戦していきたいと思います。」(佐藤氏)
MIYOSHIの挑戦は、単なる理想論では終わらない。
これまでも同社は、地域や世界に目を向けた社会貢献活動を実現してきた実績がある。今回の核廃絶株式会社という試みも、社会貢献型経営の延長線上にある。
「核兵器をなくすために重要なのは、私たち一人ひとりの心の変革です。「核兵器を容認する」思想を排し、平和を目指していくことです。」(佐藤氏)
佐藤氏の言葉からは、核廃絶という大きな目標のためには、人間の意識変革が重要であるとの強い想いが伝わってくる。
この挑戦を通じてMIYOSHIが目指すのは、全人類の幸福と平和を実現することである。
◎プロフィール
佐藤英吉
株式会社MIYOSHI 代表取締役
1967年1月30日生まれ。創価大学経営学部卒業後、丸井に入社。その後、電子機器製造EMS事業を営む父親の会社に入社するものの、7年後に倒産。そこからわずか半年で株式会社MIYOSHIを立ち上げ、「社会貢献型経営」を実践。2024年9月には核廃絶株式会社を立ち上げる。座右の銘は「人のために火をともせば我がまへあきらかなるがごとし」。
◎会社概要
会社名称:株式会社MIYOSHI
代表者:佐藤英吉
設立:2002年2月
主な事業
・現場監視カメラ開発とレンタル
・電子機器製造(EMS)
・LED照明の販売・施工
・その他、製品開発
会社所在地:埼玉県入間郡三芳町上富1916-10
URL:https://3yoshi.jp/