
森建業 森貴幸さん

尾前損害調査オフィス株式会社は、数多くの保険の契約者たちから支持される、火災保険のプロフェッショナルで構成された損害調査会社です。 保険の契約者であるお客様の立場で徹底した損害調査をすることで、適切な保険金の受け取りを支援しています。誰もが公平に保険金を受け取れる世の中にすることを目指し、契約者にはわかりにくい保険を身近なものにしようと、業界全体の認知度向上・発展を牽引している企業です。
| 名称 | 尾前損害調査オフィス株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 尾前 美幸 |
| 住所 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階 |
| URL | https://www.omae-office.com/ |
| 業種 | 損害調査コンサルティング |
| 電話番号 | 03-6853-6645 |
| 設立 | 2018年3月20日 |
| FAX | 03-6853-6601 |
| メールアドレス | info@omae-office.com |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週土・日曜日、祝日 |
SDGs
| ありがとうの総数 | 5 |
|---|

東日本大震災、毎年のように発生する台風や水害。この10年、日本は災害列島であることをまざまざと突きつけられました。全国どこでも被災地になる可能があり、大切な家族と家屋を守るために保険という備えが欠かせないことを多くの人が認識しています。一方で火災保険のわかりにくさゆえ、正当な申請や保険金の受け取りにつながっていないという問題点も顕在化しています。
尾前損害調査オフィス株式会社は、火災保険のプロフェッショナルが契約者の立場で損害調査をすることで、適切な保険金の受け取りを支援するサービスを提供する企業。誰もが公平に保険金を受け取れるようサポートする、顧客にも社会的にも貢献度の高い事業はクライアントの支持を獲得し、主に顧客から顧客へと口コミによって事業を拡大してきました。「人とのつながりが当社の大きな財産」と語る尾前損害調査オフィス株式会社代表取締役の尾前美幸さんと統括マネージャーの土井隆さんに、適切な補償の受け取り方、起業からこれまでの歩み、大切なステークホルダーへの感謝を伺いました。

―尾前損害調査オフィス株式会社について、立ち上げからこれまでの歩みについて教えてください。
尾前 当社の事業は、損害保険会社で火災保険の業務に携わっていた私と土井とで2018年に立ち上げました。保険金を受け取るには自己申告が必要ですが、大半の人は保険の仕組みを正確に理解していないので、申告できることさえ思いつかず、保険契約者のうち申請経験のある方は3%弱ほどです。つまり97%の方が申請していないというデータがあるのです。生命保険はケガや病気、死亡時など受け取りの対象がわかりやすいのに対し、火災保険は対象になるケースなどがわかりにくいことが原因です。当社では、火災保険に精通したプロフェッショナルが契約者の立場に立って損害調査をすることで、お客様が正当かつ最大に保険金の受け取りができるよう支援します。
土井 火災保険の契約者側に立って家屋の損害調査を実施し、報告書の作成や申請の支援、保険会社の損害査定に同行するのが当社のサービスの流れです。事業立ち上げのきっかけとなったのは、10年前の東日本大震災です。当時私と尾前は外資系の大手損害保険会社の社員として、契約者から寄せられる火災保険の申請に対応していましたが、家屋がダメージを受けているにも関わらず保険の申請をしていないケースが非常に多かったのです。また、申請している方でも、申請箇所が家屋のごく一部というケースが散見されました。これは業界的な構造として、保険会社とお客様との間で、情報の非対称性があるためで、この点を改善したいと考えて起業しました。
実際に、2019年10月に千葉県を襲った台風では、家屋全体が影響を受けていても屋根の損壊などわかりやすい箇所しか申請しないケースが頻発していました。私たちがお客様の立場に立って査定をすることで様々な損壊が見つかり、何倍もの保険金が出た事例はたくさんあります。このときも当社のサービスの必要性をより確信することになりました。
―本来なら支払われるべき保険金が宙に浮いている状態なんですね。
尾前 保険料は年々高くなっていますし、本来受けられるはずの支払いを受けないのは本当にもったいないことです。25年間保険料だけを払って終わりという事例はそれこそ数限りなくあると思います。何より、申請できることを知っている人は保険金をもらえ、知らない人はもらえない。情報リテラシー、保険リテラシーによって得する人と損する人がいるのは公平ではありません。火災保険のプロである私たちが知恵をお貸しすることで、そうした現状を変えていきたい。ひとりでも多くの方が公平に保険金の受け取りができるよう、貢献するのが当社のミッションです。
―保険会社にとっては、保険金の請求が増えて経営が圧迫されるという側面はないのでしょうか。
土井 2006年に大手損保の自動車保険で保険金の未払い問題が発生し、金融庁が保険会社にすべての保険契約者に対して契約内容の確認を実施するように通達があり、業界を揺るがす事態になりました。以降、どの保険会社も保険金の支払いもれに敏感になっており、約款に基づいた正当な請求には積極的に支払う姿勢になっています。保険金の支払い増による経営の圧迫はあるのでしょうが、それ以上にコンプライアンスを守ることを重視するようになっていますから、当社のサービスは保険業界が目指す方向に適っていると確信しています。

―御社と同様に、火災保険の調査や申請を支援するサービスを手がける企業はどれくらいあるのでしょうか。
尾前 同業他社は数十社くらいでてきています。ただ、工務店さんなどが副業的に行っている場合も多く、保険約款を正しく理解していないところもあると聞いています。たとえば、「ここが壊れているので工事代は100万円」と保険金がおりるかどうかわからない段階で契約し、実際に保険金でカバーしきれないケースも。損保会社の社員だった当時、そういう事例を目にし、業者に対して注意喚起をしたこともあります。保険代理店事業を手掛けている会社であれば、一定の知識を有すると思いますが、大手損保会社で火災保険の損害査定の経験を積んだプロたちと工業大学出身で建築の専門知識を持つ社員による申請支援サービスであることが、当社の強みですね。
―クライアントが安心して依頼できるプロは、災害時にはとりわけ心強い存在だと思います。サービスの費用は、どういう体系になっているのでしょうか。
土井 費用は調査の段階ではいただかず、保険金がおりた場合の成功報酬です。手数料は支払われた金額に対して35%。業界平均として、安い会社は30%、高いところは50%という会社もあり、当社は平均的な割合だと思います。他社との最大の違いは、私たちは保険会社出身で保険金のお支払いをする側の立場でしたので、専門的な知識をもって建物の損害を査定できることです。壊れた箇所の修繕費をもとに算出する査定とは似て非なるもので、おりる保険金額も変わってきます。ありがたいことに、5%高くても当社に頼みたい、検討すればするほどそう思った、と依頼される方は多くいらっしゃいます。
尾前 当社には明確なポリシーがあるのですが、調査依頼をいただいて現場に足を運んだ段階で、申請ができる箇所がどこで、どれくらいの保険金が下りるのか、工事費用がどれくらいかかるのかが大体わかります。場合によっては、そこから当社に手数料を払うとお客様の手元に修繕費相当額が残らなかったり、足が出てしまうといった場合は、報酬を必ず辞退します。お客様のためになりたいと思っての事業ですから、お客様の手元にお金が残らなければ、やるべきではないですよね。その場合も、お客様には「私たちが書類を作ったり、写真を撮ったりすることはできないですが」とご説明したうえで、保険金の申請の仕方をお教えしています。その後、ご自分で申請して保険がおりた方からも大変喜ばれることが多いです。
―他の会社はそういうケースでも報酬を受け取っていると聞きますから、尾前損害調査オフィスさん独自のスタンスですね。
土井 これは現場に行くすべての社員に守らせています。「契約をとれば利益になるのに」と思われるでしょうが、このスタンスを貫くことで、中長期的には、お客様から依頼してよかった、信頼できる、という信用をいただくことに繋がっています。当社のクライアントはお客様からの紹介がほとんどですから、お客様に信用いただくことを徹底していくことに誇りをもっています。事実、常にお客様の目線に立ち、人とのつながりを大切にしながら事業に取り組んできたからこそ今があると思っています。


―御社の社員構成と、それぞれの社員への思いをお聞かせください。
尾前 私と土井、そして今年30歳になる社員が3人です。もともと個人事業主で事業をスタートし、今の社員は業務委託という形で一緒に仕事をしていたのですが、去年の3月、株式会社に改組する際に業務委託のままか正社員になるかを訊ねると、業務委託の方が実入りがよいにも関わらず3人とも「一緒にやります」「ついていきます」とふたつ返事で言ってくれて。本当にうれしかったですね。
土井 3人ともことあるごとに「入ってよかった」「この仕事ができてよかった」と言ってくれています。「思いがけない保険金がおりた」とお客様に感謝されるのがうれしい、仕事が楽しい、と。私たちもそうですが、仕事をして「ありがとう」と言われる回数が多いので、やりがいが大きい。社員全員が同じ思いで仕事に向き合ってくれているのがうれしいですね。

尾前損害調査オフィスの北野康太さん、羽角元希さん、羽角雄基さん(左から)
ひとりひとりにも感謝の気持ちを伝えたいですね。羽角元希は、事業を立ち上げた時から1番に参画してくれた人間です。他の社員は彼の声がけがきっかけで事業に参画してくれました。他のメンバーが困っていると自ら前線に出るのを買って出るような人情味の強い性格で、彼がいなかったらおそらく今の社員同士の結束はなかったのではないかと感じています。
尾前 3人とも本当に素直な人柄です。北野康太には、それまでまったく縁がなかった和歌山で、2か月ホテルに宿泊するという大変な出張を頼んだのですが、嫌な顔ひとつせずに引き受けてくれて。本当に助かりました。
もうひとりの羽角雄基は羽角元希の双子の兄弟で、去年1月子どもが生まれた直後に入社しました。当社のような立ち上げ間もないベンチャー企業への入社を許してくれた奥様にもすごく感謝しています。当社の事業柄、明日から急に出張ということはよくあることなのです。子育ての大変な時期であるにもかかわらず、羽角は快く応じてくれ、何より、彼を送り出してくれる奥様には頭が上がりません。いつの日にか、奥様にも入ってよかったね、と思ってもらえる会社にしていきたいです。
土井 うちの会社自体がまだ力不足なので、ご家族は心配もあると思うのですが、社員になることに賛成してくれたことは本当にありがたい。その信用に報いるためにも、彼らにきちんとした道筋を作って、「いい仕事しているね」「稼げてよかったね」と思ってもらえるようにしたい。ビジネスのなんたるかを私たちなりに伝え、鍛え上げることでお返ししたいと思っています。
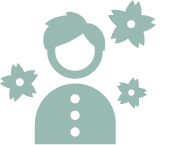
―保険の損害調査コンサルティングは契約者の利益に資するとともに、保険というシステムの公平性を担保するという社会的意義のある事業だと思います。業界の課題や将来像をお聞かせください。
土井 同業他社は小規模事業者がほとんどで、しかも保険のプロではない方も多い。たとえば美容師さんのように技術を証明する国家資格があって、どの会社に依頼しても一定水準以上のサービスが受けられる業種ではありません。実際、同業他社さんが自分たちではできないから、と私たちに損害調査を依頼してきたこともあります。現状、質が高くない損害調査報告が保険会社にあがっていくことで、この仕事の価値が低く見られる懸念もあります。他社とも協力できるところはお互いに連携して取り組んでいくことで、業界のスキルを底上げしていく必要があると考えています。
尾前 調査フローの基準をきちんと作って、業界関係者を啓蒙するようなことも考えていきたいですね。また、この事業を始めた時からのビジョンがあります。保険金は、本来であれば100%お客様が受け取れるものです。その一部を私たちがコンサルティング料としていただいていますが、本当だったら1円もいただきたくないのです。お客様から報酬をいただかずにできる方法はないだろうか。またはいただいた利益を災害寄付金に充てられるような仕組みができないだろうか。社会に貢献できる形を作ることを最終的な目標に置きながら、これからも真摯にビジネスに取り組んでいきたいです。
