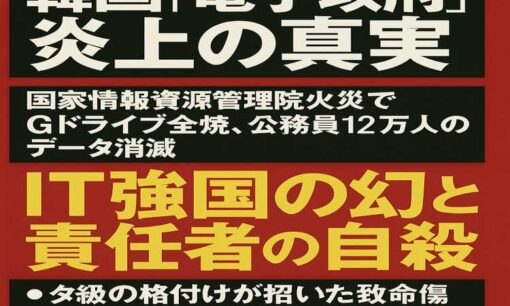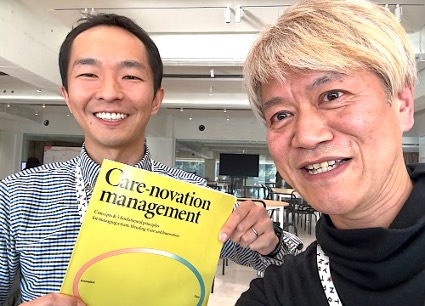歴史小説『小説 上杉鷹山』などで知られる作家の童門冬二氏が、96歳でこの世を去った。彼の人生と作品、社会に与えた影響を振り返ります。
2025年1月13日、歴史小説『小説 上杉鷹山』で知られる作家の童門冬二(本名・太田久行)氏が昨年、がんのため96歳でこの世を去った。遺族の意向により、死去から1年の節目にその事実が公表された。彼の死去は、長年にわたって日本の歴史と経営学を融合させた作品を世に送り出し、多くの人々にリーダーシップや地域社会のあり方を考えさせる機会を提供した功績を再認識させる。
童門氏は東京都庁の職員として広報室長や政策室長を歴任。美濃部亮吉知事のもと、都政改革を支えた人物である。彼の作家活動は都庁在職中から始まり、1979年に退職して専業作家としての道を歩んだ。
上杉鷹山と二宮尊徳から学ぶリーダーシップ
童門氏の代表作『小説 上杉鷹山』は、財政危機に直面していた米沢藩の改革を実現した藩主の姿を描き、経営学的視点からリーダーシップを考察する作品だ。藩主として、家臣や領民の信頼を集めながら、改革の厳しさに立ち向かった鷹山の姿勢は、現代の企業経営にも通じる教訓を示しているのではないか。
童門氏は、歴史の中に現代社会に必要なマネジメントのヒントを見出した人物だ。組織改革において重要なのは、情報の共有とリーダーの風度であると語っていた。その考え方は、二宮尊徳の教えにも通じる。尊徳のリーダー像は「風度」を持つ人物――すなわち、部下や周囲の人々から「この人が言うなら」と信頼される存在であることを重視した。
都政での経験を生かした執筆活動
東京都職員としての経験も、童門氏の作品の基盤となった。広報課長時代、都知事のスピーチライターとして携わったエピソードは、彼の作風に深い影響を与えた。ある時、彼が持参した60枚のスピーチ原稿を知事に捨てられ、「もっとシンプルに、耳で聞いてわかる原稿を書け」と言われたことがあった。その経験が、読者に伝わりやすい文章を書く訓練となった。
また、彼の篤志家としての一面も見逃せない。童門氏は、刑務所で受刑者が読む『人新聞』に寄稿するなど、社会の隅々にまで関心を寄せていた。彼の筆は、社会の底辺にいる人々にまで希望の光を届けようとする姿勢が見て取れる。
組織改革と人間の本質を探る
童門氏が繰り返し説いたのは、組織改革において重要なのは「民のために働く」という理念だったように思う。米沢藩主・上杉鷹山が、「領民がいるから武士の生活は成り立っている」と述べたように、リーダーは常に人々の生活を第一に考えるべきだと説いた。さらに、細井平洲の「情報共有」の重要性も強調した。
組織内での情報共有が生産性向上に寄与するという考え方は、都庁時代に知った『ホーソン実験』からも学ぶことができると語っていた。この実験は、1920年代にアメリカのウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で行われたもので、労働者の生産性が職場環境よりも、管理者や研究者が労働者に注目し、話を聞くことで向上することが明らかになったという実験。人間関係や情報共有が職場のモチベーションや生産性を左右する重要な要素であることが示された。
童門氏は、リーダーが組織内での情報共有を進め、メンバー一人ひとりに注目することが組織改革の成功につながると考えていたのではないか。
二宮尊徳の「風度」に学ぶ
また、童門氏と言えば、二宮尊徳の作品も有名である。二宮尊徳は、もちろん下野国桜町領の復興を手がけた人物。彼は、自らの田畑や家財を売り払い、復興に命を懸けた。その姿勢が村民の信頼を得て、「二宮先生のおっしゃることなら」という評判を広げた。
童門氏は、二宮先生のおっしゃることなら、という「風度」がリーダーにとって最も重要な資質であると考えていた。人を動かすのは「何を言うか」よりも「誰が言うか」であり、信頼される人物こそが組織を変える力を持つ、と。
童門氏の死去は、単なる作家の逝去にとどまらず、歴史から学び、社会に生かす視点の重要性を再確認させる出来事でもある。童門冬二氏が残した教えは、これからの時代においても光を放ち続けるだろう。
何より、個人的に大好きな作家だった。自分が辛かった瞬間に童門先生の文章に大いに勇気づけられたことを思い出す。本当にありがとうございました。いま、先生の本をきちんと読みたいと思います。