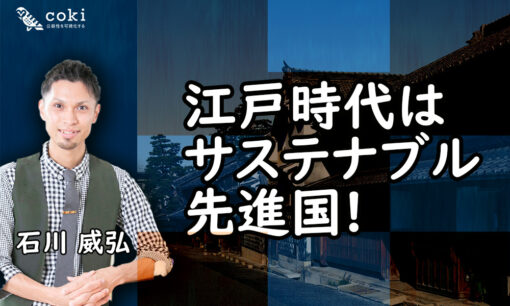新スマート寄付アプリ「GOJO」始動

国内のNPOや社会課題を支える仕組みづくりを進めるコングラント株式会社(大阪市西区)は5月22日、寄付体験を革新するWEBアプリ「GOJO(ゴジョ)」をローンチした。
従来の寄付手続きの煩雑さを大幅に削減し、さらに寄付するたびにポイントが貯まる仕組みを導入することで、“寄付する人がもっと楽になる”ことを目指すという。
「1タップ100円」から気軽に支援

会見に登壇した代表取締役CEOの佐藤正隆氏は「日本では寄付が“善意”に委ねられがちで、日常的な行動になりにくい。そこで、ユーザーに寄付体験そのものを楽しんでもらう工夫をする必要があると考えた」と説明。
新アプリ「GOJO」は、あらかじめカード情報などを登録しておけば、SNSやアプリ内で気になった団体・活動に1タップ100円から寄付が可能。煩雑な個人情報入力を省き、ユーザーが“つまずかない”設計にこだわったという。
また、寄付額に応じて最大10%以上のポイントが付与される仕組みも特徴だ。貯まったポイントはカフェ利用などに交換できるほか、さらに別の団体への寄付に充当することも可能。佐藤氏は「寄付者が何度でも“寄付してよかった”と感じられる体験を作りたかった」と語る。
企業版の狙い 非財務情報を可視化し、従業員参加を促進
会見の後半では、企業向け“従業員寄付”のプラットフォームとしての「GOJO」の活用法が紹介された。企業事業部責任者の執行役員COO 法人事業部部長の高橋敦彦氏によると、近年はSDGsやESG投資などの機運が高まり、大企業を中心に「社員の社会貢献参加を促したい」「寄付やボランティアなどの取り組みを一元管理したい」という声が増えているという。
社員の寄付・ボランティアをデータ化
「GOJO」は、企業で導入すると従業員がどの活動に寄付・参加しているかをダッシュボード上で匿名ベースで可視化できる。社員同士の行動が見えることで「社内で共感の輪が広がり、“自分も参加してみよう”という後押しにつながる」と高橋氏。さらに、寄付やボランティアなどは企業の非財務情報(いわゆる人的資本や社会貢献実績)として開示が求められる傾向があるが、これを「GOJO」のデータで一元的に確認・整理できるメリットも強調している。
従業員エンゲージメントの向上に
「オンライン寄付なら、ボランティアと比べてハードルが低い。誰でも気軽に社会貢献に関わることで、社員一人ひとりのエンゲージメントも高まる」と高橋氏は述べる。実際、参加率が上がれば“社内の空気”が大きく変わり、企業としての社会的評価につながるだけでなく、社員のモチベーションや帰属意識を高める効果が見込めるという。
ピースウィンズジャパン町浩一郎氏と対談 認知・継続寄付の壁

会見の後半では、NPO法人ピースウィンズジャパン(以下「PWJ」)コミュニケーション部 広報マネージャーの町浩一郎氏が登壇し、佐藤氏との対談が行われた。PWJは1996年の設立以来、国際人道支援や災害支援事業、犬の保護・譲渡活動「ピースワンコ」など幅広い領域で活動する団体だ。
町氏は、NPOの資金源は助成金や寄付が中心で、特に日々の活動を支える継続寄付が重要だと強調。ただし「認知度を上げるために投資が必要でも、どうしても運営費が圧迫される。小規模なNPOほど露出も限られ、支援につながりにくい」と語る。さらに、企業からのボランティア参加にはコーディネート費や現場リスクが伴い、NPO側の人件費などをどう捻出していくかも課題だという。
対して佐藤氏は「日本にはまだ知られていない優良なNPOがたくさんある。“寄付する側”がもっと選択肢を見つけやすくなる仕掛けと、団体側が投資しやすくなる仕組みが必要。GOJOでは団体掲載費用を追加で取らないのも、その一環」と応じた。
今後の展望

GOJOは今後、税制優遇手続きのオンラインサポートや、ボランティア募集・物品寄付の導入も計画している。佐藤氏は「企業連携をさらに広げるとともに、NPOや一般ユーザーの皆さんの声を取り入れて進化させていきたい」と述べた。
また、高橋氏は「従業員寄付の参加率が上がれば、企業価値は高まる。寄付やボランティアといった行動が可視化されることで、社員同士の連帯感を育み、社会貢献の裾野が広がると期待している」と結んだ。

寄付の9割が「見えない」まま終わっているという現実

株式会社Sacco 代表取締役。一般社団法人100年経営研究機構参与。一般社団法人SHOEHORN理事。株式会社東洋経済新報社ビジネスプロモーション局兼務。週刊誌・月刊誌のライターを経て2015年Saccoを起業。
連載:日経MJ・日本経済新聞電子版『老舗リブランディング』、週刊エコノミスト 『SDGs最前線』、日本経済新聞電子版『長寿企業の研究』