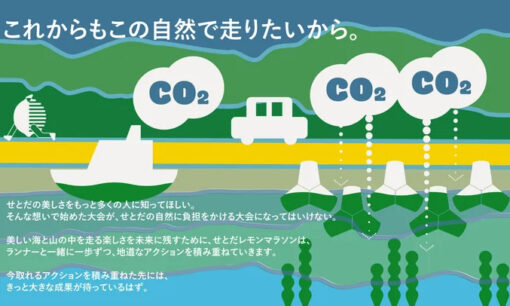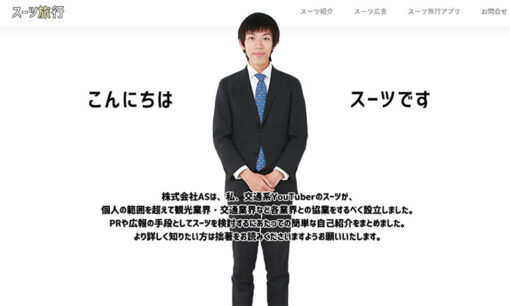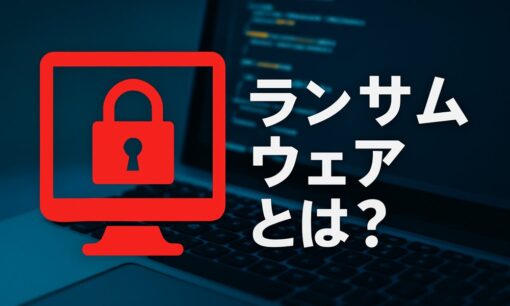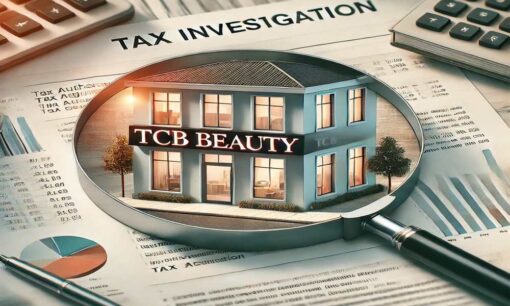義務教育は「無償」とされている。しかし、入学時にかかる制服代や給食費、修学旅行などの費用は家庭が負担しており、その総額は年々重くのしかかっている。こうした「隠れ教育費」は子どもの学びの機会を左右しかねない実態として、いま再び注目を集めている。中でも高額な制服代をめぐっては、自治体による無償化の動きが広がりを見せており、教育のあり方そのものを問い直す契機ともなりつつある。
無償のはずの義務教育 見えにくい「教育コスト」が家庭を圧迫
義務教育は「無償」とされている。しかし実際には、制服、体操服、文房具、給食費、修学旅行などにかかる費用は家庭の自己負担となっている。こうした支出は「隠れ教育費」と呼ばれ、子どもの進学や学びの機会を左右する要因にもなりつつある。
中でも制服代は高額で、保護者の家計に与える影響が大きい。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2023年に実施した調査では、公立中学1年生の制服代が平均5万6331円、高校1年生では7万615円にのぼった。入学時に保護者が負担する教育費の中で、制服代が最も重くのしかかる実態が明らかになっている。
「隠れ教育費」の主な内訳
下図は、家庭が負担する隠れ教育費の代表的な項目を割合で示したものである。
(※以下はモデルに基づく試算)
- 制服代:30%
- 体操服・運動着:15%
- 文房具・学用品:10%
- 給食費:20%
- 副教材:10%
- クラブ活動費:10%
- 修学旅行・遠足費:5%
制服は隠れ教育費の中でも突出した割合を占めており、これが無償化政策の対象として注目される背景でもある。
なぜ制服はこれほど高いのか?
制服の価格が高止まりしている背景には、以下のような要因が複雑に絡んでいる。
● 独自デザインと指定販売体制
学校ごとに異なるデザインが採用され、大量生産が難しい。また販売業者が限定されており、競争原理が働きにくい構造となっている。
● 高機能素材と縫製技術
防シワ・耐久性・速乾など、日常使用に耐えるための高機能素材を使用しており、衣料品としての製造コストが高くなる。
● セット販売による一括負担
ブレザー、シャツ、スカート(またはスラックス)、ネクタイ、ベスト、夏冬の衣替え用と、多数のアイテムを一括で揃える必要がある。
● 地域業者による価格支配
地域によっては長年同一業者が納入を担い、価格競争が起きにくい状況にある。
● ブランド化・ファッション化
一部の私立校では制服にデザイナーを起用し、ブランド価値を打ち出している。これが高額化の一因ともなっている。
制服無償化に踏み切る自治体が増加
こうした家計への負担を軽減すべく、全国で制服無償化の動きが広がっている。北海道北斗市では2023年度から中学校5校の新入生を対象に制服代3万4100円分を市が全額負担。東京都品川区は2025年度から新入生1930人を対象に制服を無償化する予算を可決した。
奈良県香芝市では、小中学校の新入生を対象にそれぞれ上限額(中学4万円、小学2万円)を設けて支給。熊本県御船町や南小国町でも同様の制度を実施している。ただし、多くの自治体では「1回限りの補助」にとどまっており、成長や破損に伴う買い替えへの支援は今後の課題である。
「制服そのものの必要性」にも再考の声
名古屋大学大学院の内田良教授(教育社会学)は、「制服は隠れ教育費の中でも突出して高く、3年間で使い切って終わるため持続可能性にも乏しい」と指摘。「全額でなくとも部分的な補助には意義がある」と評価する一方で、「制服が本当に必要なのかという根本的な議論もすべき時期に来ている」との認識を示した。
形式の平等が実質の格差を覆い隠しているとすれば、それは制度の問い直しを迫る信号でもある。各地で進む制服無償化の動きは、教育のあり方そのものを見直す契機となるかもしれない。