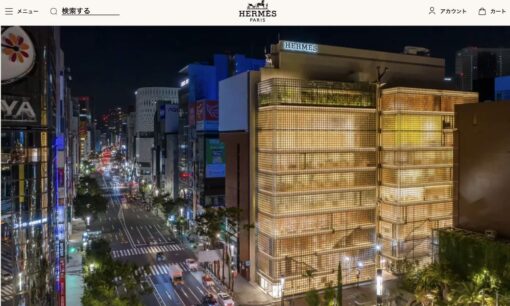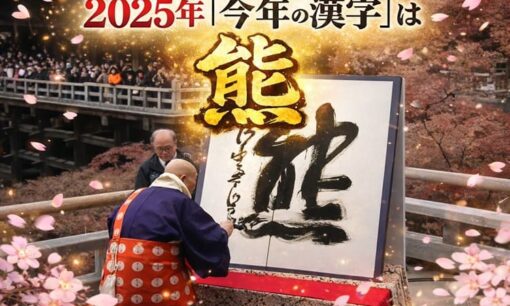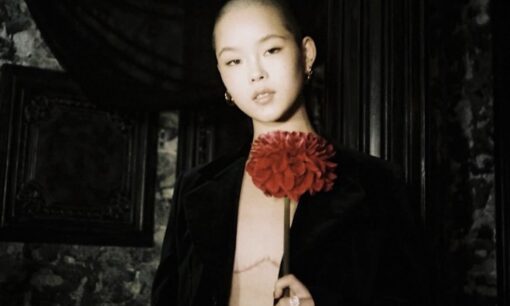東京世界陸上、男子4×100mリレー決勝。雨の国立競技場で、日本の「リレー侍」は38秒35の6位に沈んだ。桐生祥秀の足つりが象徴的に語られたが、敗因はそれだけではない。個の走力不足、他国のバトン精度向上、そして攻めの設定が裏目に出た。技術一辺倒では勝てなくなった現実が、ここにはあった。
国立競技場に響いたため息
9月21日、東京世界陸上の最終種目。スタンドを揺らす歓声と雨のしずくの中、日本の「リレー侍」は6位に沈んだ。タイムは38秒35。過去には銀・銅メダルを手にし、日本のお家芸とまで呼ばれた4×100mリレーが、なぜ表彰台から遠ざかったのか。答えはひとりのミスではなく、構造的な問題に潜んでいた。
桐生祥秀の“足つり”は象徴にすぎない
3走を任された桐生祥秀は、スタート直後に右ふくらはぎをけいれん。「僕の責任です」と涙ながらに語った。雨に合わせて厚底から薄底へとスパイクを替えたことも影響したと自己分析する。しかしスプリットを見れば、桐生の区間は9秒71と最下位。それでも仮に米国並みに走ったとしても、メダルには0.14秒届かない計算になる。つまり、敗因を桐生一人に帰すことはできないのだ。
日本の“強み”が世界に追いつかれた
これまで日本は、アンダーハンドパスという独自のバトン技術で走力差を補ってきた。ほんの0.1秒を削り出す精度の高さが、世界の舞台でメダルを可能にしていた。しかし今回、上位国はいずれも大崩れなく、むしろ流れるようなバトンワークを見せた。かつての日本のアドバンテージは縮小し、純粋な走力勝負の比重が大きくなっている。
個の力不足という冷徹な現実
短距離コーチの信岡沙希重氏は「100mで準決勝に進む選手がいない」と率直に語った。今大会、日本は誰一人として個人100mでベスト8に残れず、準決勝すら届かない状況だった。メダルを獲得した米国・カナダ・オランダはいずれも複数の9秒台ランナーを揃え、自己ベストの水準からして日本を上回っていた。リレーはチーム競技であると同時に、個の速さの総和でもある。その差が、表彰台と入賞の境界線になった。
攻めの設定が裏目に出た決勝
予選は「安全バトン」で通過した日本。決勝では1-2走を1.5足長、2-3走を0.5足長伸ばす攻めの設定で挑んだ。ウォームアップでは手応えがあり、「0.4秒は縮められる」と選手と共有していた。しかし本番は雨、歓声、プレッシャーのなかで噛み合わず、加速のつなぎが不安定になった。リスクを取る選択が再現性を欠いたことが、痛恨の結果につながった。
次に必要なもの
「バトン技術だけでは勝てない」。この事実を突きつけられた一戦だった。今後、日本が世界で再び戦うためには、
- 9秒台ランナーを常時揃える層の厚さ
- 雨や風を想定した可変オーダーと用具の最適化
- アンダーハンドを超える新たな工夫
が欠かせない。リレー侍の強さを信じる観客の声援はまだ熱い。その期待に応えるには、個と技術の両輪強化が必須だ。
悔しさの先に見える、新たなスタートライン
雨の国立で流れた涙は、敗北ではなく再出発のしるしだろう。桐生、小池、栁田、鵜澤。彼らが背中で示した「悔しさ」は、未来のスプリンターたちに引き継がれていく。メダルを逃した夜を境に、日本のリレーは次の段階へ踏み出している。