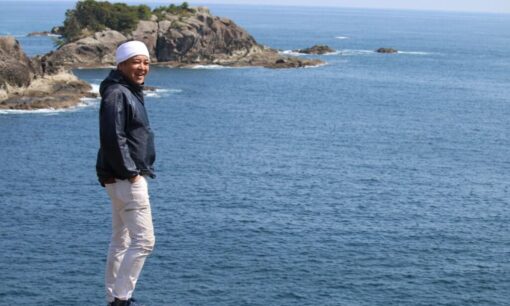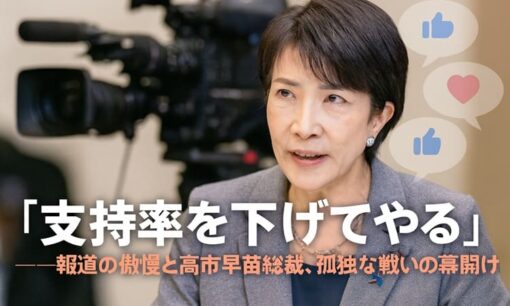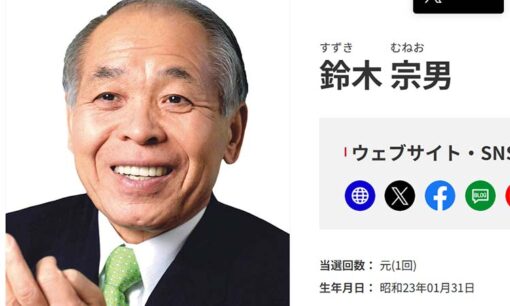教員による性暴力を防ぐため、文部科学省が導入した「教員によるわいせつ処分歴データベース」。法律で確認が義務化されたにもかかわらず、2024年度の全国調査で、私立学校・幼稚園の約75%がこのデータベースを採用時に活用していなかったことが判明した。
教員採用におけるチェック体制の甘さ、制度運用の形骸化、公私間の運用格差… 文科省は8月にも全国調査に乗り出すが、制度が機能するためには何が求められているのか。
私立校の約75%が「未確認」。制度化から2年で浮かんだ運用不備
「教員による児童生徒性暴力防止法」は、2022年に施行された。わいせつ行為などにより教員免許を失効した者が再び教育現場に戻らないよう、採用時に専用のデータベースを活用し、確認を義務づけた制度である。
ところが、2024年度の調査で明らかになったのは、私立学校や私立幼稚園を運営する法人のうち、約75%(およそ5,480法人)がこの確認作業を怠っていたという実態だ。制度施行から2年が経過しても、義務化された確認が現場で徹底されていない現状は、制度そのものの実効性に疑問を投げかける。
公立でも発覚、採用前チェックの“抜け落ち”
名古屋市教育委員会も、2022年度以降に採用された常勤・非常勤あわせて5,932人の教員について、データベースを用いた確認を行っていなかったと発表。文科省はこれを重大な問題と受け止め、阿部俊子文科相は「二度とこのようなことがないよう猛省していただきたい」と強く非難した。
さらに、横浜市や東京都内の学校では、教員による盗撮や、SNS上での不適切な画像共有といった事件も相次ぎ、教育界全体に対する信頼が揺らいでいる。制度の不徹底は、実際の事件を未然に防げなかった可能性にもつながりかねない。
私立校が“空白地帯”となる構造的背景
公立校では教育委員会が人事を一元管理しているのに対し、私立校は各学校法人の自主性が高く、制度の運用にも温度差があるとされる。確認作業の義務があるにもかかわらず、現場レベルでは「制度の存在を知らなかった」「作業負担が大きい」といった声も少なくない。
また、現時点で未確認に対する罰則規定や行政指導の仕組みが明確でないことも、制度形骸化の一因となっている。制度設計はあっても、実行と監視の体制が整っていなければ、教育現場における“空白地帯”は容易に生まれてしまう。
文科省、8月から全国調査へ。制度見直しも視野に
こうした実態を受けて、文科省は8月にも全国すべての学校種別を対象とした調査に着手する方針を明らかにした。私立・公立を問わず、採用時のデータベース確認が行われているか、義務を履行しているかを包括的に調査し、その結果次第では制度の見直しや、監視・罰則体制の強化も検討される。
文科省関係者は「制度が“有名無実”とならないよう、公正な運用の担保が不可欠」と述べている。
制度運用を支える“実効性”とは何か
この問題は、教育現場にとどまらず、人を採用するすべての現場で共通する課題を浮かび上がらせる。コンプライアンス遵守が企業においても厳しく求められるなか、「制度はあるが、運用されていない」「記録はあるが、確認されない」といった事態が続けば、信頼性の喪失や重大な人権侵害にもつながりかねない。
公的制度の信頼を支えるのは、最終的には現場の実行力と、それを継続的に監視する仕組みである。教育現場の再発防止に向けた全国調査が、単なる確認作業で終わるのではなく、制度の再構築へとつながることが求められている。