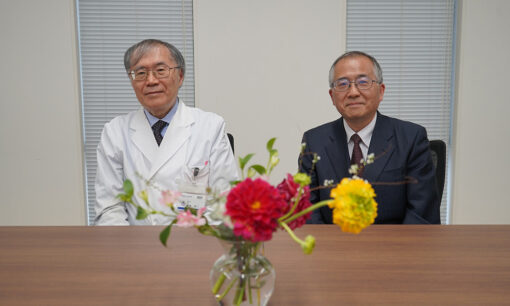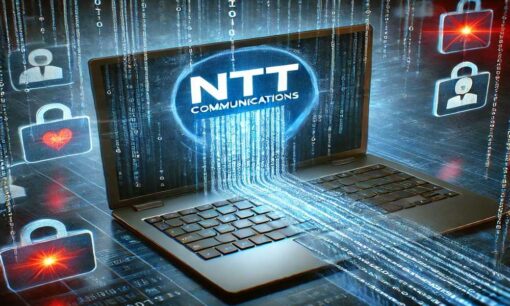医療界の“利権構造”に音喜多駿が切り込む 令和の虎・林尚弘も医師役で出演

2025年7月14日、参議院東京選挙区候補の音喜多駿氏が公開したショート動画がSNSで大きな反響を呼んでいる。内容は「医療法人会長と政治家が料亭で癒着し、国民に2万円配れば喜ぶ」といったシーンを含むパロディ風の演出で、医療界と政治の癒着を風刺したものだった。
注目を集めたのは、そのなかで“医師役”として登場したのが、YouTube番組『令和の虎』で知られる林尚弘氏だった点だ。林氏はスーツをきた医師会関係者として、診療報酬制度について語る役柄を演じている。
動画の狙いは、企業・団体献金が医療政策に与える圧力をメタファーとして表現し、社会保障制度が一部団体の利害により歪められている現実に警鐘を鳴らすことだった。だが表現が過激だったこともあり、「医療従事者全体への批判」と誤解され、SNS上で“炎上”する事態となった。
開業医と勤務医の格差、診療報酬制度の歪みとは
動画は主にクリニックなどの「開業医」の利権を皮肉ったものだが、病院の「勤務医」のようなアカウントまで過剰に反応している。SNSでは日ごろ開業医をくさす勤務医たちも、今回の動画にはおおむね批判的な模様だ。
ただ、急性期医療の病院の勤務医は激務であるし、その割に給料も低く、寧ろ待遇改善をはかるべきものであることは多くの人が感じているところだろう。問題提起の焦点は、開業医と勤務医のあいだに存在する構造的な格差にあてるべきだ。
急性期病院や大学病院、自治体病院などで働く勤務医たちは、長時間労働と人手不足に悩まされながら、日々現場で奮闘している。ところが、診療報酬制度に支えられた一部の開業医や自由診療主体のクリニックは、高収益を上げているケースもあり、医療界内部における「温度差」は看過できない。
制度の根幹にある診療報酬は、診察回数や検査数に応じた「出来高払い」が基本で、治療成果ではなく“処置量”に応じて報酬が支払われる。これにより、医療機関には「治しすぎると儲からない」という逆インセンティブが働きやすい構造があると指摘されてきた。
変わらない診療報酬の点数に病院は崩壊寸前
また、医療制度の枠組みのなかで、勤務医の報酬や労働条件が十分に報われているとも言い難い現実がある。診療報酬改定は2年に一度と定められているが、医療材料費や人件費の高騰に報酬水準が追いつかず、厚生労働省の調査でも全国の7割の病院が赤字状態にあるとされている。医療関係者のあいだでは、「制度の歪みを解消せずに現場だけに負担を押し付けている」との不満が渦巻いている。
「このままでは立ちいかなくなることは明白。診療報酬の点数をあげていかなければ早晩、日本の医療制度は崩壊する」(大学病院勤務医)
一方、病院と一口に言っても、その性格はさまざまだ。大学病院は高度医療や研究、専門医の養成を担い、文部科学省と厚生労働省の両方が関与する。一方、自治体病院は都道府県や市町村が設置し、地域医療や災害医療を支える公益性の高い存在だ。
民間病院やクリニックの多くは医療法人が運営し、保険診療に加えて自由診療を行うなど、比較的自由度の高い経営が可能である。こうした病院の違いは、制度改革を語るうえで無視できない要素だ。
「急性期医療を担う病院の場合、公立病院には1床あたり1日1万円以上の補助金が支出される。仮に病床数200の病院であれば、毎日200万円以上のお金が診療報酬以外に入る計算に。補助金が投入されない民間病院との間に大きな格差が生じている」(四病協関係者)
勤務医と開業医でまったく違う現実。開業医優遇をやめるべき
また、勤務医と開業医の違いは、単なる職場の違いにとどまらない。勤務医は大学病院や急性期病院などに所属し、医局の人事に従って転勤や当直をこなす厳しい労働環境に身を置く。一方、開業医は自身のクリニックを構え、診療時間や経営方針を自ら決定できる立場にある。医局を離れた「脱藩医師」が自由診療や特化型クリニックで成功を収める姿も珍しくない。
こうした構造のなかで、勤務医からは「開業医は責任の重さや時間的拘束が少ないのに報酬が高い」といった不公平感も根強い。とりわけコロナ禍では、勤務医が感染リスクを負って最前線に立つ一方で、開業医が一時休診する事例が目立ち、医師間の分断が露わになった。医療制度改革を議論する際、この見えづらい“内部格差”にも目を向ける必要がある。
医療団体のなかには、「すべての開業医が利権を貪っているわけではない」と反発する声もある。もちろん地域医療を支える誠実な開業医も多数存在する。しかし、制度を巧妙に活用しながら「政治的な力で既得権益を守る」構造があるのも否めない事実だ。
日本とヨーロッパの医療制度の違い 治すほど報酬が高い国々も
欧州諸国との制度比較からは、日本の医療制度がいかに“結果”を評価していないかが浮かび上がる。
スウェーデン、オランダ、イギリスなどでは、アウトカム(治療成果)ベースの報酬制度が導入されつつある。例えば、慢性疾患の重症化を防いだり、再入院を回避した場合に追加報酬が発生する設計になっている。
こうした制度では、単に多くの診察をこなすことよりも、「患者を健康にすること」に医療者が報われる仕組みが存在する。医療の質的向上を図るうえでは、医療機関におけるアウトカム(成果)評価を診療報酬に含めることが、世界的な潮流となっていることを思えば、日本の歪んだ診療報酬を改革する好機だろう。
今回の音喜多氏の主張には、こうした国際的な制度動向を踏まえた「構造改革」への問題提起の意図があった。
医クラの反応とSNSでの炎上「本質には誰も反論できない」意見も
動画公開後、SNS上では医師を中心にした“医クラ”界隈から批判が殺到。「侮辱的だ」「医療をわかっていない」といった声がX(旧Twitter)を中心に相次いだ。
一方で、冷静な意見も目立った。嚥下評価法で知られる勤務医・長神康雄氏は、「一部の団体が特定の利害を守りすぎているという指摘は事実。動画に本気で怒っているふりをするのは、社会保障費削減の議論で自分たちの既得権益が脅かされるからではないか」と投稿。炎上の本質が「制度設計」への不安に起因していることを指摘した。
SNSでは「キレているのは動画そのものではなく、“割を食う改革”の中身だ」という意見も多く、建設的な議論の必要性を訴える声も広がっている。
診療報酬改定と赤字病院 制度疲弊を止めるために必要な対話
もう一度重ねるが、日本の診療報酬は2年に一度の改定が制度化されているが、実質的な上昇幅は限られ、医療材料費や人件費の高騰には対応しきれていない。厚生労働省のデータによれば、全国の病院のうち7割が経常赤字状態にあり、制度の持続可能性は極めて厳しい局面にある。赤字に耐えきれず閉院を余儀なくされる中小病院も増えており、医療アクセスそのものが危機に瀕している地域も少なくない。
こうしたなか、医療制度の透明化とインセンティブの再設計を求める声が高まっている。自由診療の柔軟な活用や、成果連動型報酬への転換も含め、制度疲弊を止めるための包括的な改革が急務だ。
政治と医療が向き合うべきは「制度の再構築」
音喜多氏は「表現の一部が言葉足らずだった」としてSNS上で謝罪しつつも、「医療従事者全体を否定する意図は一切ない」と繰り返し説明した。医療現場の疲弊を知ったうえで、制度改革の必要性を訴えたのだと主張する。
政治と医療が対立するのではなく、共に制度の矛盾に向き合い、より公正で持続可能な仕組みを構築すること。そのためには「越えてはいけないライン」を恐れず議論する勇気と、現場の声に耳を傾ける対話の姿勢が必要とされている。