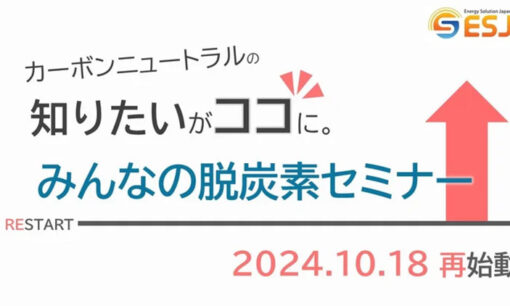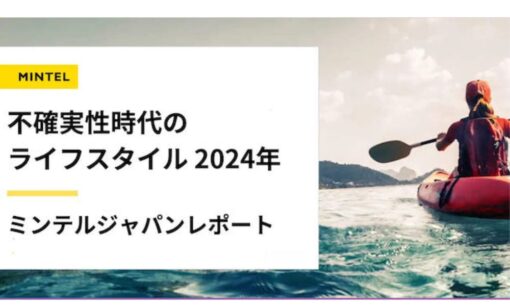JA全農あきた米穀部の児玉参与と秋田の田風景(画像提供:京浜急行電鉄株式会社)
JA全農あきた米穀部の児玉参与と秋田の田風景(画像提供:京浜急行電鉄株式会社)
持続可能な社会を築いていくためには、「食の安全・安心」は切り離せないテーマです。
京急グループも持続可能な社会の醸成に向けて様々な取り組みを行っていますが、なかでも「食の安全・安心」に対して、10年もの長きにわたり、応援している「あきたecoらいす応援プロジェクト」という活動があるそうです。
そこで、今回は、本活動と京急グループとの取り組みについて、JA全農あきた米穀部の児玉参与にお話をお聞きしました。
地球にやさしい“あきたecoらいす”から生まれた京急グループとの共創関係

児玉
JA全農あきた米穀部、参与の児玉徹です。主な業務としましては、生産者への技術指導や各JAとの現地試験、米の品質・食味についての調査・分析など、米作りに関わる業務全般に従事しています。
JA全農あきたは京急グループとの取り組みとして京急あきたフェアを行っていますが、どのようなことがきっかけで両者の関係ははじまったのでしょうか。

児玉
はじまりは10年以上も前に遡るのですが、京急グループさんに秋田県が誇る「あきたecoらいす」の普及を応援してもらうことになったのがはじまりです。
きっかけとなった「あきたecoらいす」とは使用農薬成分回数を50%以上削減し環境にも、消費者にもやさしい秋田米の総称です。
農林水産省が1997年に有機栽培のガイドラインを策定したことを皮切りに秋田県も特別栽培米の開発をすすめていき、何度も研究や実証実験を繰り返して生まれたのが、「あきたecoらいす」です。
農薬を減らすことで、食の安全・安心だけでなく、田んぼなどの周辺環境保全に、水中生物から鳥類までの様々な生物の生存環境を守ることができます。
鉄道事業を根幹とする京急グループ各社では、業種・形態に関わらず日頃から「安全・安心」の領域でも事業を展開しています。
京急グループにとって、使用農薬を50%以上削減した環境にやさしい「あきたecoらいす」は、まさに「安全・安心」のテーマに沿った題材でした。ちょうど収穫の時期が「京急あきたフェア」開催の時期と重なることもあり、秋田県とJA全農あきたとの取り組みがスタートしました。
京急グループさんと秋田県とのコラボレーションである「京急あきたフェア」ですが、どういったものなのでしょうか。

児玉
実際に京急グループさんに秋田県にお越しいただき、地域と交流をしながらお米の生産から販売までを一緒に行っていく取り組みです。
いつも私たちが食べているお米ですが、生産する際は田植えや稲刈りなど労働力が必要で、お米を収穫するということはとても大変な作業なのです。
これらの作業を地域の人達と交流しながら、生産する苦労を共に分かち合い、消費者にどのように届けていくのかを参加した皆さんと考えて取り組んでいくのがこのフェアの醍醐味であります。
このフェアは地域の高校生にも参加してもらっています。
例えば2018年までは秋田北鷹高校の農業クラブの生徒さん達、2019年は大曲農業高校の生徒さん達に参加してもらい、田植えや稲刈り、そして京急グループさんの協力のもと、駅構内での販促から販売まで行ってもらいました。
また、2021年と2022年には大曲農業高校の生徒さんとのコラボレーション企画として、みなさんで丹精込めて生産した秋田米を活用して高校生が考えたおにぎりのレシピを消費者の方々に販売したりもしています。
このフェアも2023年で15年目になるので京急グループさんには長い間お世話になっております。
 高校生が考えたおにぎりのレシピを京急グループと協力し、消費者にお届けする(画像提供:https://www.keikyu.co.jp/cp/akita2022/index.html)
高校生が考えたおにぎりのレシピを京急グループと協力し、消費者にお届けする(画像提供:https://www.keikyu.co.jp/cp/akita2022/index.html)
京急グループでは、空の玄関口である羽田エリアを沿線に持つ強みを活かしたPR・販促活動として、地方とタイアップしたキャンペーンを多く行っています。
秋田県との結びつきは、2008年5月にウィング高輪に秋田県のアンテナショップ「あきた美彩館」がオープンし、さまざまな取り組みを行い、次第に深くなっていきました。こうした背景があり、秋田県とのフェアを開催するに至りました。
高校生も貴重な体験をしたと思いますが、反響はいかがでしたか?

児玉
聞いていて、嬉しくなるような声を多数いただいています。参加した高校生としても、お米を作る大変さだけでなく、販売をする大変さまで体験できることが、よい学びの機会となっているようです。
高校生達にとって、将来、家の農家を継ぐにせよ、就職するにせよ、大学で学ぶにせよ、その時の重要な判断をする際の経験値として有意義な時間を、提供することができたと実感しています。
そして何より、お米作りを通して地域の人たち、京急グループの皆様と交流ができることが参加した人たちにとっての財産になるのではないかと思います。
また、私どもにとっても地域の高校生と接する機会というのはとても大きな刺激になっています。
「学生さんたちはこんなふうに考えるのか」「こういうこともできるね!」と彼らの作業を見ながら多くの学びを得ることもできています。
つまるところ、このフェアは高校生だけでなく、地域のJAや参加した大人達という多数のステークホルダーにとっても気づきの場として機能しているのだと感じますね。
あきたecoらいすの普及という観点以外での効果もあるのですね。とてもいい共創関係だと思いますが、児玉参与にとっては京急グループとはどういう存在でしょう?

児玉
とても頼りになる存在です。
お米というのは日本の代表的な主食ですので、様々な形で消費者にお届けできるというのは県にとっても、生産者にとっても非常に大切なことであり、ありがたいことであります。
2023年で15年目ですけどもこれからも継続してお付き合いしていきたい存在でありますし、もっと多くの消費者に届けることができるように共に頑張っていきたいパートナーでもあります。
地元の生産者、地域の高校生たち、そして消費者、このフェアを通じて様々な関係者と関わることができているので、今後も多くの人たちと関わり、太いパイプのようなつながりを持ち続けていきたいですね。
秋田の田園風景に赤とんぼがあふれる未来を想像して
2023年で15回目となるこの京急あきたフェアですが、意気込みをお願いします。

児玉
この「あきたecoらいす」は技術の立ち上げからはじまり、もう25年近く経ちます。
私自身、この「あきたecoらいす」の研究をはじめた当初、よく想起したのは「赤とんぼ」なのです。私が子供の頃はそこら中に赤とんぼが飛んでいました。
でも、最近は気候変動など温暖化の影響からか、赤とんぼを見る機会はとんと減ってしまいました。
環境に良い「あきたecoらいす」を普及していき、昔のように秋田の田園風景に赤とんぼが飛翔する未来を夢見ています。
そのためにも、より多くの人に秋田米を知ってもらい、消費者の皆様にもお米を食べてもらわないと。多くの方に消費いただき、持続的に生産していくことで秋田の田んぼは守られるのですから。
「あきたecoらいす」の栽培方法でお米を生産すれば生物多様性や田園風景を守っていくことができます。多くの皆様と協力していければ、決して実現できない未来ではないです。
その点で言うと、京急グループさんのおかげで生産者から消費者まで、こんなにも多くの方々と繋がることが出来ています。これは全国でも稀なことであると思っております。
「安全・安心」の観点からも生産者や消費者、そしてこれから先の未来を築いていく学生の人たちに少しでも明るい未来を創れていければいいなと思っています。
これからも継続して皆様と一緒に「あきたecoらいす」を、そして秋田県の人達の魅力を届けていきたいと思います。
京急グループさんとの取り組みで明るい未来、過ごしやすい地球、そして田園風景にあふれる赤とんぼの景色を共創していけると感じました。本日はありがとうございました。
 京急あきたフェアでは秋田県の皆様と共に持続可能な社会を創ります。(画像提供:京浜急行電鉄株式会社)
京急あきたフェアでは秋田県の皆様と共に持続可能な社会を創ります。(画像提供:京浜急行電鉄株式会社)
◎プロフィール
児玉 徹(こだま・とおる)
昭和22年2月10日生まれ 秋田県五城目町出身
東京理科大学理学部化学科卒
昭和45年4月 農林水産省農地局入省
昭和47年4月から秋田県農業試験場にて勤務、平成11年稲作部部長等を経て同18年場長を務めた。平成9年頃から秋田県の特別栽培米の基礎研究をすすめ、現地・実証試験をすすめ「あきたecoらいす」の誕生に貢献した。同19年から現職である全国農業協同組合連合会秋田県本部米穀部参与として勤務。