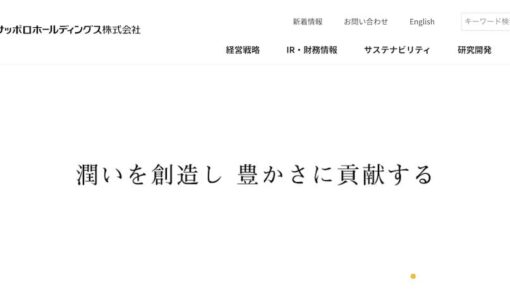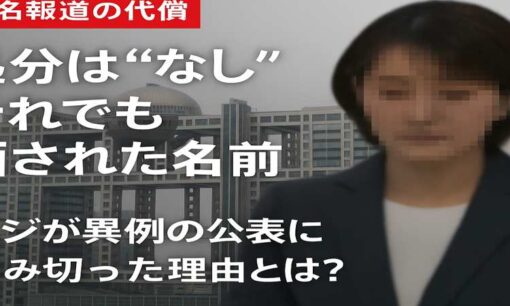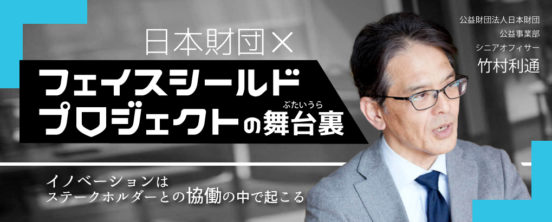日本のビール文化は、明治期の輸入品から始まり、戦後の大衆化、そして現在の多様化へと劇的な進化を遂げてきた。伝統的なラガーが主流だった時代を抜け、今ではクラフトビールや低アルコール、サステナブルな製造法など、新たな価値観が共存している。飲む人の“次の乾杯”のため、日本ビールは新しい物語を紡ぎ続けているのだ。
今回は、ビールの歴史と現状、さらに未来に描くビールの姿についても解き明かしていく。
日本のビールはどこから来たのか 歴史的背景と定着のプロセス
日本におけるビールの歴史は、幕末の長崎・出島にさかのぼる。オランダ商人が持ち込んだビールが最初とされ、当時は一部の外国人が楽しむ“異国の酒”にすぎなかった。
明治維新後の開国により、西洋文化が流入するとともに、ビールも本格的に日本へ根づき始めた。1870年には横浜に日本初のビール醸造所「スプリング・バレー・ブルワリー」が誕生。これが日本のビール産業の出発点となる。
その後、大正〜昭和初期にかけてビールの国産化が進み、戦時中の統制経済下では製造制限を受けつつも、人々の嗜好品としての地位を維持した。戦後の復興期を経て、高度経済成長とともに家庭への普及が進み、昭和30年代にはビールが“食卓の定番”として確立される。
アサヒ、キリン、サッポロ、サントリーといった大手4社が台頭し、均質なラガービールが全国に流通。いわゆる「ビール=キレと喉ごし」という時代が続く。しかし、1994年の酒税法改正を契機に、小規模ブルワリーにも醸造免許が降りるようになり、“地ビール”の時代が幕を開ける。さらに2010年頃からは、“クラフトビール”という新たな潮流も始まる。
消費量は減少しているのか? 現代におけるビールの立ち位置
1970年代から1990年代にかけて、日本のビール消費は右肩上がりだった。ピークは1994年で、1人あたりの年間消費量は75リットルを超えたという調査もある。
だが2000年代以降、ビールの消費量は減少の一途をたどる。2023年時点ではピーク時の半分以下にまで落ち込んでいる。
その要因は複数ある。ひとつは健康志向の高まり。若年層を中心に「糖質オフ」「アルコール控えめ」が重視され、そもそも“お酒を飲まない”という選択も一般的になってきた。もうひとつは多様化する選択肢だ。RTD(缶入りカクテル)や微アルコール飲料、さらにはノンアルビールの台頭によって、「ビール以外」が当たり前になりつつある。
また、Z世代・ミレニアル世代の間では、「酔うための飲酒」から「楽しむための飲酒」へと意識が変化している。苦味や炭酸が苦手という声もあり、クラフトビールや香り重視のビールが注目を集める背景となっている。
クラフトビールがもたらした新しい価値
1994年の酒税法改正により日本各地に「地ビール」ブームが到来し、小規模ブルワリーが続々と誕生。地域性・個性を前面に出したビールが次々と市場に登場しブームとなったが、品質のばらつきから一部で「まずい」との印象も定着し、次第に低迷した。
その後、2010年以降は米国発の「クラフトビール」文化が浸透し、個性や品質を重視したビールが注目され始める。現在では「クラフトビール」が主流となり、地ビールは観光用、クラフトビールは本格志向という位置づけで定着している。
2024年時点で、日本のクラフトビール市場は約1兆円規模。今後も年平均10%前後で成長が見込まれており、ビール産業における“希望の星”とされる存在だ。特に注目されているのが、地域密着型ブルワリーの動きである。地元食材を活用し、観光やふるさと納税と連携する事例も増えている。
クラフトビールは、これまでの「男性中心」「苦くて重い」ビールのイメージを覆した。フルーティーな香り、軽やかな口当たり、ユニークなパッケージデザインが、若者や女性層の支持を集めている。「ビールを飲まなかった人が、クラフトビールなら飲むようになった」という声も多い。
世界の中の日本 グローバル市場と日本ビールの位置づけ
世界で最もビールが飲まれている国は中国である。次いで米国、ブラジル、ロシア、ドイツなどが続く。消費量という点では日本は10位前後に位置しているが、輸出量や技術力という点で評価が高まっている。
近年は、アジアや北米を中心に日本のクラフトビールが輸出される機会が増え、ジャパニーズ・スタイルのIPAやラガーが高い評価を受けている。また、訪日外国人にとっても「現地のクラフトビールを飲む」ことが観光体験の一部となりつつある。
世界ではAI醸造、ヴィーガン対応ビール、環境配慮型パッケージなど、持続可能性と革新性を兼ね備えた動きが加速。日本のビール産業も、こうした潮流にどこまで対応できるかが問われる局面にあるといえる。
日本ビールの未来 持続可能性と「乾杯文化」の再構築
今、日本のビール業界が注目しているのは「サステナビリティ」である。各社は缶の軽量化、再生アルミ素材の使用、再生可能エネルギーの導入など、環境配慮型の生産体制へと移行を進めている。サントリーは2040年までに水使用量の35%削減を掲げ、アサヒは低アルコール飲料の販売比率を50%以上にする目標を立てている。
また、ビールの「飲まれ方」そのものも変化している。フードペアリングによる食体験の高度化、醸造所併設パブでのライブイベント、テイスティングツアーなど、体験型や物語性のある商品が求められるようになった。
そして、かつての「とりあえずビール」という文化は、今や問い直されている。乾杯の一杯に選ばれるのは、必ずしもラガーではない。IPA、ヴァイツェン、ペールエールなどのさまざまなスタイル、あるいはノンアルビールなど、多様な選択肢が“乾杯文化”をアップデートしつつあるのだ。
ビールは変化し続けている
日本のビール事情は、ただの飲酒傾向の変化にとどまらない。それは、時代ごとの価値観、産業構造、ライフスタイルの変容を映し出す鏡でもある。
今後のキーワードは「多様性」と「共感」、そして「物語」だろう。誰と、どこで、どんな一杯を選ぶのか。そのすべてがビールの価値になる。
ビール離れと呼ばれる現象の裏には、かつてなかった新しい飲み方、新しい作り手、新しい楽しみ方が広がっている。
これからの日本ビールは、飲まれるだけでなく、語られる存在になっていくはずだ。