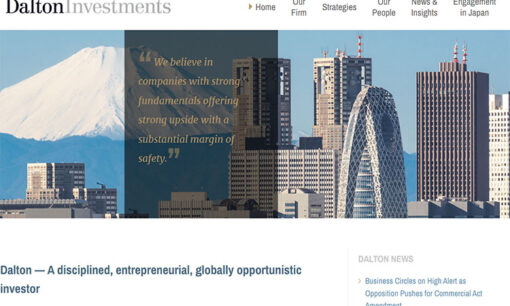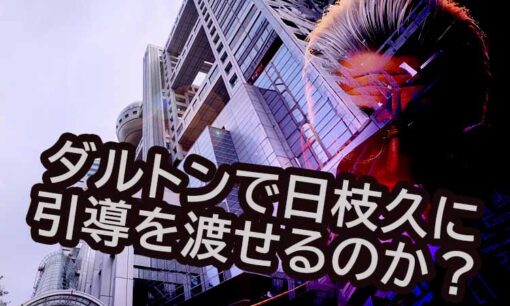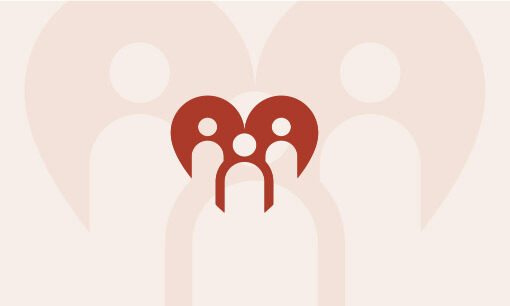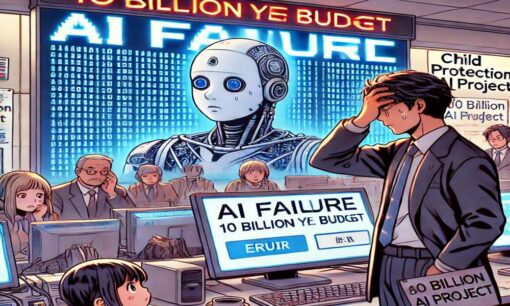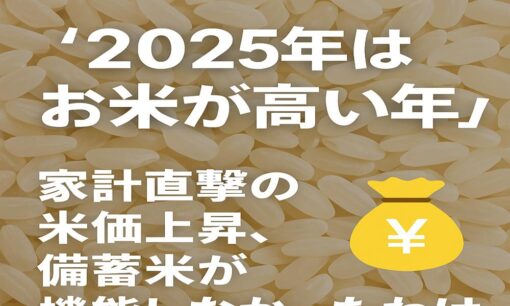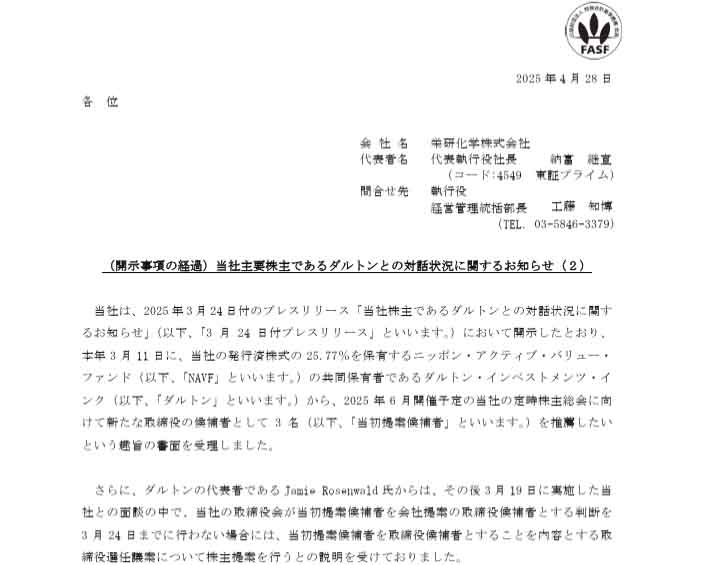
医療検査薬大手の栄研化学は4月28日、米アクティビストで筆頭株主のダルトン・インベストメンツから取締役6名の選任を求める株主提案権行使書を受領したと発表した。
ダルトンは共同保有分を含め発行済み株式の25.77%を握り、6月下旬の定時株主総会で取締役会の過半を奪取する構えを見せる。同社は「実質的な経営支配につながる」と警鐘を鳴らし、5月中旬に取締役会として公式見解を示す準備を進めている。
二年越しの対話が決裂へ至った道筋
2023年12月5日12月5日、ダルトンが5.09%の大量保有報告書を提出したところから始まった。当初は資本効率やROE向上をめぐる意見交換が中心で、対話は穏健だっ2024年11月8日11月8日、ダルトンは経営陣・従業員・主要取引先が株式の大半を保有し、残りを自ら握る「折り返し出資」型のMBO(経営陣が参加する買収)モデルを提示。ここで両者の温度差が表面化した。
2025年3月4日、栄研化学はそのモデルにキャッシュフローの二重計上や税務処理ミスがあると正式に指摘した。ダルトンは「たたき台にすぎない」と回答したが、3月11日には「取締役会の検討が遅い」と非難し、資本コストに詳しい取締役候補3名を月内に受け入れるよう迫った。守秘義務契約の合意と撤回が相次い3月24日24日に会社側は「現時点で候補者を会社提案に取り込む合意は困難」と通告し、対話は決裂した。
「毎期50億円上振れ」が突きつけた現実
栄研化学が4月28日に開示した資料によると、ダルトンの財務モデルはキャッシュフローを毎期およそ50億円過大計上していた。修正すれば借入返済計画が成り立たず、レバレッジを軸にした非公開化案は破綻しかねない。
会社は一般株主保護を理由に、株式売買を制限するスタンドスティル条項と、利益相反時にダルトン推薦取締役を議決から除外する条項を盛り込んだ協定書案を提示したが、ダルトンは回答を留保したままだ。
低PBRは「口実」か「課題」か
ダルトンは「株価が純資産に対して割安だ」と主張する。実際、栄研化学のPBRは2023年3月期末に1.18倍まで沈んだものの、足元では1.5~1.7倍前後へ回復している。会社側は「感染症検査薬など研究開発負担の大きい事業を抱え、短期的なキャッシュ還元より長期投資が不可欠」として、非公開化による高レバレッジには慎重だ。
フリーキャッシュフロー(FCF)は直近3期で7~8億円規模にとどまり、50億円を超えた年度はない。この実態とかけ離れた「50億円上振れ」モデルが提示されたことが、会社の不信感を決定づけた。
SNSで渦巻く怒りと嘲笑
投資家コミュニティには「近年FCFが50億円を超えた年はないのに、どうやってそんな計算違いを?」「モデルが崩れればダルトンの信用は地に落ちる」といった冷ややかな投稿が並ぶ。さらに辛辣なのは、分析担当者を「ジュニア」と揶揄する声だ。
「ジュニアの仕事、そのまま使ったんだな。奴らの仕事はマジでいい加減。ワイの脳内モデルで瞬時に出せる株価と比較して4割ズレ。2週間かけて作ったモデルを根拠に言うくせに、手取りが少ないってツイートするんだから勘弁してほしい。ジュニアちんでほちい。」
財務モデルの粗雑さが露呈したことで、ダルトン側の分析体制にまで疑念が飛び火している。
衝突が不可避となった三つの背景
第一に、東証改革が「PBR1倍割れ」企業へ資本効率改善を迫る中、キャッシュリッチな中堅製薬は海外ファンドにとって格好のターゲットといえる。第二に、コロナ特需の反動で検査薬需要が一服し、業績成長が鈍化したタイミングでMBOによるリレバレッジが描きやすくなった。第三に、医療インフラを担う企業には安定供給や規制対応といった長期責任が重く、守秘義務契約の翻意や期限付き圧力といったダルトンの強硬策が「協働型」から「敵対型」へ評価を一変させた。
総会まで残りわずか
栄研化学は5月中旬に取締役会として公式見解を示す予定だ。ダルトンが協定書に同意しなければ、会社側は反対推奨を貫く公算が大きい。財務モデルの再提出、候補者の適格性審査、そして一般株主の支持――三つの関門を突破しなければ、ダルトンが描く非公開化シナリオは実現しない。6月の株主総会は、日本型アクティビズムの成熟度を測る試金石となりそうだ。