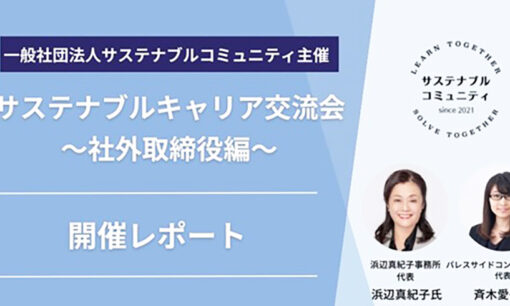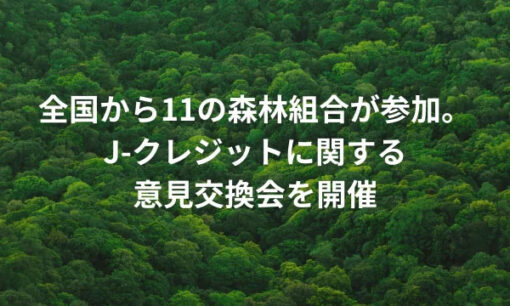「コーポレートガバナンスの旗振り役」として知られる伊藤邦雄氏が、今、厳しい批判の的になっている。現代ビジネスの報道によると、小林製薬に対し、香港のアクティビストファンドであるオアシス・マネジメントが指名する弁護士など3名を取締役として選任するよう求めているとのこと。
また、社外取締役の伊藤氏ら7人に、経営の不備によって小林製薬に与えた損害約110億円の賠償を求めて、小林製薬を提訴するよう求めているようだ。
伊藤氏は、かつて日本企業のガバナンス改革を主導した人物として高い評価を受けていたが、今回の紅麹問題を巡って、その役割と責任が厳しく問われている。
オアシス・マネジメントの主張
オアシスは、創業家支配が強い企業に対し、ガバナンスの強化を目的に株主提案を行ってきた実績があるファンド。もの言う株主として今回の小林製薬のケースも、創業家に対する監視体制が甘く、社外取締役が形骸化していると指摘している。
さらに、オアシスは伊藤邦雄氏を「伊藤レポートでは株主との対話の重要性を説いている一方で、オアシスとの面談を拒否している」と批判。伊藤氏が提唱する理想と実際の行動との間に乖離があることを指摘している形だ。
伊藤邦雄教授とは。日本のコーポレートガバナンスを変えた「伊藤レポート」
日本のコーポレートガバナンス改革は、伊藤邦雄氏なしには語れない。ただ、伝統的な日本型企業のオーナー経営者に話をきくと、伊藤氏の評価は「功罪相半ばする」ものが多い。なぜか。
コーポレートガバナンスが今日、日本企業に根付いたその功績は大きい。ただ、伊藤レポートの内容により、ROE(自己資本比率)8%が過剰に求められるようになり、従来の日本型経営の象徴であった「長期的視点を重視する経営スタイル」が揺らぎ、短期的な株主利益の最大化に重きを置く欧米型の企業運営が広がるきっかけとなったことを嘆く人が多いのだ(※)。
しかし、伊藤レポートは、その後も進化を遂げ、2017年には「伊藤レポート2.0」、2020年には「伊藤レポート3.0」とバージョンアップ。特に3.0では、「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」の概念が導入され、企業が短期的な利益追求に偏るのではなく、長期的な持続可能性を重視した経営への転換を求める内容となっている。
社外取締役選任の課題と情報開示の不十分さ
今日、伊藤氏は、「ミスター社外取締役」と言われる存在らしい。確かに、三菱商事、東京海上ホールディングス、住友化学、セブン&アイ・ホールディングス、東レなど、そうそうたる企業の社外取締役歴だ。
ただ、伊藤氏のように、制度に詳しく、また執行役をしっかり監督できそうな人材が社外取につくのであれば、まだいいが、日本の上場企業では、えてしてそういったことにはなっていない問題がある。
多くの会社で社外取締役として選任されるのは、学者、役人、運動選手、宇宙飛行士、アナウンサーなど、企業経営に全く携わっていない人物たちだ。本当に必要な取締役なのか疑問視されるケースも少なくない。株主訴訟などの際には、会社法第423条に基づき、取締役が「善管注意義務」に違反した場合には法的責任を負うこととなるため、アルバイト感覚で役職に就く社外取締役は排除されるべきだ。
実際に、有価証券報告書に記載される社外取締役の選任理由も、表面的な一口コメントにとどまり、具体的な情報が欠けているケースが散見する。株主はもっと詳細な情報開示を求め、選任理由が不透明な場合は、株主総会で選任に反対票を投じるべきと強く言いたい。
また、一般に社外取締役の任期は6年程度が適切と考える人が多い。会社法やコーポレートガバナンス・コードでは取締役の任期を原則2年と定め、長期間の在任が独立性を損なうリスクを回避するための規定が設けられている。この点、伊藤氏が小林製薬の社外取になったのは、2013年とのこと。いやはや、11年間もの長期間にわたって務めるというのはさすがに、なあなあの関係というか問題が発生しやすくならないか勘繰りたくなる。
小林製薬の開示方針の変化と伊藤氏の発言
この点を象徴するような伊藤氏のインタビューを見つけた。小林製薬は2022年度まで任意開示のデータブックである統合報告書を開示していた。紅麹問題が2024年3月に発覚したことを考えると、2023年度版は問題発覚したため開示を取りやめたのだろう。
さて、この2022年度の統合報告書には、伊藤氏の社外取締役としてのインタビューが掲載されているのだが、その内容が、主にパーパスなどの話であり、紅麹問題が起きたいま見てみると、もっと社外取締役として執行役をどうやって監督しているのかが聞きたいんだよと突っ込みたくなるシロモノであった。
株主が知りたいであろう経営体制の評価や執行役との情報格差をどのように埋めているのか、企業課題をどのように見ているのか企業価値向上に向けてどのような話し合いがされているのか、サクセッションプランなどの説明が足りていないことを感じる。
取締役会でのパーパス議論の詳細
ただ。読み物としては非常に面白かった。一例をあげると、小林製薬が掲げる「パーパス」についても詳しく語っていて、パーパスの策定にあたっては、取締役会で4回にわたり議論が行われ、最終的に「見過ごされがちな お困りごと」という独自の表現が採用されたと述べている。
パーパスの議論において、伊藤氏は「企業理念をベースに従業員との対話がしっかりできていれば、パーパスを掲げる必要はない」との意見を最初に提起した。しかし、執行側から「暗黙知だけでは一体感が出ない。従業員と経営陣が改めて立ち位置を確認するために言語化が必要だ」との意見が出され、最終的に伊藤氏もこれに賛同し、議論が深まったという。
この議論の過程は、同社の文化や経営理念を重視する姿勢を示しているが、株主や外部から見れば、取締役会が企業の長期的な価値向上に向けた具体的な戦略をどのように議論し、どのように実行に移しているのかといった情報が不足していると言える。
女性社外取締役の増加と課題
話がずれてしまった。戻そう。日本企業の社外取締役問題を見ると、筆者が個人的に最も問題と思っているのは、女性社外取締役就任ブームである。内閣府が東洋経済新報社の「役員四季報」に基づいて作成したデータによると、2023年7月時点でプライム市場上場企業の「取締役、監査役、執行役」に占める女性の割合は13.4%に過ぎない。問題の数字は、男性役員の60.4%が社内登用であるのに対し、女性役員の87.0%が社外役員であるという点だ。
もう一つ、日経が開示しているデータでも、女性取締役の数は急増しており、2024年7月時点で1002人に達したが、そのうち88.7%にあたる889人は社外取締役とのことだ。
特に、男女雇用機会均等法が施行された1986年から90年ごろに就職した「均等法第1世代」が、近年、多くの企業で取締役として起用されるようになっている。しかし、これらの女性取締役が実際にどれだけ企業の経営に関与しているのか、具体的な情報は少なく、単なる形式的な登用にとどまっているケースも少なくないだろう。