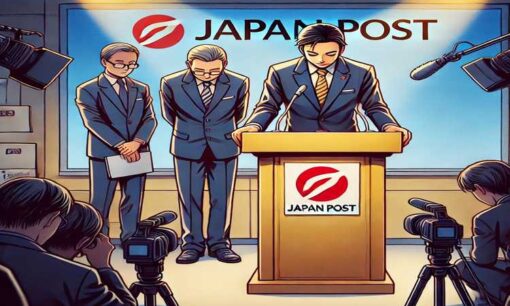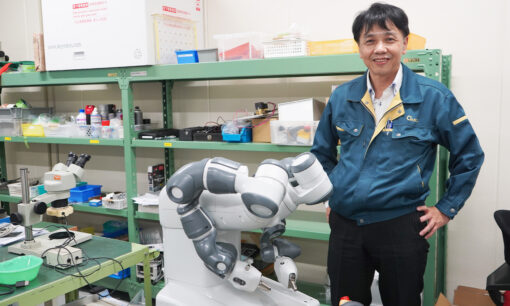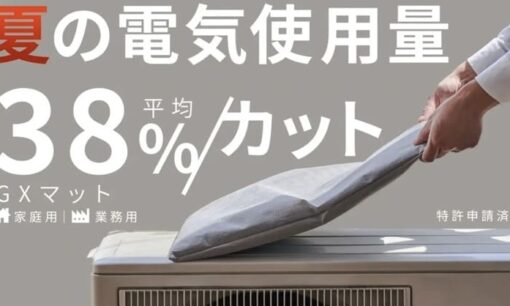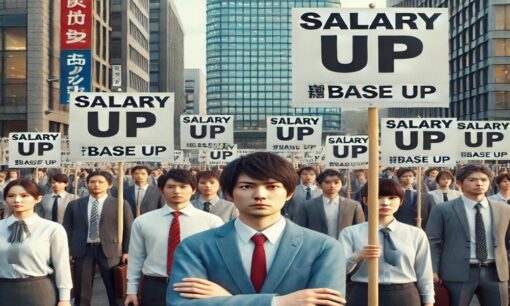販売認可を待たずに、顧客への勧誘が始まっていた。かんぽ生命と日本郵便による保険の不適切勧誘問題が、またも日本郵政グループのガバナンスの甘さを露呈させた。681件にのぼる違法行為、700人に迫る社員の関与、そして繰り返される社長処分。その実態と再発防止策に迫る。
認可前に681人を勧誘 社員700人弱が関与
かんぽ生命保険と日本郵便は2024年4月19日、保険業法に違反する認可前の保険勧誘が計681件にのぼったことを明らかにした。日本郵政グループ内での再発防止策の甘さが露呈した形だ。
同社の調査によると、勧誘された顧客681人の内訳は、2024年1月に発売された「一時払い終身保険」が199人、2023年4月に販売開始された学資保険が479人、その他の商品改定に関するものが3人であった。
認可前に顧客へ販売説明や提案を行うことは、保険業法違反にあたる。これらの不正行為には、かんぽ生命の社員400人超、日本郵便の社員250人超の合計700人弱が関与していた。
不正の端緒は、2024年3月にかんぽ生命が167件の事前勧誘を公表したことに始まる。金融庁の報告徴求命令を受けた同社が追加調査を実施した結果、さらに514件の勧誘行為が確認された。
組織ぐるみか?指示のあいまいさと「説明は可能」との通達
本件が深刻視されているのは、現場の判断だけでなく、本社側の指示や認識にも問題があったとされている点である。
かんぽ生命の能登一美執行役は、報道陣に対し「本社からの指示が曖昧で、法令違反になる可能性を伝えていなかった」と説明。新商品の届け出時に、現場には「一般的な範囲での説明は問題ない」との通達が出されていたという。
つまり、「認可を得る前に内容を説明しても構わない」と受け取れるメッセージが組織的に共有されていた可能性があり、結果的に違法行為が常態化していたともいえる。
社長ら11人が報酬減額処分 繰り返されるトップの処分
この事態を受け、日本郵便の千田哲也社長とかんぽ生命の谷垣邦夫社長は、それぞれ月額報酬の10%を2か月間減額する社内処分を発表した。さらに、副社長を含む両社の役員9人も同様に報酬減額の対象となった。
千田氏と谷垣氏は、2024年3月にも別件で処分を受けたばかりだ。ゆうちょ銀行が顧客情報を金融商品の営業に不正使用していた問題で、同様に報酬減額処分を受けていた。これにより、両社トップの不祥事による処分は今年に入って2回目となる。
日本郵政グループでは、2019年にも保険料の二重徴収や不利な契約への乗り換え勧誘などの不適切販売が社会問題化し、当時のグループ社長らが辞任している。今回もまた、トップの「処分」で幕引きを図ろうとする姿勢に対し、根本的な構造改革を求める声が高まっている。
ノルマや圧力の影は否定 だが再発防止策は十分か
なお、今回の不正勧誘については、厳しい販売ノルマや上司からのプレッシャーが直接的な原因であったという証拠は確認されなかったという。しかし、現場が「売らなければならない」という空気に支配されていた可能性は否定できない。
再発防止策として、両社は弁護士による法令研修の強化、新商品の内容を認可後に初めて販売現場へ伝える制度への改定、営業記録システムの改善を掲げている。
具体的には、認可申請段階での情報開示を廃止し、販売開始のタイミングでのみ説明が許可されるよう社内規定を見直す。また、営業活動の詳細を記録するシステムを導入することで、将来的なトラブルの証拠を明確に残せるようにするという。
ただし、これらの対策がどこまで現場に浸透するかは未知数であり、形式的な対応に終始する可能性も懸念される。
不祥事続く日本郵政グループ 揺らぐ信頼とガバナンス
今回の不正勧誘は、あくまで日本郵政グループの一部門であるかんぽ生命と日本郵便で発生した問題だが、グループ全体のガバナンスが問われる事態となっている。
ゆうちょ銀行では、顧客情報を無断で保険営業に利用していた件や、郵便局ではドライバーの飲酒チェックなど法定点呼業務の不備も明らかとなったばかりである。わずか数年のうちにこれほどまで多くの不祥事が重なれば、国民からの信頼は大きく揺らぐのは当然だ。
日本郵政グループは約20万人の社員と、日本中のあらゆる地域に拠点を構える巨大なインフラ企業である。その分、ひとたび信頼を損なえば、影響は社会全体に及ぶ。
今回の処分と再発防止策は、その第一歩にすぎない。真の意味でのガバナンス再建が果たされるかどうか、注視が必要だ。
消費者に求められる「見る目」 金融商品契約前にできること
最後に、一般消費者が不正勧誘から身を守るためにできることを考えておきたい。
保険や金融商品に関しては、販売担当者の説明を鵜呑みにするのではなく、「この商品はすでに販売認可を受けているか」「説明されている条件に違和感はないか」といった点を、慎重に確認する姿勢が必要である。また、不審に感じた場合は、消費生活センターや金融庁の相談窓口に早めに連絡することも重要だ。
企業側のモラルとガバナンスの向上は当然だが、消費者自身が正しい知識を持ち、主権者として契約の是非を判断する力もまた、再発防止の一助となる。
おわりに
不正が起きるたびに処分と謝罪を繰り返すだけでは、信頼は戻らない。かんぽ生命と日本郵便、そして日本郵政グループ全体に問われているのは、「今度こそ本気か」という問いである。一時的な制度変更ではなく、社員一人ひとりが法令を理解し、顧客と誠実に向き合える文化を築けるかどうか。その成否が、グループの未来を大きく左右することになるだろう。
【関連記事】