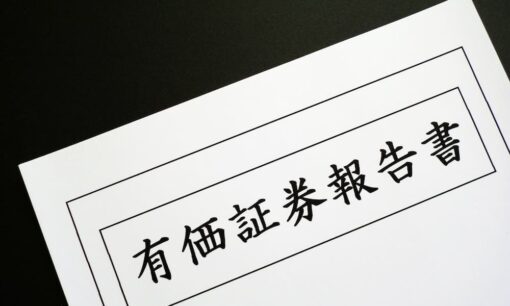半導体市場が急拡大する中、東京エレクトロンが宮城県に新たな製造装置の生産拠点を建設する。投資額は1040億円超。2025年6月の着工を予定し、2027年夏の完成を目指す。世界的な半導体競争が激化する中、日本の産業競争力はどう変わるのか。
1000億円超の大型投資、その狙いは?
東京エレクトロンは、子会社の東京エレクトロン宮城(宮城県大和町)に新たな半導体製造装置の生産棟を建設する。新棟は地上5階建て、延べ床面積は約8万8600平方メートルに及ぶ計画で、主力製品であるプラズマエッチング装置の生産能力を飛躍的に強化する狙いだ。
生産能力は2029年3月期に現在の1.8倍、将来的には3倍まで引き上げる見込みだ。また、新棟の完成により、雇用も拡大。2029年3月期には1100人、将来的には1400人規模の体制となる予定だ。
世界的な半導体競争が生んだ日本国内の投資拡大
半導体需要が加速度的に増加する背景には、生成AIや5G通信、電気自動車(EV)といった最先端技術の進化がある。これに伴い、高性能な半導体を生産する装置の需要も急増しており、東京エレクトロンの今回の大型投資につながった。
国内では、台湾積体電路製造(TSMC)が熊本県菊陽町で第二工場の建設を進めており、2027年末の稼働を計画している。こうした国内投資の拡大は、日本の半導体供給網の強化に大きく寄与すると期待される。
日本はかつて半導体大国だった——その変遷と再興のカギ
1980年代から1990年代初頭にかけて、日本の半導体産業は世界をリードしていた。NEC、東芝、日立製作所などの日本企業は、DRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)の分野で世界市場の約50%以上のシェアを誇っていた。しかし、1990年代以降、米国企業の技術革新や台湾、韓国の企業によるコスト競争力の向上などの影響を受け、日本のシェアは大きく低下した。特に、韓国のサムスン電子や台湾のTSMCの台頭により、日本企業は半導体の製造分野で後れを取ることになった。
現在、日本は半導体の製造ではなく、製造装置や材料供給といった分野で強みを持っている。東京エレクトロンは半導体製造装置の分野で世界トップクラスの企業であり、信越化学工業やSUMCOは半導体の基盤となるシリコンウエハーの供給で高いシェアを誇る。こうした分野での優位性を生かし、日本の半導体産業が再び世界で存在感を示すためには、技術革新の継続や生産効率の向上が求められる。
日本の半導体装置・材料分野の強みと課題
日本は半導体製造装置や材料供給の分野で世界的な競争力を持つ。半導体製造装置では米国に次ぐ31%の世界シェアを持ち、主要半導体部素材では世界トップの48%を占める。日本企業の強みとしては、精密技術に基づく高精度・高品質な製造装置の開発力があり、数十年にわたる業界経験に裏打ちされた信頼性が確立されている。また、グローバル顧客との強固な関係性や細やかなサポート体制を持ち、持続可能な製造プロセスへの取り組みも積極的に進めている。これらの要素により、日本企業は特にウェハー洗浄装置、コータ・デベロッパー、検査・測定装置などの分野で高い競争力を維持している。
しかしながら、半導体製造装置市場全体における日本企業のシェアは、欧米企業による積極的な統合と規模の経済の追求、新興国企業の台頭と価格競争の激化、最先端プロセス技術への大規模投資の遅れなどの要因により低下傾向にある。
日本の半導体産業は復活なるか?
東京エレクトロンの今回の投資は、日本の半導体産業の競争力を高める重要な一手となるだろう。しかし、真の復活には、技術開発の強化や生産効率の向上、環境負荷の低減といった多角的な取り組みが必要だ。
日本の半導体産業が再び世界で存在感を示せるかどうかは、今後の政策支援や企業の戦略次第である。引き続き、国内外の動向を注視する必要がある。