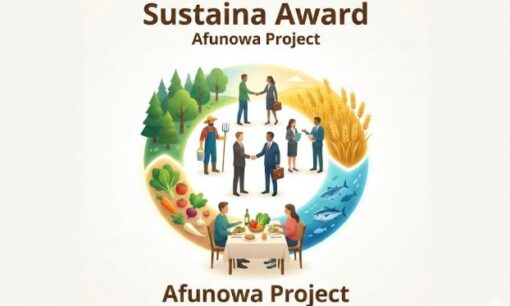三菱商事は2月6日、秋田県沖と千葉県銚子市沖の計3海域で進める洋上風力発電事業について、2024年4~12月期の連結決算(国際会計基準)で522億円の減損損失を計上したと発表した。世界的なインフレや円安の影響で資材コストが高騰し、事業の採算性が悪化したことが要因だ。
千葉県銚子市沖の事業は当初1月着工を予定していたが延期する。
洋上風力発電の採算性に影響 資材高騰で計画見直し
三菱商事は2021年、政府が公募した洋上風力発電の事業者選定で、1キロワット時あたり11.99~16.49円という低価格での売電計画を提示し落札。しかし、その後の資材価格の高騰により、当初計画の実現が困難となった。これを受け、三菱商事は事業の採算性を再評価する方針を示した。企業連合の一員である中部電力も179億円の減損損失を計上している。
6日の決算記者会見で中西勝也社長は「地政学リスクやインフレの影響が押し寄せ、ゼロから見直す必要がある」と説明。着工時期や運転開始の見通しについては「現時点では何とも言えない」と述べた。
地域経済への影響 漁業や自治体の懸念広がる
三菱商事の洋上風力発電事業は、地元自治体や住民にとっても大きな関心事となっている。千葉県の関係者は、「地域経済の活性化に寄与するプロジェクトとして期待していたが、延期は大きな影響を及ぼす」と懸念を示している。特に漁業関係者の間では、「海域の利用制限や生態系への影響を懸念していたが、突然の延期でホッとした」との声も上がっている。
一方で、自治体の担当者に話を聞くと、「事業の規模が大きいため、慎重に進めることが必要。三菱商事には地域と連携しながら計画を再構築してほしい」との切なる声も。
政府の支援策は有効か? 再生可能エネルギー政策の行方
こうした事態を受け、経済産業省は2025年度以降、資材価格の上昇分を売電価格に転嫁できる制度を導入する方針を示した。政府は2040年までに洋上風力で3000~4500万キロワットの発電能力を確保する計画を掲げており、支援策を強化する姿勢を明確にしている。
ただし、支援強化は電気料金の上昇につながる可能性もある。米ニューヨーク州では、開発コスト増加を反映した価格改定により、家庭の電気料金が2%以上上昇すると試算されたことが日経新聞で報じられた。英国でも入札条件を見直し、電力販売価格の上限を66%引き上げる措置を講じた。
日本の洋上風力発電は、遠浅の海が少ないことから「浮体式」が主流になるとみられるが、着床式の約2倍の建設コストがかかるとされる。今後、国民負担の理解を得ながら公的支援をどのように進めるかが焦点となる。
撤退か事業継続か 三菱商事の今後の選択肢
事業見直しを進める三菱商事は、今後の方針を慎重に検討することになる。採算性が厳しくなった場合、事業の撤退も選択肢の一つとして浮上する。もし撤退を決定すれば、政府は別の事業者への引き継ぎや公的支援の強化を迫られることになる。一方で、政府の支援策が強化され、売電価格の見直しが進めば、事業を継続する可能性も残されている。
また、国内外の企業との提携を強化し、資金調達や技術支援を受ける形で事業を続ける道も考えられる。海外では、共同出資やリスク分散のためのパートナーシップ戦略が広がっており、日本国内でも同様の手法が取り入れられる可能性がある。
SNSでは「失敗」の声も広がる
今回の三菱商事の減損計上に対し、SNS上では「洋上風力にしろ再エネは何もかも見せかけだけ」「秋田県内の事業は何をやっても続かない。ますます過疎が進む」などの厳しい意見が目立つ。採算を考慮せずに落札した三菱商事の入札価格についても「現実的な水準ではなかった」との指摘が上がっている。
三菱商事が受注した3海域のプロジェクトは、日本の洋上風力事業の象徴的な存在だった。今後の対応次第で、国内の洋上風力発電の未来が大きく左右されることになりそうだ。