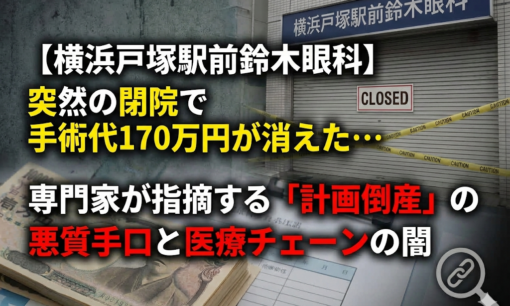難航する交渉、バクーの夜明けまで

アゼルバイジャンの首都バクーで開かれた国連気候変動会議(COP29)。途上国支援をめぐる交渉は、予定されていた会期を越え、24日の未明にようやく合意に至った。この合意は、途上国の脱炭素化や異常気象への被害対策を支援するため、先進国が2035年までに年3,000億ドル(約45兆円)を拠出するという新たな資金目標を掲げたものだ。
会場では熱気が漂う中、先進国と途上国の溝が最後まで埋まらなかった。特に、資金提供の仕組みや負担分担を巡る議論は難航し、「歴史の責任」を主張する途上国と「現実的な限界」を訴える先進国の対立は深刻だった。それでも夜を徹しての交渉は最後に妥結へと至り、長い議論の幕が閉じた。
新たな目標、そして課題
今回のCOP29では成果文書として、2035年までに先進国が年3,000億ドルを拠出することに加え、官民合わせて年間1.3兆ドル(約200兆円)の投資を呼びかけることも決定された。さらに、途上国にも自主的な拠出を奨励する文言が盛り込まれた。
しかし、この新たな枠組みが歓迎一色だったわけではない。途上国からは「拠出額が依然として不十分」という批判が相次ぎ、またNGOからは日本などの先進国が途上国支援の義務から逃れようとしているとの厳しい指摘も飛び交った。特に、途上国支援を義務付けられているはずの国が依然として化石燃料への資金提供を続けていることが批判の的となった。
日本の立場、そして未来
今回の会議では、日本も厳しい目が向けられる場面が目立った。気候行動ネットワーク(CAN)からは「特大化石賞」を贈られるという不名誉な事態にも直面した。資金拠出への消極的な態度や、化石燃料への投資継続が主な理由だ。
一方で、日本にとっても議論は他人事ではない。気候資金への巨額の拠出は、国内経済にも影響を及ぼし得る。それでも、地球環境の未来を考えたとき、国際社会の一員としての責任を果たす必要性は否定できない。今後、日本がどのように課題と向き合い、具体的な行動に移していくのかが問われている。
「1.5度」の目標に向けて
会場の熱気が冷めた後も、地球温暖化との戦いは続いていく。産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えるという目標は、依然として険しい道のりの先にある。延長戦の末に新たな道筋を示したCOP29は、果たしてその一歩を進める契機となるのか。それを決めるのは、これからの各国の行動に他ならない。