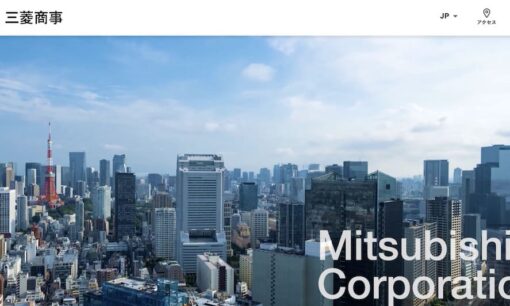日本の企業経営で長らく課題となっているガバナンスの最適化。社外取締役制度もようやく根付きつつある状況にあり、最近では、財務情報以外に様々な情報開示が求められるようになっている。しかし、まだ日本国内の経営体制の準備が十分に整っているとは言い難い。
このような状況をどのように分析し、そして、解決への処方箋は何であるのか? 日本におけるガバナンスの現状と先行きに強く警鐘を鳴らす一橋大学大学院 経営管理研究科 教授 円谷昭一氏にお話を伺った。
円谷昭一先生について
――はじめに先生の研究内容を紹介していただけますか。
私の専門は財務会計ということになりますけれども、学生には授業で簿記などを教えています。研究分野としては、最近はコーポレート・ガバナンスに興味があります。日本はまだガバナンス改革が始まって10年そこそこということで、その効果や、それによって生じているメリット・デメリットが定量的にはまだ示されていない段階です。
そうしたところで定量的なデータを出すということが社会的に必要だと思っています。それがないと、やはりどうしても理論や経験だけで議論がなされてしまうので、昔はこうだったとか、自分はこう思うというだけなので、そうしたところで効果や、また議論の中で見落とされている点などを、数値で浮き彫りにしていこうというのが、現在のテーマです。
具体的には、去年はこの株式の政策保有について集中して書きました。これまで、実証分析と、持ち合いがいいのか悪いのかというのは、データが実は示されていかなったのです。そういったものを去年はやりました。
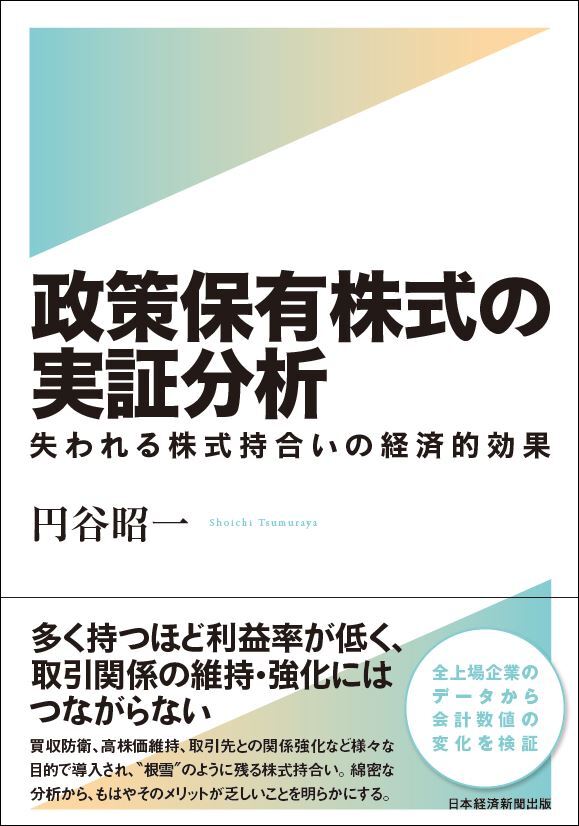
その前はこういった表紙の黄色い本(著書『コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」-大量データからみる真実-』同文舘出版)で、今年第2弾を出そうと思っているのですけれども。
今年のテーマとしては、社外取締役の報酬や、社外取締役が多いと本当に何か効果があるのかということを考えています。効果というのは、経済的な、ということですけれども、測定できる、定量化できる経済的な効果があるのかどうかです。そうしたものをやっていこうと思っています。
株式の持ち合いの功罪
――株式の持ち合いの功罪については、どのような方向性が見えてきたところなのでしょうか。
持ち合いに関しては、昔は効果があったと思っています。買収防衛策として効果がありました。簡単に言うと、私は「よろい」と言っているのですけれども、「よろい」の時代、戦国時代は、行動経済成長の時代では、敵の弓矢から守る「よろい」として効果がありました。
しかし、今、このDXの時代、弓矢ではなくて鉄砲になると、それはもう意味がなくて、逆に重しになってしまっています。昔は敵の弓矢、他社からの攻撃から身を守るという役割で経営の安定度につながっていたものが、今はむしろ経営の重しになって、しがらみになってしまっていると思っています。したがって、株式の持ち合いという行為自体が悪いというよりも、行為の経済的効果が時代とともに変わってきた中で、やはりまだそれにこだわっている会社が多いという課題があると思います。
以前の経営安定化ということへの成功体験、特に社歴の長い会社は、そういう体験を重視する考え方をまだ持っています。それが、日本企業がなかなか変われない一つの理由になっていると思っています。
――社外取締役の有効性については、いかがでしょうか。
社外取締役につきましては、マーケティングの世界でクリティカルマスというのですが、少数派が3割になると少数派ではなくなるという議論が、実証的にも理論的にもあります。今、日本の上場会社の取締役会のボードメンバーの平均が大体9人です。東証一部の社外取締役の平均が、去年やっと3人になりました。
したがって社外取締役の効果が出るのは去年・今年からだと思っています。それまでは、やはり社外取締役が1人、2人のときには、まだ少数派なので、その意見が通るわけでもなく、なかなか効果を発揮できませんでした。そういう意味では、社外取締役については3名になった去年あたりからがガバナンス元年だと、私は思っています。
ESGは日本に根付くのか?
――今ESG経営という言葉も最近見られるようになってきています。果たして今後、日本でもそういった経営方針は根付いていくのでしょうか。
根付くも何も、世界の流れにあらがうことができなくなってきていると思います。以前は日本も国力がありました。簡単に言うとGDPということですけれども、もはやそういうものがない中で、国力がない中で、日本独自のことを打ち出すという力が、発信力がなくなってきています。そうした1歩先、10歩先に、アメリカもヨーロッパも行こうとしています。
いわゆる脱炭素や、サスティナブルや、ガバナンスの中でのダイバーシティーの確保です。そういう状況の中で、「ダイバーシティーが要らない」「脱炭素が要らない」と言うのは難しいと思います。ましてや、あちらは欧米諸国は理論武装がうまいのです。彼らは世界標準を作っていくことがうまいので、そこに日本はノーと言える力がもはやないのです。
そのような中で、「日本はいいのだ。日本型でやっているからいいのです」と言っても、ROEや時価総額の結果が付いてきていないのです。そうすると、やはり見方としては「世界と違うガバナンスをして、システムをやっているから収益性も低いのではないですか」と言われたら反論ができないのです。
そうすると、監督庁もそのように変えていこうと当然思います。世界からそう思われるのは国益を損じるので、日本企業もできる限り世界に合わせていこうというような施策といいますか、制度といいますか、当然考えます。
日本がその評価を受け入れるかどうかという話とは別に、権威ある評価機関からは、既にガバナンスランキングということで、そのように評価されてしまっています。それは駄目でしょう。もっと力を入れて、「最先端のESG、ダイバーシティー、脱炭素、サスティナブルにしても、世界と合わせてやっているのですよ」ということを世界に発信していくべきです。
経営に今後根付いていくのかどうか、根付くかどうかというか、腹落ちして企業がやり始めるかどうかは別として、少なくともまず形を整えていかなければいけない時代だと思います。あるところで形が整ってくると、きちんとやらなければいけないという会社がどこかしら出てくるのです。社外取締役と一緒だと思います。
そういう意味では、外圧ではあるけれども、時間をかけて根付いていくと思っています。ただし時間はかかります。
――では、ガバナンスや社外取締役の重要性が叫ばれてから今年に至るまで、どのぐらい時間がたっていると考えたほうがよいのでしょうか。
社外取締役については10年だと思います。今まで「社外取締役なんて要らん」とずっと言っていた大会社があったのですが、ちょうど5~6年前に導入しました。日本を代表するような製造業が入れると広がります。産業界の世論を形成するキーパーソンというか、キーカンパニーの動きもまた必要になってくると思います。
例えばそうした日本を代表する製造業のような会社が、本当に脱炭素、ダイバーシティー、サスティナブルを本気で経営に位置付け、さらに情報開示も「率先してやります」という話になると、当然「横へ倣え」ではないですけれども他の多くの会社が同じような取り組みを始めると思います。
やはり日本を代表する製造業さんが右を向いたら、左を向いたらというところもあると思います。今事例に出した企業だけではありませんが、そうした日本を代表する企業とその系列会社が動き出すことになります。

同文舘出版
――なるほど。情報開示は、財務情報だとBS、PL、キャッシュフローシート等は定型化されているわけですが、ESGにしろ、社外取締役の効果にしろ、これらの新しい概念を評価するための指標については、今後、どのようになっていくのでしょうか。
まず評価するほうについては、ESG評価機関、これにはいろいろなところがありますけれども、まだどこがイニシアチブを取るのかという、混沌とした争いの最中です。ただし、もう後半戦です。
雨後の筍のようにいろいろなものが出てきて、それが合併を繰り返して、だいぶ集約してきたという感じだと思いますが、まだ幾つかの巨大団体があります。
去年の11月に、IIRCというヨーロッパの統合報告書の団体と、アメリカのSASBという統合報告書の引っ張っている団体が合併して、バリューレポーティングという新しい会社になるということを表明しました。やはり、そこは強いです。そこでM&Aをしてきて1つになると、ヨーロッパとアメリカが力を合わせて主導権を握ると、さすがにもうアジアは従わざるを得ないということになります。アジア以外の地域もそうです。そうしたところの主導権争いの最終局面が、評価する側はそろそろ始まっていると思います。
それが、まだ主要な団体として、国際会計基準側や力が強いところがあるので、そこら辺がどう収斂するかということは、この数年なのではないかと思います。そうしたら、もうそこには逆らえないでしょう。
ESGへの日本企業の対応
――例えば、日本を代表するような大企業の中では、既にこういった分野に対する取り組みが内々で進められているのですか。
もちろんそうした企業さんは、その辺はうまいです。しかし、上場会社は3,800社がありますけれども、世界の中でフロントランナーとして取り組んでいこうというのは100社程度だと思います。これらの会社さんは、当然優秀な人をそういった部署に配して、情報収集と、諸外国の動きのレポートを在外法人から上げさせています。ただし、実際には100社もいないでしょう。数十社というイメージです。
――これも先進的な企業で形にして消化されつつあるものが、どんどん川下に流れて、まさにクリティカルマスの3割ぐらいのところがやれたら、何となく他社も追従していくという流れになっていくということでしょうか。
そうですね。ですから、やはり日本を代表する製造業さんがやると、中小の3,000社は「そういう企業さんだからできるのであって、うちはできない」となるわけです。
ただし、業界2位、3位がやり始めると、それ以下も「うちらもやらなければ」という気持ちになってくるのです。ですから、「いや、それは日本を代表する製造業さんがやるからです。それは僕らに関係ないです」というところが、徐々にトリクルダウンではないですけれども、下に垂れてくるというか、そうすると一気にやるのですが、そこはどうしても経営資源もないので形式的な対応、作文で終わるというところが実際には多いとは思います。
――業界ごとに色合いはあるのですか。
あります。例えば、商社は日本にしかない業態です。ですので、商社のビジネスモデルがよく分からないと、世界の投資家から常に言われているわけです。となると、やはり世界の投資家へのアピールとして、ESGを軸に打ち出していたりします。また、いわゆる脱炭素系のところで、絶対にネガティブに見られる業種は当然力を入れます。医薬など、いわゆる本業がそのままESGにつながるようなところは力を入れています。
逆に言うと、そういうものがない業界だと、自分事だとは受け止めにくいでしょう。特に国内だけでやっている業界になると、多分「ESG? 現場の安全第一のことか」、「海洋プラスチック? うちの事業とは関係ない」という世界だと思います。「児童労働をさせているかどうか? させていないのに決まっているではないか」と、強い関心を持たないと思います。
ホームカントリーバイアスというか、やはり海外の投資家は、自国にない業種は分からないのです。それはそうです。日本人もそうだと思います。
――商社の人はコングロマリットであることをプラスだと思っているのですけれども、インベスターからするとコングロマリットであることでディスカウントされている側面があると。
そういうことの一つとして、共通の軸としてのESGを打ち出すということはありだと思います。
ところで、上場会社の情報開示項目に関する企業側の負担増という話について事前に質問をいただきましたが、実は私はあまりそのような影響は考えていません。というのも、GDP比でこれほど上場会社があるのは日本だけなのです。
これほど上場会社が、3,800社あるのは日本だけです。つまり、本来の資金調達の場として活用していないのです。いわゆるレピュテーションとかブランドというか、社会的な上場会社というものを求めて上場している会社が多いのです。本当に世界から資金調達をしたいというのであれば、こういう負担を、当然負担だと思わないわけです。開示を充実させて安く資金調達ができるのであれば、その負担に掛かる費用は当然ペイできるでしょう。
そうではない方が多いから、こういう声を発するのだと思います。特に何十年も増資などはやっていないけれども、上場のブランドは欲しいということで典型的なところは地方の金融機関さんです。地方の金融機関さんは上場不要な業種だと個人的には思っていますが、やはり地元の代表企業として上場していないということは許されないという状況になると、負担だという拒否反応が出てくるのです。
それをわれわれはよく聞くから、企業負担を配慮しなくてはというように心がそちらに行ってしまうのですけれども、僕は「それでは上場を廃止すればいいではないですか。全部免れますよ。情報開示も費用負担も心理的負担もずっと軽くなりますよ」と言います。しかし上場はしたいという話なのです。上場は維持したいけれども、開示の負担はしたくないのです。「それは違うのではないですか」というのが、私の意見です。
――上場の本来の目的を活用するためには、手段としてESGやガバナンス対応が必要ということですよね。
そうです。それで資金調達コストが減るわけですから、それは費用ではないはずなのです。少なくとも負担増ではないはずです。

コーポレート・ガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードの改訂
――話は変わりますが、ガバナンスコードとスチュワードシップ・コードの改訂について教えてください。
どのコードも定期的に改訂することになっており、次のガバナンス・コードの改訂は3年後ではないかと思います。スチュワードシップ・コードも3年ごとに改訂していて、去年改訂されたので、次の改訂は2年後です。このように改訂が進んでいるし、これからも進むのです。
――金融庁が日本版のスチュワードシップ・コードを制定して、改訂が続いているのですけれども、これは日本では受け入れられているのでしょうか。
機関投資家はだいぶ変わったと思います。議決権の個別行使結果を開示するようになりましたし、それこそ相当反対があったのですけれども、スチュワードシップ・コードに入れて強引に開示させました。一部の会社は、いわゆる外部向けの報告書もきちんとやるようになってきたので、僕は影響があったと思います。ただし、やはりこれをさらに推し進めるとなると、投資家の格付けなど機関投資家さんが強く反対するであろう重い案件、重い改訂項目を検討せざるをえません。
重いというのは、投資家側は強く反対するであろう案件です。ですから、ガバナンスコードで言うと、例えば女性取締役比率の義務化を2年以内にするとなると、企業側はかなり拒絶してくると思います。政府もそうです。議員の4割を女性にしなさいという法律になると、大ブーイングが起きると思います。スチュワードシップ・コードの残りの改訂項目も、そういう案件が増えてきています。
――先生の目からご覧になって、日本と世界の機関投資家の温度差はありますか。
よく言われることは、世界の投資家は自分のお金を運用しているので真剣です。日本の投資家はサラリーでやっているのです。月給でやっているから運用成績が上がろうが下がろうが関係ないのです。母体から系列があるので独立性がなく、どこかのグループの一員で、いわゆる出向者なのです。どこかにまた戻っていきます。腰掛けていると言うと失礼ですけれども、その二つだと思います。
そこに一生いるとなると勉強するし、頑張るし、そこに自己資金が入るとなると全然頑張る気持ちが違ってくると思います。そこが大きな違いとしてよく言われます。ですので、アメリカでは自分のお金を使って、まずは自分で出資者になって、独立性のある会社を作って、運用パフォーマンスが良ければそこに乗ってくる出資者がどんどん増えて、ファンドが大きくなっていきます。当然それには自分のお金が入っていますから、決して手を抜きません。
――日本の機関投資家のクオリティーが高まらないと、日本の市場性のクオリティーが上がらず、適切な会社が適切に投資を受けられないと。
おっしゃるとおりです。逆に言うと、不適切な会社が適切な投資を受けてしまいます。要らないところに回収されない資金が回り、要るところに回らないという、二つの不合理が当然背反の関係なのであるのです。これが根本的な課題の一つです。
――それは、今、国内もしくは世界の中で、解決しようという動きはあるのでしょうか。
それが二つのコードなのです。スチュワードシップ・コードで、投資家も汗をかきなさい。ガバナンスコードで、企業側もきちんとやりなさい、ということです。共に汗をかきなさいという考え方なのです、今から10年弱前、2015年頃にその二つが導入されたのは、まさにその問題意識なのです。
――なるほど。スチュワードシップ・コードの発祥自体はイギリスで、おそらく市場の環境などは日本と少し違うと思うのですけれども、それでもそこで求められているものが、結果的に日本においても有益だと認められてきたという理解でよいでしょうか。
そうですね。欧米での改革は30年間、続けられてきました。人間で言えば30歳なのです。成熟してくるわけです。いろいろと手直ししてきて、成果も出てくる。日本もそれを見習おうとしていますが、二つのコードを入れて10年もたっていませんから、人間で言うとやっと小学校の低学年です。それで30歳と同じことはできません。
そこをどう見るかだと思います。効果が出ていないから、二つのコードを入れたことに意味はなかったという方もいると思います。ただし、時間軸の話なので、効果があったかどうかを見るには時期尚早だと思います。
なぜ東京は世界の金融セクターになれないのか
――日本政府の中で、東京を世界の金融セクターにしようという動きがありました。なぜ日本はそうならないのか、なぜ日本はなれなかったのかという疑問は、今のような話に関係しているのでしょうか。
まず、世界から資金を得るには、日本の市場は、やはりフェアでないのです。
例えば日本を代表するような製造業に投資したい、あるいはそのグループ会社の超優良企業に友好的に「ぜひマジョリティーを持てるようにたくさん投資させてください」と言っても、「株式の持ち合いで全然買えません」となります。簡単に言うと、八百屋さんにリンゴが売っていて、おいしそうだから買おうと思って「リンゴを下さい」と言っても、「これは売り物ではありません」と言われるような感覚です。
それをどうするかというと、二つの方法があって、一つは持ち合いのように外部者を締め出すことを全廃して、「リンゴを買いたい」という人はお金さえ払えば買える状態にするか、「売り物でないのであれば、売り場に置かないで、倉庫の中に置いてください」と、つまり「上場を廃止してください。上場するのであれば、全投資家がフェアに投資できるようにしてください」ということです。
その中にはいろいろな人がいます。アクティビストもいるかもしれませんが、そういう人と対峙することが上場でしょう。
しかし、上場のメリットは欲しいけれども、アクティビストは排除したいわけです。そうしたことで、世界から見るとアンフェアな持ち合いのようなものが、今でも温存されているわけです。何十年前から、持ち合いは良くないとずっと言われても、今でも残っているわけです。それで海外からのお金は欲しいと言っても無理です。
情報開示も日本語だけです。それは無理です。もし世界から来てほしいのであれば、英語にしなければなりません。ツーリズムと一緒です。「来るのであれば、日本語を勉強してから来てください」というスタンスなのです。それは無理です。
それはなぜかというと、GDPは世界3位なので、国内で何とか生き残れてしまうからです。1億2,000万の人口のうちの何%かのシェアを取れば、倒産せずに食べていけます。この感覚は分かりますよね。危機感はないのです。そうなると、本気で有価証券報告書を全部英文開示するということは、誰も言い出さないわけです。
それで持ち合いもやめなければいけないとなると、「そこまでしなくても」となるのだと思います。
――しかし、長い目で見ると、世界の資金の流れから取り残される市場であり続けることは、日本にとっても日本の会社にとっても、マイナスではないかと思います。
おっしゃるとおりです。僕らの世代はその危機感があるのですけれども、今回のガバナンスコード改正の議論も「世代にもダイバーシティーを」ということで、われら世代、逃げ切れない世代も入れるということで、少しずつそういった汗をかく改革をやろうというように、内部で変化させるということです。
しかし、この改革には時間がかかります。その成果が出てくるまで、産業界のどのセクターも、対中国で耐えられるかどうかだと思います。
日本の理論で言うと、携帯電話の5Gも中国のほうが先を行っています。パソコンにしても、そもそも半導体が昔は世界の半分を日本で作っていたのが、もはや見る影もなくなっています。どんどん、どのように各セクターが弱ってきている中で、日本型のゆっくりした改革を続けていて耐えられるかどうかです。特に定年まで残り3年ともなる方々が意思決定をすることになれば、大なたを振るえるでしょうか。そうは思えません。
――ある意味面白い時代に生きていると思います。変えなければいけないものが明確にあって、かつやらなければいけないことも分かっている。いかにそれにアタックするかという状況なのですね。では、次の質問に移りたいのですが、今後、会社側のIR担当者がいわゆるマーケティング活動をもっと積極的に展開していく時代になると考えてよいでしょうか。
いわゆる投資家ターゲティングですね。機関投資家に何割持ってほしい、個人投資家に何%持ってほしい、機関投資家も国内と海外で何割ずつ、アクティブとパッシブで何割ずつというような、大ざっぱな株主構成を定めて、それに合うIRツールを用意する行動を投資家ターゲティングと呼びます。
例えばエーザイさんは、海外のアクティブ運用者を重視しているので、開示資料などもかなり専門的な化学式が書いてあります。海外のアクティブ運用者は、場合によってはドクターを持っている人たちが投資家をやっていますので、そういう人たちに向けた情報発信をしているのです。
一方、日本で「御社の投資家ターゲットはどうですか」と聞くと、多くの場合、あまり明確な回答が得られません。それはなぜかというと、やはりIR部門に異動になり、数年たってIRのことがよく分かってきて、投資家ターゲティングが重要だと思うと、他の部署に異動するわけです。ローテーションの一環なのです。
ですから、なかなか戦略が根付かないのです。エーザイさんは、CFOが何十年もIRを所管し、その中でIR戦略を立案しています。しかし、多くの会社では、その人材がIRのプロフェッショナルになってくる頃に異動することが多いです。
――そうした人事上のミクロな理由の影響が意外と大きいのですね。
そう思います。あとは社長によって、IRに力を入れる社長と、そうではない社長である場合があります。ずっと力を入れる社長がいても、後任社長が法定開示だけでいいとなると、今まで培っていた無形財産がIR部署の中で消えてしまいます。トップもIR意識の高い人を持続的に育成しないといけません。
現場のIR担当者も、当然ベテランが生涯担当をするわけではないのですけれども、うまくサクセッションプランを考えながら人繰りをしていかないといけません。場合によっては中途採用なども活用して、専門家を入れてくるということです。
ただし、そこまでやっている会社はあまりありません。それこそ先ほど申し上げた100社の中でも数十社というところだと思います。持ち合いによる安定株主がいるので、究極的には、そこまでIRを頑張らなくても、となってしまう面もあるのではないでしょうか。
――日本で持ち合いの構造を変えるにはどのようにすればよいのでしょうか。
持ち合いを崩すには強いガバナンスが必要になりますので、ニワトリと卵のような難しい話になってきます。ドイツはそれを強力にやめさせるために税法を変えて改革を実行しました。それを日本の政策当局ができるかといったら、現状ではなかなか難しいと思います。
一つの制度を変えるとしても、それに付随して上場基準や開示規則なども改訂が必要になるでしょう。金融庁さんや東証さんなどが強力なイニシアチブを握って、他の関連団体をすべて巻き込みながら推進する必要があります。すると、必ず周囲から反対意見が出てきます。そうした中で、政治主導で会社法、税法、金商法などを変えて、持ち合いを禁止させるメリットを見いだせるでしょうか。
このままでは先送りになってしまいかねません。今、取り組むべき喫緊の課題なのです。
20年後、30年後、今の形では資本市場もガバナンスも生き残ることはできません。よく分かっている人ほど、今やらないとまずい、という危機感は強いはずです。日本企業の現預金の保有残高、技術力、ブランド力などがあるうちにやらないと、それこそ武器なしで戦わざるを得なくなってしまいます。その頃にガバナンス改革といっても、誰も見向きもしないでしょう。
どこかで持ち合いをやめるとか、今、機関設計も、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社と3つあるのですけれども、そのようなことをやっているのは日本だけです。もちろん現状のままでよい、という意見もありますし、問題視する意見もあります。そろそろこれらを将来的に整理・統合をするのかしないのか、もしするとしたらどういう方向性でするのか、という議論を始めてもよいかと思いますが、誰もそれをやりたくありません。
それを誰かが「やろうよ。僕も汗をかくから、皆も汗をかいてよ」と言い出せる主体というか、強固な反対もいとわない強い意思、同じ志を持った仲間が集う場をうまく作っていくことが必要だと思います。
――本日はありがとうございました。

円谷 昭一(つむらや・しょういち)
一橋大学大学院 経営管理研究科 教授
2001年、一橋大学商学部卒業。2006年、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士(商学)。2011年より一橋大学経営管理研究科 准教授、2021年より現職。2019年、韓国外国語大学客員教員。専門は情報開示、コーポレート・ガバナンス。2007年より日本IR協議会客員研究員。日本経済会計学会理事、日本IR学会理事。2017年よりりそなアセットマネジメント「責任投資検証会議」委員。2020年より金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」委員。主著に『コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」大量データからみる真実』(同文舘出版、2017年12月)、『政策保有株式の実証分析』(日本経済新聞出版、2020年6月)など。
<関連記事>
CSRと利益追求のバランス|気候変動と健康リスクで増える企業の責任
慶應義塾大学SFC研究所 xSDGラボが提唱するSDGs実現への12の方策
日本市場とガバナンスの改革に向けて|一橋大学大学院 教授 円谷昭一|時は今、集え志のある者たちよ!
神戸大学大学院 鈴木竜太氏に聞く~職場の役割と組織における闘争の倫理
島田昌和先生に聞く~日本資本主義の父、渋沢栄一の実像とは?
企業は社会の公器。今こそ日本的経営に戻れ~日本電設工業株式会社 顧問 井上 健
100年経営研究機構 後藤俊夫「コロナ禍対応調査で判明した長寿企業の強さとは?」