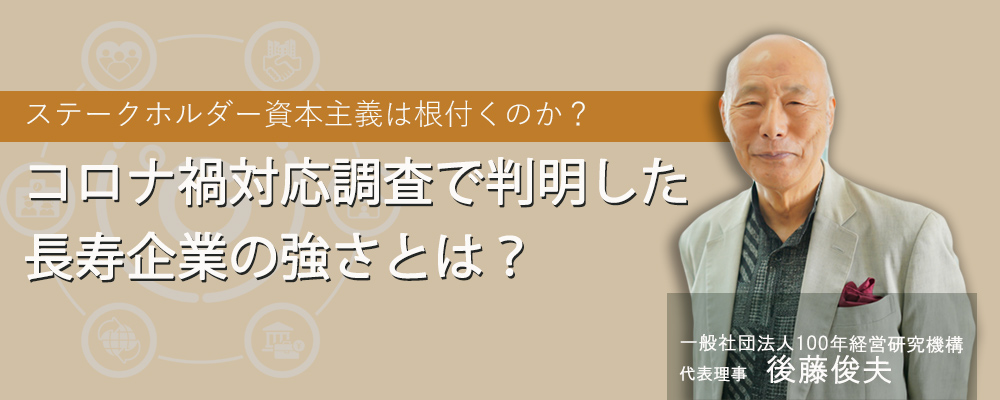
ステークホルダー資本主義は根付くのか?
一向に終息する気配のないコロナ禍。戦後最大の経済危機の影響は全産業セクターに及びつつあり、多くの企業が苦難に直面している。感染症との共生への覚悟が問われる、この時代を生き抜く経営とは何か。答えは「幾多の苦難を乗り越えてきた長寿企業にある」と100年経営研究機構の後藤俊夫代表理事は喝破する。
利他主義の実践者が長寿企業

―米ビジネス・ラウンドテーブルの「株主第一の反省」の声明やコロナ禍の影響により、株主重視だった従来の企業経営の在り方が、マルチ・ステークホルダー重視へと変わりつつある。この流れと並行して日本企業の経営者たちにも、従来の経営観を見直す声があるが、長寿企業研究の第一人者としてどう思うか。
フランスの哲学者ジャック・アタリは、これからは人々が助け合う利他主義の時代になっていくと明言している。人類が経済成長を優先し、企業各社も自社利益を過度に追及してきたからこそ、地球上の至る所で歪みが起きている。コロナ禍をきっかけに、こうした考えを改める機会になるのではないか。私自身も、次の時代は人々が共助の精神を発揮し、地球をもステークホルダーの対象と見る利他主義となっていくと見ている。
そして、それは顧客だけでなく、社員や地域社会といった社会全体のことを考え大切にする「三方よし」という言葉に代表される伝統的な日本式経営が見直されることに繋がるだろう。世界の100年を超える長寿企業のおよそ4割が日本に存在することは、日本の経営者が利他主義を実践し続けてきた結果なのだ。
歴史的に見ると、アメリカも伝統的にステークホルダー間でバランスのとれた経営を行う企業が多数を占めていた。それが1970年代のミルトン・フリードマン的思想やエージェンシー理論の台頭によって、株主第一主義に転換していった経緯がある。その波及効果が日本に及ぶにいたって、物言う株主、アクティビニストたちの声が強くなり、会計制度も含めて株主第一主義に舵を切っていった。今は行き過ぎた株主第一主義からステークホルダー資本主義へ移行するかどうかの端境期と見ることができる。恐らく米国大企業経営者が集うビジネス・ラウンドテーブルやダボス会議における議論の背景には、ステークホルダー資本主義を口先で終わらせてしまって良いのか、という問題意識があるだろう。
私は言葉だけで終わりではなく、実践せざるを得ないようになるだろうと思う。そして日本も同じく株主第一主義から脱却し、経営学の考え方も変わるだろうと期待している。その先頭にいるのがステークホルダー資本主義を体現している日本の長寿企業だと考えている。
―経営学者にはビジネス・ラウンドテーブルの声明はポーズであり、株主第一主義は容易に衰退しないだろうと見る向きもある。

株主はステークホルダーの一人でもある。ステークホルダー資本主義は株主を無視することではない。株主も含めたステークホルダーを総合的に見て、バランスを持った経営にあたることだ。決して株主を無視するとは言っていない。株主ばかりを重視する昨今の風潮に歯止めをかけようとするものだ。
コロナ禍を受けて流れは変わると思う。一昨年までは、マルチ・ステークホルダーを意識した日本的経営は過去の遺物だという人が経営学会にも多かった。事実、私が「企業は社会の公器であるという言葉や三方よしが大切なことだ」と言うと否定的な意見が多かった。一昨年の総会では、ある学者が、「社会の公器は今や死語になった」とまで言った。私は手を挙げて反論を述べた。社会の公器はすごく大切なことだと。その姿勢を100年以上貫いているのが日本の長寿企業だと。そうするとそれもそうだと一定数は賛同してくれたが、日本の経営学者たちの多くは、否定的に捉えた。なぜならば日本の経営学の主流は株主第一主義でこの10年を走ってきたからだ。
―ところがコロナ禍を受けて、変わると。
その通り。象徴的なのは、日本電産の永守重信さんの話だ。「人命を最優先に従業員の待遇を良くし、環境や社会課題の解決にお金を使っても高収益を上げる」と6月の株主総会後にも話している。
私は過度な自社利益の追求が否定され、SDGs、ESGが起こってきた背景を考えると、根付くと思う。今求められているのは、持続可能な経営である。その持続可能な経営の理想像が長寿企業であることを否定する人はまずいないだろう。では、長寿企業はどのような経営を行っているのか。それは地域社会をはじめ、ステークホルダーを大切にする経営だ。
緊急調査で見えてきた長寿企業の強みと海外への新たな展開
―そのエビデンスともとれる調査を今回、100年経営研究機構(以下機構)で実施したと聞いた。

4月に緊急事態宣言が出されたことを受け、飲食業や宿泊業を中心に大きな影響が発生することが予想された。そのため、これまでお世話になってきた創業100年を超える長寿企業の皆様に、機構としてお見舞いの連絡をさせていただいた。日々刻々と状況が悪化していた時期である。お返事を読むと、どの企業もコロナ禍に動じることなく、奮闘していることがわかった。こうした未曽有の危機を前にしても、果敢に立ち向かおうという姿勢が垣間見え、事業の継続にかけるエネルギーや知恵が溢れていたのだ。
やもすると一般企業よりも逞しいその姿に、これこそ長寿企業の長寿企業たる所以があるのではないかと考えた。そして、その長寿企業の粘り強く挑戦する姿を社会に広く伝えることが機構の責務だと再認識したのである。
こうした経緯で、長寿企業がコロナ禍とどう向き合っているかの情報を集めることを決めた。長寿企業ならではの強さや特長が浮き彫りにし、経済危機における長寿企業の対応のなかに長寿企業たる理由を見出すことができれば、同様に危機に直面する世界中の企業活動の指針にもなり得る。対外的に発信する価値が大いにあることだった。
―そこで5月に、「コロナショックへの長寿企業の対応に関する緊急調査」というアンケートを実施したということか。結果として、100件近い数の長寿企業の方が回答している。どういった傾向が見えてきたのか?
最終的には95社もの企業に協力いただけた。これほど多くの方に回答いただけるとは思わなかった。本当にありがたいことである。業種としては製造業40社、小売り18社、サービス業12社(旅館・ホテルを除く)で7割を占め、大半が年商10億円未満の中小企業だ。
調査結果から、1年以上事業継続のための資金を確保している企業が33.7%、2年以上が27.2%いることがわかった。約6割の企業が1年以上の資金繰りを確保しているという結果がでた。また、81.1%の企業が販売方法の変更を行い、生産方法の変更を行っている企業が35.6%いることもわかった。調査結果はドイツなど海外へも伝えた。海外の方は特に資金繰りの潤沢さが驚きだったようだ。
-我々日本人の感覚からすると、長寿企業が1年以上事業継続できる資金繰りを早期に確保していることはある種納得できるデータだ。それが海外では新鮮な情報となったのか?
そうだ。先日インターネットを介して約17万人の中国人に講演する機会があった。私が日本の長寿企業の資金繰りに関する状態について話をすると、非常に驚いていた。比較できる話として、中国のレストラン業界を対象にしたアンケートがある。そのアンケートでは資金繰りが3か月もたないという回答が過半を占めていた。日本の長寿企業では1年以上と回答した企業が6割を超えていることを考えると、改めて日本の長寿企業の強さが浮き彫りとなったと言える。
―要因をどう分析しているか?
日本の長寿企業の高い収益性と配当性向の低さが挙げられる。利益率が高いビジネスを長年続けており、しかもそれを配当として外に出さずに内部に留保し、再投資している。一方、中国など海外では利幅よりも売上規模を増やすことが優先される。また、事業で得た利益は配当に回し、経営層が豊かな生活をすることを良しとする彼らの価値観も、日本と異なる点として関係しているのではないかと思う。
―日本では株主還元よりは、社員教育やR&Dなど未来の投資に利益を分配する傾向がある。
その傾向は一般企業よりも長寿企業の方が顕著である。もう一つ、資金繰りを担保する要因として、長く経営を続けていることで培われたステークホルダーからの信用という点も挙げられる。
ある東北の旅館の話になるが、その旅館は2月の段階で先行きを憂い、銀行や信用金庫など3つの金融機関から億単位の資金を確保している。金額もさることながら、注目すべきはそのスピードだ。短期間に億単位のお金を集めるだけの信用が地域金融機関と旅館との間に、長い期間をかけて培われていたからこそ、資金調達が可能になったと推察できる。
ー長寿企業が地域社会をはじめとしたステークホルダーに多大な貢献をしてきたからこそ、「地元の名士」として信頼されていたと?
そうだ。地域を支える地元の名士という認知があるから、銀行も多額のお金を貸し出すのだろう。長寿企業は総じて、地域との結びつきも一般企業より深く、それがこのような危機に直面した際に、大きなネットワークとして機能しているものと考えられる。共存共栄を重視して地域との共生を重要視する経営にあたっていることが、こうした有事にも強い企業を作るのだろう。海外の方が驚かれる、6割という数字の背景はこうした理由によると考える。
この資金繰りの話や長期的な展望について驚かれてたドイツの方は、現在、アンケートを同じ文面で、ドイツでも実施しようという話をしてくれている。その他、香港やアメリカ、ポーランドなどでも実施を検討中である。
―日本だけでなく、ドイツやアメリカなどもこれから調査をするということは、国別の長寿企業の傾向が取得できるということか。
そのような展開を期待する。日本が先駆的な例として、見本になり得る未来が見え始めたので、各国間の調整が大変だが、国際的な規格でアンケートの文面を整えて実施できるように進めていきたい。
コロナ禍を受けて、大学などの研究機関もまた我々とは別に日本の中小企業を対象とした調査を実施している。ある調査ではサンプルが400弱集まっている。そのデータと今回の調査結果を比較することで、一般企業と長寿企業との違いも詳らかにすることができるだろう。様々な機関が連携しながら、比較を通じて、日本の長寿企業の特徴を明らかにしていく下地ができつつあるように感じている。
7年に1回の頻度で訪れる危機
―コロナ禍が長寿企業に与えたインパクトは?
経済危機の規模は戦後最大と言われるようになり、多くの産業セクターに影響が及んでいることは重く受け止める必要がある。しかしその反面、もう少し冷静に現状を俯瞰してみることも必要だ。実は、この100年間を見るだけでも、リーマンショックや東日本大震災、阪神淡路大震災やオイルショックといったディスラプション(大危機)、大危機があった。1945年の第二次世界大戦の敗戦ではGDPを8割以上も失っている。自然災害や政治経済的なものだけでなく、過去にはモータリゼーションやインターネット、パソコンの普及など、技術革新に基づく各産業セクターへの影響も大きかった。こういった技術工業的な変革は一晩にして起こるわけではないが、産業構造を劇的に変容させる力を確実に持っている。また、長寿企業の多くはファミリービジネスである。事業継承の機会も複数回あったはずだ。事業承継は家族内での対立・構想を惹起しかねないなど、失敗したらそこで潰れるリスクを孕んでいる。私が調べた中では事業継承は平均すると28年に1度の頻度で起きている。
この事業継続を阻む所与の条件はたくさんある。大別すると、政治経済的な危機、自然災害、各産業セクターで生じる技術変革及び規制など法的変化、事業承継に係る危機の4つに分類できる。これらを合計すると、この100年に未曽有の危機が15回あった。単純に100年を15で割ると7年に1回。誤解しないで頂きたいのは、コロナ禍の影響を軽視しているのではないことだ。ただ、誤解を恐れずに言えば、企業の存続を左右するような事業継続を阻む危機は、それ相応の頻度で定期的に起きているという事実に目を向ける必要があり、そこに立脚してはじめて持続的な経営とは何かの道が開けることだ。
それを如実に示す例として、緊急調査でも回答いただいた一社、くず餅の製造販売を行う船橋屋さんの話がある。船橋屋の7代目の先代社長が今回のコロナ禍について、「10年に1度はこのようなことが起きるものだから、皆で団結して知恵を出し合えば今回も必ず乗り越えられる。うちはこういった危機を乗り越えて230年続いてきたのだ」と社員に伝えたということだ。
そして先代社長が強調を出したのは、こういうときはとにかく皆で団結することだと。社員全員で団結して、知恵を出し合えば乗り越えらえるんだと、こう言ったそうだ。船橋屋さんは賃金カットもしなければ、社員の首を切ることもしていない。ただ団結と言うだけでなく、皆で一緒に勉強しようと。これはやはり長寿企業だから言えることだと思う。
先代社長は長寿企業を研究している人ではない。ただ、肌感覚で10年に1度は危機が訪れると感じているのである。「絶対に乗り越えられる」という言葉は今まで危機を克服してきたからこそ言える言葉だと思う。
長寿企業の実数は5万社に?
―機構の存在意義が、コロナ共生時代に再認識されるか?
機構が設立されて5年が経つ。当初より、長寿企業の英知を視覚化し、共有することを目的に私が作ったデータベースを更新するミッションがあった。このミッションが、コロナ共生時代にはより具体性・切実性をもち始めていることを感じている。短期間の調査にも関わらず、95社もの長寿企業から回答をいただけことが示すように、ここにきて機構を支えてくださる協力者のネットワークが醸成されつつある。このネットワークを活用することで、機構が、長寿企業の課題や悩みをサポートできる存在になっていくことも期待される。
―コロナ共生時代でシナリオが変わるのか?
今までやってきたことをよりスピード感をもって進めることだ。去年より、機構では東京商工リサーチと提携し、我々のデータベースと東京商工リサーチのデータベースとを突合し、国内の長寿企業の実数把握を進めている。突合するうちに、長寿企業の全容が徐々に明らかになってきた。二つのデータに重複している企業は相当数あるのだが、重複しない企業も少なくないことがわかってきた。正確な数字はまだ出せないが、日本全体で約5万社前後の長寿企業が存在する可能性があることがわかってきた。データベースの更新と長寿企業を創る長寿経営の英知に関するアーカイブの構築と運用は、機構の存在意義の根幹だ。同時に、今後は全国に長寿企業を中核にした様々なネットワークを作っていくことを、より具体的に且つスピード感をもって展開していく。ネットワークを拡充させていくことで、今よりもさらに濃密な情報を会員の皆様に提供できると考えている。
そして、機構が社会的責任を果たす手法については、個人や社会の価値観が大きく変容するとともに、技術的な革新も進んでいることを踏まえて進化させていかなければならない。コロナウイルスへの感染拡大防止の観点から6月の研究会はZoomで行ったが、大変好評だった。普段は参加できない遠方の方にもライブで情報を届けることができた。
コロナ禍によって機構の存在は、社会的要請の観点でますます重要となっている。世界的に長寿企業、なかでも日本の長寿企業に注目が集まっている今は時に利がある。時を逸しないように、機構の機能・組織も多様化させ、会員の皆様の期待に応えるようにしたい。

今はまだ大変な状況にあり油断はできないが、共助の精神の下、皆で知恵を出しあい結集すればコロナ禍は乗り越えられるはずだ。今の段階から、私たちはウィズコロナ、アフターコロナとは何かをきちんと考えていく必要がある。先ほども話した通り、株主第一主義からステークホルダー資本主義への移行の動きは、人々の幸せのために、それぞれが協力し合い、人間の経済成長をコントロールしながら地球を大切にしていくという、次の時代のスタンダード、一言で表現すれば利他主義の必要性が高まっていることの現れだ。そして、実践方法はそれぞれ多様だが、その利他主義を常に実践してきたのが長寿企業に他ならない。
今は明日の経営の姿を皆が悩んでいる。私はその答えが100年を超えて存続する長寿企業の中にあると考えている。「企業は社会の公器」然り、「三方よし」然り、自分のためではなく、利他を大切にする日本的な経営を続けてきたからこその長寿企業だ。
後藤俊夫(ごとう・としお)
一般社団法人100年経営研究機構 代表理事
日本経済大学大学院 特任教授
1942年生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後に日本電気株式会社 (NEC Corporation)に入社し、1974年ハーバード大学ビジネススクールにてMBAを取得。1999年静岡産業大学国際情報学部教授、2005年光産業創成大学院大学統合エンジニアリング分野教授を経て、2011年より日本経済大学渋谷キャンパス教授に就任。同経営学部長を経て、2016年4月から現職に就く。日本における長寿企業やファミリービジネス研究の第一人者であり、精力的に教育活動や講演・セミナーなどを行っている。















