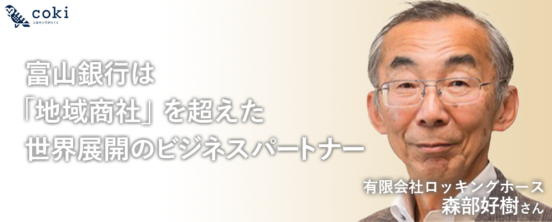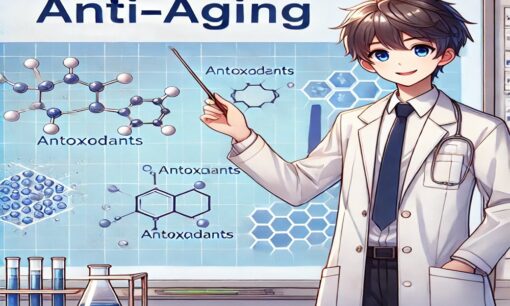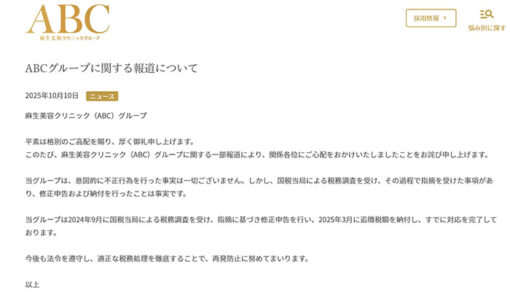SBI新生銀行が再上場を申請 旧長銀の公的資金返済で自由度回復へ

SBI新生銀行は7月11日、東京証券取引所に対して再上場の申請を行ったと発表した。かつての日本長期信用銀行(旧長銀)を前身に持つ同行は、バブル崩壊後に巨額の公的資金を受け入れて経営再建を進めてきたが、このたび残る公的資金約2,300億円の返済が完了し、ようやく「自立経営」への道筋が整った。
再上場による資金調達を通じて、親会社であるSBIホールディングスが掲げる「第4のメガバンク構想」において、同銀行が中核的な役割を果たすことが期待されている。関係者によれば、上場は早ければ2025年内にも実現する見通しだという。
今回の再上場は、SBIグループによる「地方銀行連携網」の構築戦略とも深く関わっている。公的資金の完済によって、これまで制約のあった経営の自由度が拡大し、提携銀行との共同商品開発や業務統合などの動きも加速するとみられる。
では、そもそも旧長銀とはどのような存在だったのか。
かつて「メガバンクより上」と言われた旧長銀の栄光と転落
SBI新生銀行の前身である日本長期信用銀行は、1952年に設立された国家管理型の特殊銀行である。当時の日本経済は高度経済成長の只中にあり、長期資金を必要とする産業界の要請を背景に、長銀は産業資本向け融資に特化した銀行として急成長を遂げた。
長銀は、信託銀行や都市銀行とは異なる「長期信用」という独自の業務領域を持ち、「長期信用三行」(長銀、興銀、日債銀)の一角として、日本のインフラ整備や重厚長大産業の成長を金融面で支えた。とりわけ、海外の機関投資家からの信任も厚く、米ドル建て債券の発行などにおいても強いプレゼンスを持っていた。
当時は、メガバンク(都市銀行)よりも信用力が高いと評価され、「国家の銀行」としての重みを持っていた。
しかし、バブル崩壊後、長銀はその特異な資金運用スタイルとリスク管理の甘さから巨額の不良債権を抱え込み、経営は急速に悪化。1998年には破綻し、国有化された。長銀はその後、2000年に外資系投資ファンド・リップルウッドの手に渡り、「新生銀行」として民営化された。旧長銀が国家の威信を背負った存在だっただけに、その破綻と外資への売却は当時の日本社会に大きな衝撃を与えた。
新たなステージへ 「第4のメガバンク構想」の中核に
現在のSBI新生銀行は、SBIグループの「第4のメガバンク構想」において、既存のメガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ)に次ぐ新たな金融エコシステムの要として期待されている。この構想は、地域銀行との資本・業務提携を通じて、全国規模の金融ネットワークを構築し、フィンテックとの融合で競争優位性を高めるというものである。
公的資金の完済と再上場によって、SBI新生銀行は長年背負ってきた「再建中の銀行」というイメージから脱却し、完全民間資本としての新たな歩みを進めることになる。
その歩みは、単なる上場の再実現という枠を超え、日本の地域金融と資本市場の再編という大きな文脈の中で注視されるべき動きである。