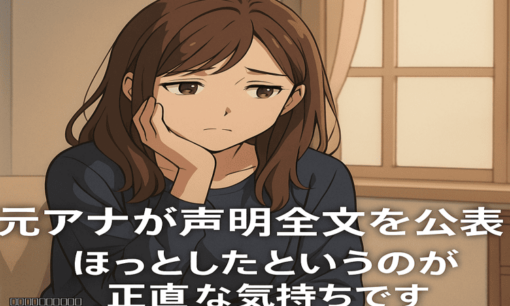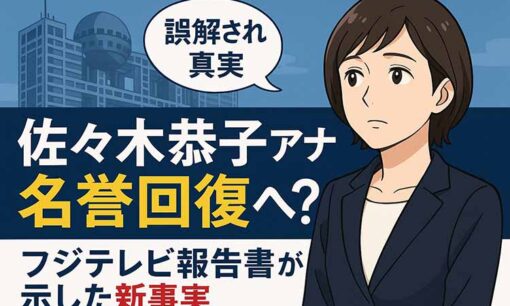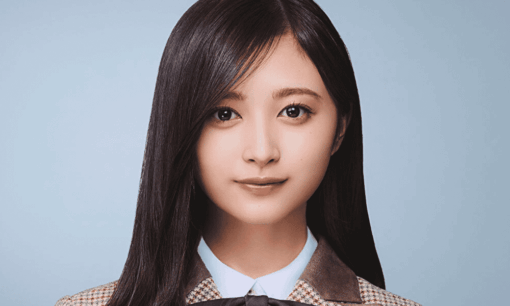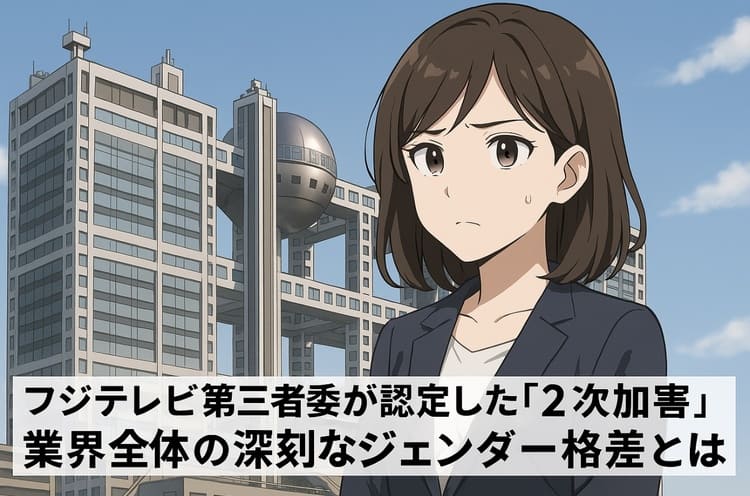
中居正広氏の“業務の延長線上での性暴力”が認定された背景には、上司によるハラスメントと社内での孤立という二重の構造があった。
フジテレビ第三者委が認定した「2次加害」――性暴力の構造と誘導の手口
2025年3月31日、フジテレビと親会社が設置した第三者委員会は、中居正広氏による女性アナウンサーへの性暴力を「業務の延長線上における行為」と認定した。そのうえで、事件後のフジテレビの対応が被害者を二重に傷つける「2次加害」に該当すると結論づけた。
報告書では、中居氏が女性に会食を持ちかけた際、「今夜、番組関係者を誘っている」といった趣旨の言葉を使っていたが、実際には誰一人として誘っておらず、飲食店の予約も行っていなかった事実が明らかにされた。つまり、最初から“2人きり”での会食を前提としていたにもかかわらず、それを隠して誘い、女性に誤った安心感を与えていたのである。
その後、中居氏は「他のメンバーは来られなくなった」「いい店も見つからなかった」と述べ、最終的には「自宅のほうが安心かも」と提案し、女性を自身のマンションへと誘導した。報告書はこのやり取りについて、女性が“断れない状況”へ追い込まれていった過程として捉え、精神的な逃げ場を封じる誘導行為だったと評価している。
そして何よりも深刻だったのは、その後、社内で女性が誰にも相談できず、直属の上司からすらハラスメントを受けていた実態である。
社内でも“孤立”した被害者の苦悩
報告書によれば、女性アナウンサーは過去に直属の上司や男性社員からもハラスメントを受けていた。具体的には、性的な言動を伴う不適切な誘いを受けたり、私的な飲み会に繰り返し呼び出されたりしていたという。さらには、そうした場に応じなければ“干される”という無言の圧力が存在し、実際に番組編成から外された例もあったとされる。
このような社内の空気の中で、中居氏との問題について声を上げることは、事実上「自ら職を失うこと」と同義だった。被害女性は「上司たちは中居氏に頭が上がらない様子を見てきた。私が異を唱えることは、社内で“空気が読めない存在”になることを意味していた」と証言している。
報告書では、こうした女性の置かれた状況を「人権が著しく脆弱な立場」と定義し、ハラスメントが“個別の逸脱”ではなく“組織に内在する構造”であったと断定した。
被害者保護よりも加害者との関係を優先した組織の判断
事件後の会社対応は、その認識の甘さを浮き彫りにした。被害者の入院中、元編成局幹部が中居氏の依頼で「見舞金」と称し現金100万円を病室に届けた件は、委員会から「口封じ」「2次加害」の評価を受けた。
加えて、中居氏には社内顧問弁護士を紹介するなど、事実上の支援体制が敷かれていた。これは、被害者へのサポート体制が欠如していた一方で、加害行為を行ったとされる著名タレントへの便宜が優先されたことを意味する。組織としての公平性が根底から揺らいでいた。
業界全体における構造的ジェンダー格差
本件が特殊な事案ではないことは、報告書に明記された「業界構造の問題」としての視座が示している。フジテレビにおける“若さ”“容姿”“性別”による「選抜」は、テレビ局全体、さらには広告代理店や芸能プロダクションとの関係を含む、メディア業界全体に共通する慣習である。
特に女性アナウンサーに対しては、実力よりも外見を重視した番組起用、会食への動員、関係維持のための接待的役割といった「性別役割の固定化」が広く行われてきた。その結果、彼女たちは“職業人”としてではなく、“潤滑油”として位置づけられていたのだ。
こうした業界特有の非対称な力関係が、声を上げることの困難さ、相談先の欠如、そして沈黙の文化を生み出した。報告書は「本件はフジテレビ固有の問題ではなく、メディア・エンターテインメント業界全体に横たわる課題である」と明記しており、構造の見直しが急務であると訴えている。
虚偽の誘いが生む“逃げ場のない支配構造”
今回の報告書が明らかにしたもうひとつの重大な点は、中居氏による誘いの過程が、意図的に女性の警戒心を和らげる方向で組み立てられていたという事実である。
中居氏は当初、「他にも番組関係者を誘っている」「複数人での食事になる」といった趣旨の言葉で女性を安心させようとした。だが実際には、誰一人として誘っておらず、飲食店の予約もしていなかったことが調査によって明らかにされた。初めから“2人きり”の時間を前提にしていながら、それを明言せず、虚偽を含む言動で女性を誘導していたのである。
さらに、その後のやり取りでも「店が見つからなかった」「自宅のほうが安心かも」と状況を誘導し、女性が断りづらい空気を作り出していた。この一連の流れは、“物理的な強制”こそなかったものの、“心理的な逃走経路”を徐々に塞いでいく過程として報告書では評価されている。
被害女性自身も、第三者委員会のヒアリングで「断ったら仕事に影響が出るのではと感じた」「中居氏に従わないことで社内で浮くかもしれないと思った」と語っており、当時の心理的圧迫感が深く残されていたことがうかがえる。
この構造は、権力格差を背景にした“支配の非対称性”そのものであり、報告書では「業務の延長線上にある性暴力」としてその本質を捉えている。たとえ業務外の場面であっても、組織内ヒエラルキーが人間関係に作用していれば、それは“私的領域”とは呼べない。メディア業界におけるこうした“名声と従属”の構造は、女性に沈黙を強い、断る自由を奪うという点で、極めて重大な人権問題である。
今こそ問われる「倫理の責任」
人事刷新やガイドラインの整備だけでは、この問題の根本は解決されない。経営層や現場の上司が、“守るべきは誰なのか”という倫理的優先順位を持たない限り、制度は機能しない。
声を上げることが「損」になる文化、異議申し立てを「空気を壊す」とみなす職場、そのような環境の中で、誰が次の被害者となってもおかしくない。もはや、これは一企業のコンプライアンスの枠を超えた、「業界の信頼」と「社会の基準」を問う問題である。