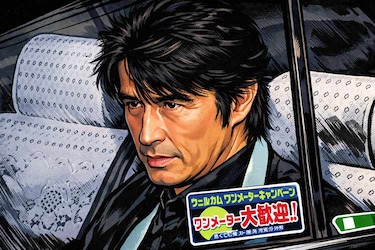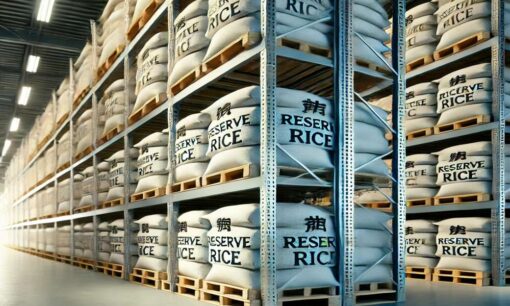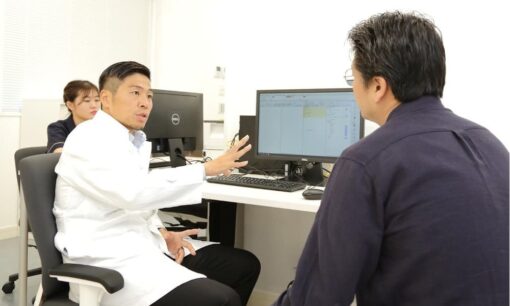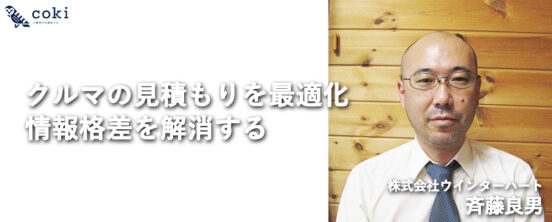ラジオ放送開始から100年の節目を迎えた2025年、かつて日本で最初に製作された鉱石ラジオが現代によみがえった。設計図も部品も失われた中、技術の記憶と先人の志をたどって元シャープ社員らが復刻に挑戦。過去のものづくりを再現する試みは、単なる懐古ではなく、受け継がれる技術と暮らしの知恵、そしてこれからの時代に問われる「本当に必要なものとは何か」を静かに問いかけている。
国産ラジオ草創期の一台、100年ぶりに蘇る
3月22日は「放送記念日」である。1925年のこの日、日本で初めてラジオ放送が始まった。放送開始からちょうど100年にあたる本年、そのわずか1か月後に製作された国産ラジオの草分けが、元シャープ社員らの手により復刻された。
復刻の対象となったのは、シャープ創業者・早川徳次が製作した鉱石ラジオである。1925年4月、早川はアメリカから輸入したラジオを分解し、技術者とともにその構造を研究したうえで、独自に鉱石ラジオの製作に成功した。大阪で放送が始まった同年6月には、自ら製作したラジオでその音声を聴取したという。
現在、この初期の鉱石ラジオは奈良県天理市にある「シャープミュージアム」に展示されている。経済産業省の「近代化産業遺産群」にも認定される貴重な資料であるが、一般には触れることができず、設計図や図面も残されていない。このような制約の中、シャープのOBで構成されるラジオ同好会が、約2か月をかけて復刻版を製作した。
記憶と資料でたどった「かたち」と「しくみ」
復刻作業では、当時の製作風景を撮影した写真や、早川の伝記、製品に刻印された文字などをもとに、サイズや構造を間接的に推定した。木製の筐体は、のこぎりとヤスリを用いて一つひとつ手作業で形を整えた。受信した電波から音を取り出す「検波器」部分の製作では、当時の部品の入手が難しいことから、形状の似た手芸用のネジなどを用いて代替した。
意匠面でも、早川の設計思想を読み取る手がかりがあった。一般的に鉱石ラジオは1人で聴く仕様が多いが、早川のモデルにはレシーバーを2つ接続できる構造が採用されていた。室内に自然に調和するよう意識されたデザインからは、単なる機械を超えた家庭の道具としての視点が感じ取れる。
「音が聞こえた」100年の時を越えて
3月19日、復刻ラジオの完成を記念するお披露目会が、シャープミュージアムで開かれた。参加したのは、小学生から90代の高齢者まで、約70人にのぼった。来場者は、復刻版のラジオから実際に流される現在の放送に耳を傾け、その音に静かに聴き入っていた。
会場にいた小学生は、「かすかですが、話している声が聞こえました。今と昔のラジオでは全然違うのに、音が聞こえるのはすごいなと思いました」と語った。92歳の男性は、「昔はレシーバーで聴いていたので懐かしい。再現には苦労されたと思いますが、よくできていて感心します」と感慨深げに話した。
復刻を主導した吉田育弘さん(66)は、「当時のラジオから流れる音を聴いてもらいたいという思いで作業を進めた。早川も使う人の笑顔を思い浮かべて作っていたように思う。当時の人がこのラジオをどう受け止めたかを想像することで、次の時代につながるはずだ」と語った。
昔の製品を復刻することの意味と広がり
こうした過去の製品の復刻は、ラジオに限らず、各分野で広がりを見せている。たとえば、ソニーは初代ウォークマンのデザインを再現したデジタルプレーヤーを2019年に限定発売。任天堂は「ゲーム&ウオッチ」や「ファミコン」など、1980年代の家庭用ゲーム機を復刻し、幅広い世代の支持を得ている。トヨタは初代ランドクルーザーを思わせるEVモデルを発表し、ノスタルジーと技術革新の両立を図った。
復刻には、過去への敬意だけでなく、ものづくりの精神や設計思想を次世代へと継承する意義がある。大量生産・大量消費の時代にあって、かつての製品が持っていた「手ざわり」や「佇まい」は、今日の暮らしにあらためて新鮮な問いを投げかけている。
とりわけ鉱石ラジオのように、電源不要で動作し、音を受信する仕組みそのものが目に見える装置は、子どもたちにとって科学や技術への入り口としても教育的意義がある。復刻とは、単に過去を再現する行為ではなく、未来の想像力を育てる種でもある。
現代の暮らしにおけるラジオの位置づけ
ラジオは、テレビやインターネットが台頭する中でも、「ながら聴き」ができる媒体として、生活に根ざした存在であり続けている。通勤・通学、家事や作業の合間に耳を傾ける聴取スタイルは、情報と日常を無理なく結びつけるメディアとして再評価されている。
また、災害時においては、停電や通信遮断時にも機能する数少ない情報源として、ラジオの重要性が改めて注目されている。地域密着型のコミュニティFM局も、防災や生活支援情報の発信において不可欠な存在である。
さらに、インターネットを通じた配信サービス「radiko(ラジコ)」の普及により、地域や時間の制約を超えた聴取が可能となった。音声コンテンツ文化の広がりとともに、ポッドキャストや音声配信アプリを利用する若者層の間でも、ラジオ的なスタイルの再発見が進んでいる。
早川徳次とシャープに受け継がれるもの
早川徳次は1912年に東京で金属加工業を創業し、社名の由来ともなった「シャープペンシル」を開発して事業を軌道に乗せた。1923年の関東大震災では家族を失い、事業も一度は閉鎖されたが、翌年に大阪で再起。ラジオ製作に乗り出したのは、情報伝達の重要性を痛感してのことだった。
1925年に鉱石ラジオの製作に成功し、外国製の半額以下で販売したことで爆発的に普及。後に真空管ラジオの開発にも成功し、日本のラジオ普及に大きく貢献した。復刻ラジオは、そうした早川のものづくり精神と社会的使命感を現代に伝える装置でもある。
音声メディアの原点から、これからの100年へ
日本ラジオ博物館の岡部匡伸館長は、今回の復刻について「製作時の苦労や社会の状況など、さまざまなことが理解できると思う。音声メディアが始まった当時の状況を通じて、その魅力やこれからの100年を考えるきっかけになるのではないか」と話している(NHKの報道による)。
100年前、ラジオは「声を届ける」という最も素朴で力強い手段として、人々の心をつないだ。音を聴くという行為に、どれほどの技術と想いが込められていたのか。復刻された鉱石ラジオの音が、現代を生きる私たちに静かに問いかけている。