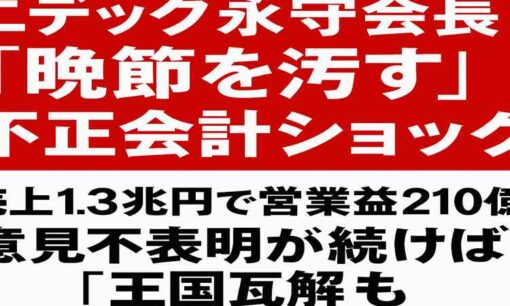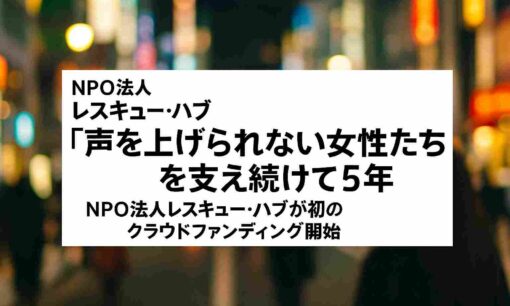触法行為を犯した犯罪者の社会復帰 社会はどう受け止めるべきか

1月6日に北海道放送が報じた「加害者の“その後”から矯正や社会での処遇を考える」の特集。1989年に起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件で、準主犯格だったB(51)が2022年7月、埼玉県のアパートで孤独死していたことが判明したことを報じる記事は現在SNSで反響を読んでいる。
Bは出所後、コンピューター関連の派遣の仕事に就くも、職場での被害妄想に苦しみ離職。その後再び罪を犯し、2度目の服役を経て、生活保護を受給しながら引きこもりの生活を送っていた。この報道は、犯罪者の更生支援のあり方について、私たちに重要な示唆を投げかけている。
北海道放送の記事「「女子高生コンクリ詰め殺人事件」準主犯格Bの孤独な最期 3年前51歳で自宅トイレで…加害者の“その後”から矯正や社会での処遇を考える」はこちらから
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1627718?display=1
家族との断絶が深める孤立
Bの更生を阻んだ最大の要因は、長期の服役による拘禁反応で生じた被害妄想だった。犯罪精神医学の専門家・小田晋氏は「職場でコンクリ詰め事件の噂をされたという被害妄想的な態度が矯正されないまま社会に出てしまった」と指摘する。実際、Bは出所後の職場で「同僚が事件のことを噂している」と思い込み、また自宅では「隠しカメラやマイクで監視されている」という妄想に苦しんでいた。これらの妄想は、2004年の再犯の遠因ともなった。
また、Bの更生をより困難にしたのが、家族関係の修復の失敗だった。幼少期に父親が家を出て以来、複雑な家族関係を抱えていたBは、出所後も両親との関係を修復できなかった。母親は「事件の話は一切しなかった」と語り、父親も「刑務所の話は絶対にしなかった」と証言している。
立命館大学の森久智江教授は「出所した後も基本的には家族が責任を全て持たなければいけないような状況になっている。少年事件の家庭の状況は、家庭自体が何かしらの困難を抱えていることが多い」と指摘している。
変わりゆく矯正教育の可能性
2025年6月から導入される「拘禁刑」は、これまでの懲役刑や禁固刑に代わる新しい刑罰制度だ。この制度では、フィンランド発祥のオープンダイアローグという精神医療の手法を取り入れ、チームを組んで一人ひとりの受刑者の再犯防止に取り組む。
森久教授は「オープンダイアローグは自分自身や自分の置かれている状況を鏡のように客観的に見る形になる。妄想で疑心暗鬼的になった自分の考え方を良い方向に向けられる可能性がある」と期待を寄せる。
社会からの厳しい視線、SNSでは
Bの死亡報道に対するSNSでの反応からは、事件から30年以上が経過してもなお、社会に深い傷跡を残している実態が浮かび上がる。
「80歳近くになる私の母が、この事件が発覚した時に本当に辛がって、いまだにずっと口にしている」「遺族でなくても私や母、そしてみんなの心に傷が残っている」といった声からは、この事件が与えた社会的影響の大きさが読み取れる。また、「日本の司法制度の甘さから、このような事件の再発を恐る人は多い」「未成年というだけで被害者とその家族の一生を壊してしまった」という指摘も目立つ。多くの人が少年犯罪に対する量刑や更生制度への不信感を表している。
また、「母子家庭すべて子供に影響があって、それが原因と簡単には言わないでほしい」という声もあり、家庭環境を安易に犯罪の要因とすることを看過できない人が多い。
犯罪者の更生の難路、更生とは?
日本において、犯罪を犯した者が社会復帰を果たす難しさは、しばしば語られるテーマだ。犯罪者とラベリングされれば、それを剥がすのは至難の業である。雇用、住居、交友関係など、社会のさまざまな場面で“過去”が影を落とし、更生の道を阻む要因となる。
何より、犯罪者自体が、自らの罪を悔い改め、更生しようと思う人が少ない現状がある。留置所や拘置所、刑務所などの空間では、神妙に反省した気になって生活を過ごすが、ひとたび娑婆に出れば、現実生活に翻弄され、罪のことを考える余裕はなくなるもの。数年も経てば、罪のことを思い浮かべることもほとんどなくなって日常生活を送っているか、あるいは塀のなかに舞い戻っているかだろう。被害者のやられ損というのは変わらない現実がある。
また、いまの刑務所や少年院などの矯正施設で自らの罪を反省し、社会復帰を自覚的に考えることはかなり難しい状態だと言える。独居生活ならいざしらず、雑居生活では過去に犯した犯罪手法の共有やいじめの横行など、とても矯正できる環境ではないと聞く。
更生は、本人の努力が不可欠であるのは確かだ。求められるのは、犯罪者自身が更生という言葉は他者が宛がう言葉であり、自らが口にできる言葉ではないことを自覚し、日々の生活を過ごすことだろう。
しかし、それだけでは十分ではない。社会が再犯防止に向けた支援の手を差し伸べなければ、再び罪を重ねるリスクが高まるのも、どうしようもないが現実である。過去を清算し、新たな一歩を踏み出そうとする者に対して、社会が扉を閉ざしてしまえば、その意志は容易に挫けてしまう。
社会復帰している人はどうやって?
一方で、社会復帰を果たし、懲役に戻ることなく、社会に交われた元受刑者の例も存在する。例えば、刑務所で書に出会い、出所後に書家として成功した人物もいる。あるいは、勉学に励み、弁護士、税理士、司法書士といった国家資格を取得し、法の専門家として活躍する者もいる。さらには、起業家としてビジネスの第一線で奮闘し、事業規模の大きな企業のオーナーとなった例もある。
これらの人物に共通しているのは、彼らが社会から支援を受けた経験を通じて、社会復帰の道を見出した点である。また、多くの場合が家族から見捨てられていない恵まれた人たちである。
犯罪を犯すことで、家族との縁が切れてしまったもので、社会復帰していける人もいるだろうが、その難度は本当に大変なものだろう。本人が二度と塀のなかに戻りたくないという強い意志のもと努力を重ね、その努力を見て応援してくれる人を獲得し、自らの社会復帰の足場を築いていかなければならないのだから。それでも、そういった人が少なからずいることも確かだ。
北海道放送の特集で、森久教授は、「オープンダイアローグ」の手法が更生に役立つ可能性を指摘している。この手法は、受刑者が自分の置かれた状況を客観的に見つめることで、妄想や被害妄想を和らげる効果が期待されている。2025年6月から導入される「拘禁刑」にもこの手法が取り入れられる予定であり、再犯防止に向けた矯正教育の新たな可能性を示している。期待したい。
ただ重要なのは、社会復帰後のサポートの在り方だ。疑似家族のように、手を差し伸べる存在が増えることでしか、懲役の社会復帰を円滑にすることはできないだろう。現状は、保護司などの善意に頼る構造であり、無償で奉仕している保護司に過度に負担がかかっている歪な状態であることを行政も認識しているのだから改めるべきだろう。
犯罪歴のあるものを受け入れる企業が増えていくことも重要だ。犯罪者の再雇用を支援する雑誌「Chance‼(チャンス)」や支援団体、活動家などの活動を多くの人に知ってもらいたい。

刑務所出所者の就職支援。社会復帰を阻む負のスパイラルを打ち壊せるか? 株式会社ヒューマン・コメディの挑戦はこちらから
https://www.biglife21.com/companies/15975/