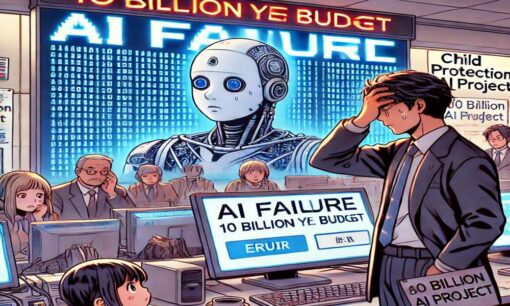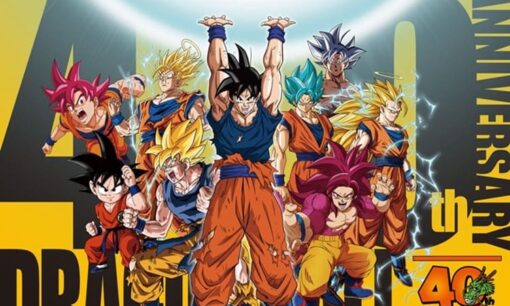「ソーシャルグッドな活動をしている誰か」を訪ね、その人との雑談を通じてその活動に込めた思いなどを紹介していく「#ソーシャルグッド雑談」。
第8弾は川地真史さんです。
「今日は来ていただいてありがとうございます。変わったお寺でしょ? こんなふうにフェスをやったりBARをやったりして。でも、おかげでおもしろいオトナたちが集まってくれるの。はい、お待たせ。コーヒーはいりましたよどうぞ。」むぬフェス パドマエデュケーションセンター
今回は、この「むぬフェス」の真ん中あたりにいる川地真史(かわちまさふみ)さんに、あちこちと動きながらぬるっと近づいてみたい。
■シーン1 | 産まみ(む)めも展@むぬフェス 今回、むぬフェスの一部として展示された「産まみ(む)めも展」は、産まない・産みたい・産む・産めない・産もうか……など、産むにまつわるあれやこれやを、さまざまなアプローチで揺さぶろうとするアーティストやデザイナーたちの軌跡を紹介している。公共とデザイン
写真中央: 川地 真史(かわち まさふみ)
一般社団法人Deep Care Lab
写真左: 八木橋 パチ(やぎはし ぱち)
バンド活動、海外生活、フリーターを経て36歳で初めて就職。2008年日本IBMに入社。現在は社内外で持続可能な未来の実現に取り組む組織や人たちとさまざまなコラボ活動を実践し、取材・発信している。脱炭素DX研究所 客員研究員。
写真右: 我有 才怜(がう さいれい)
2017年メンバーズ新卒入社。社会課題解決型マーケティングを推進するほか、気候変動への危機感や市民運動への興味から国際環境NGOでも活動中。メンバーズ「脱炭素DX研究所 」所長。IDEAS FOR GOODと共にWebメディア「Climate Creative
だが川地さんとの雑談を紹介する前に、むぬフェス会場でじっくり味わった「産まみ(む)めも展の2つの展示を紹介したい。碓井ゆい ハリコドモ
5羽のハリコドモ。左奥から時計回りにハシビロコウ、モリフクロウ、エミュー、ペンギン、ュウイチ。 ■ シーン2 | 川地真史さんにあれやこれやと訊いてみた
パチ
今日はむぬフェスのことも聞きたいんですけど、でもそれ以上に川地さんのことが知りたくって。ちょっと質問させてください。
川地さんは「公共とデザイン」の他に「Deep Care Lab」という団体の代表もされていますよね。おれから見ると川地さんたちの取り組みは、時間軸も社会の捉え方も、より広くケアしていくためのものに見えます。
なぜ、Wide(ワイド)ではなくDeep(ディープ)と名付けたんでしょうか?
川地
おもしろいですね…ノリかな(笑)。
まあ、改めてまじめに考えて答えると、僕らは「ケア」という言葉にまつわるイメージを変えたいと思っているんですけど、そこには水平的な次元よりも垂直的な次元の方が相応しかったというところがあるかなと思います。
面的な広さというよりも、深い次元の体験性を備えたケア、というイメージとでも言うか。 …そうか。でもおもしろいな。これまでワイドとディープで考えたことなかった。
パチ
じゃあ続いてもう1つ。川地さんはときどきプロフィール欄に「はたけとほとけ」的なことを書いてらっしゃいますよね。
畑づくりと仏づくり。なんだか今回のむぬフェスのテーマである「産むと死ぬ」が持つ循環性のようなものに少し似た要素を感じたんですけど、どうですか?
川地
プロフィールをすごくよく見ていただいているのがわかって嬉しいです。ありがとうございます。
そうですね。「はたけとほとけ」は両方とも数年前にスタートして、わりとハマっている趣味というかアクティビティーですね。
たしかに言われてみると、「畑づくりと仏づくり」と「産むと死ぬ」には関連するところがありますね。
そのどれも僕に「生」を強く実感させてくれるものではあるけれど、前者は手触り感を伴って日常の中でそれを感じさせてくれるもので、後者は意識的に感じようとしなければ目に入ってきづらくてつい見過ごしがちになってしまうものですね。
パチ
はたけもほとけも、わりと最近スタートされたんですね。我有さんも、畑がきっかけで川地さんと出会ったの?
我有
たしかに、畑関係の共通の知人が川地さんとつなげてくださいました。でも、私はもっと以前、たしかフィンランドにいらっしゃった頃にオンライン・イベントでお話を聞いたのが最初だったと思います。
その頃は「畑系の人」として川地さんを認知していなかったですけどね。畑はどんなきっかけでスタートされたんでしたっけ?
川地
フィンランドにデザイン研究の留学をしていた期間、自然の力に圧倒される時間や経験がたくさんあったんです。
巨大な森の中で静かに過ごす時間であるとか、「極夜」と呼ばれる圧倒的に短い日照時間の短い冬であるとか。
そういう「自然」が圧倒的な力を発揮する中でメンタルを保つためには、物理的な自然との触れ合い——たとえば土に触れたり光を浴びたりとか——そういうものが大切だって強く感じたんです。
フィンランド留学中に川地さんが現地で撮った写真
川地
それから、これはちょっと「それ大丈夫?」とか思われちゃいそうかなとも思いますけど、フィンランドで、自分たちで食べ物を自給自足しながら暮らしている人たちをエコビレッジに訪ねたんです。
その帰りに、昆虫を材料に作られたお菓子みたいな「インセクトバー」を食べたんですけど、そのとき、数千の虫たちが自分の身体を駆け巡る、鮮烈な感覚を覚えたんです。「なんだこれは一体?!」という経験で。
それで、日本に帰ってきた後、京都に移住して畑しごとを始めました。
我有
それって…すごい体験ですね! 私もデンマークで試しにコオロギチョコを食べましたけど、そこまでの感覚はなかったなあ…。
パチ
川地さんの舌の上から虫たちが喉を行進していく、なぜか楳図かずおタッチの絵が脳内に浮かびました。それでは仏づくりは?
川地
パチさんは「円空仏」って知っていますか?
なんかこちらも、「スピリチュアルなちょっと危ない人」って思われちゃいそうな話ではあるんですけど…。やっぱりみんな「人生を全うしたい」、「魂燃やして美しく生きたい」と思いますよね。
円空さんは僕の出身地の岐阜あたりではとてもよく知られている江戸時代の修行僧で、32歳から仏像を彫り始めた仏師でもあるんです。
そこから亡くなられるまでの30年間ちょっとで、12万体を超える仏像を彫られた狂気のお坊さんです。
我有
川地
でも、生涯をかけてそれだけ彫り続けたってことは、彫ることで自分自身も救われていたからなのかもしれませんね。
そして円空さんは、彫った仏にかんして「大切にしなさい」なんて言わないんです。子どもたちが川遊びで浮き輪がわりに使っていた、なんて話もあって。
それって、円空さんが上から偉そうに「救おう」というお坊さんじゃなくて、「民の救い」の実践者であり続けたということじゃないかなと思うんですよね。
ただ、円空さんの仏って、彫り始めたばかりの頃から上手いんですよ。それで僕もフィンランドから帰ってきてから、少し教室に通ったりしながら彫り始めました。
パチ
…川地さんにも、救われる経験が必要だったのでは?
だからこそフィンランドに行き、だからこそ帰国後「はたけとほとけ」をスタートしたのでは? ——これは失礼な質問かなって思うけど、なんだかそんな気がしました。
川地
僕は逃げたかったんです。日本から…日本のビジネス慣行から…自分が感動して飛び込んだデザイン業界から…逃げたかった。
僕は「美しくありたい。美しく生きたい」って、強く思っていたんです。そして人や社会の可能性を拡げるデザインの力に魅了されていました。
それなのに、いざデザイナーとして就職してウェブやアプリ制作の仕事を始めると、そこでの仕事は社会に存在しているものをそのまま縮小コピーして配るような仕事で…。
これってむしろ、人の可能性を縮めていることじゃないか。そして人を搾取しているだけじゃないかと感じていたんです。
でも、周囲のデザイナーの多くは「まあしょうがないよ。世の中そんなものだよ」って感じでした。
我有
美しく生きたくてデザイナーになったのに、そのままじゃ自分が汚染されてしまいそうだった——そういうことですね。
川地
そう。それで会社を辞めて、友だちのデザイン会社の仕事を手伝ったりしていたんですけど、あるとき、セクシャルマイノリティーの方のアプリを作る仕事をしました。5-6年前かな。
今よりもずっと、LGBTQについて語られる場面も少なかった頃です。
パチ
…LGBTQ当事者の自殺リスクは、シスジェンダーのそれと比べて数倍高い——さまざまな調査でそれが証明されていますもんね。
たしかに、言葉の使い方やデザインによっては、彼・彼女たちを死に追いやりかねません…。
川地
でもその仕事の一方には、自殺念慮から救う力や可能性もある。 デザインの力で、今よりも違うところに行けるかもしれないって、そういう希望を改めてデザインに求められるとも感じたんです。
そこからは仕事も勉強も頑張り、お金もどうにか貯めて、フィンランド・アールト大学のデザイン修士課程へと向かいました。
フィンランドの森の中で その後のコロナ禍におけるアールト大学での体験などの話も興味深かったのですがここでは割愛し、最後に、むぬフェス最終日前日に行われた即興演劇ワークショップ『産magination』について、ファシリテーターを務めた我有さんにその感想を聞いてみます。
■ シーン3 | 即興演劇ワークショップ『産magination』を振り返る 「産magination」は、不妊治療や出生前診断など「産む」や「育てる」で遭遇するシーンを、簡単な脚本に沿って演じていく「演劇ツールキット」を使ったワークショップ。
(写真は「公共とデザイン」のX(旧Twitter)投稿 より)
我有
脚本は10パターンくらいあるんです。今回は各グループその中から3つの台本を自分たちで選び、それぞれを2分くらいで演じ、5分くらいで振り返るという構成のワークショップでした。
私は全体ファシリテーターだったんですけど、グループワークにも参加しました。
参加者像は…そうですね。やっぱり「産む」ことを自分ごととして捉える時間を長く持たれてきた方もいれば、「演劇」のワークショップが気になったという人もいましたね。
パチ
当事者性が高くて繊細なテーマだけに、感情が相当昂りそうな気もするけど…そのあたりはどうだったの?
我有
役と演技への「入り込み度合い」は皆かなり高かったです。でも、泣き出してしまうような方はいませんでしたね。
事前に川地さんからワークショップのレクチャーと、簡単なリハーサルもしていただいていたんですけど、そのときに、「できるだけ自分とは異なる属性の役を演じてもらった方がいい」と助言をもらっていました。
その方が、自分でも思いがけない言葉や感情が出てきやすいからと。でも、どこか客観性を担保しておくという意味もあったのかもしれないですね。
パチ
他にも事前に川地さんからの助言的なものはあったの?
我有
参加者に「言われた言葉に動揺したりショックを受け過ぎないように」と、それから「ここは『言ってしまった』が許容される場だ」ということはしっかりと伝えて欲しいと言われました。
私もファシリテーターをやっていて、それがとても重要なアドバイスだったと思いました。
人って、傷つけられることはもちろんショックだけど、傷つけてしまったショックの方が大きいことも、少なからずあるじゃないですか。
パチ
我有
これは、出生前診断のスキットでの妻役の方が振り返りの場で言われていたんですが、夫役が「堕ろす」という言葉を躊躇なく使っていることがショックだったとコメントしていました。
その「言ってしまった3文字」に対し、なぜそういう感覚の違いが生まれるんだろうと、問いと対話が生まれていました。すごく興味深いプロセスで、演劇の力を借りることで生まれた対話だったと思います。
パチ
おそらくだけど、川地さんは「癒し」の様相を帯びさせたいとも思っているだろうし、誰だってそういう場が二次被害や二次加害につながって欲しくないよね。
それを分かっているからの「言ってしまったが許される場」ってアドバイスなんだろうな。
ところで、当事者性といえば、我有さんもかなり高い人だと思うんだけど、このワークショップのファシリテーターを引き受けたのは、それもあってなの?
我有
いや。それが違うんです。
むぬフェスに関われるならどの企画でもよいなという感じで、「川地さんともっとお近づきになれるんじゃないか」くらいの軽い理由でした(笑)。
ただ、当日を迎えるまでの間に、私自身、まさに「産まみ(む)めも」に考えを巡らせざるを得ない出来事があって、いろんな感情がうごめいていました。
そういえば、今回のワークショップでは、出生前診断や特別養子縁組などに関する 説明的な情報は、事前に与えることなく進めたんです。
すぐ脇の展示会場で、しっかりと 理解を深めてもらえるような導線設計にはしてあったものの、「役を演じきる」にはもう少し、説明的な要素もあってよかったのかも? という気もしています。
パチ
でも、情報が先にありすぎると、どうしても感情にブレーキをかけがちになってしまうから、事前に伝える必要はない気もするな。
とはいえ、一方で、これ以上ないほどの大切な決定を、その場の感情に重きを置きすぎるのもどうかと思うので、そのあたりは参加者の様子を見ながらかもね。
じゃあ最後に聞くけど、このワークにはどんな人にオススメする? 今後どんな場所で開催したらいいと思う?
我有
産むについてあんまり考えたことない、あるいは、考えるきっかけや視点がほしい人にまずは体験してほしいかな。
演劇の力を借りることで、その状況に対しても自分の思考や感情に対しても、解像度が増すと思うから。…場所っていうのは、どういう意味合いですか?
パチ
たとえば職場で同僚ととか、親戚一同でとか。あとは市役所とか病院でとか?
我有
うーん、どうでしょうね。
参加者アンケートを見ると、「初めまして同士だから演じられた」という声も多くて、あえて赤の他人のほうが自分の無意識を表出させるのには良いのかもしれないし、傷ついた / 傷つけた 場合の互いのケアもしやすいのかもしれないなと思いました。
…親戚一同は重た過ぎるかも。 でも、私は家に持ち帰って、パートナーと一緒にやってみたいって思っています。
パチ
あそびの精舎(しょうじゃ)