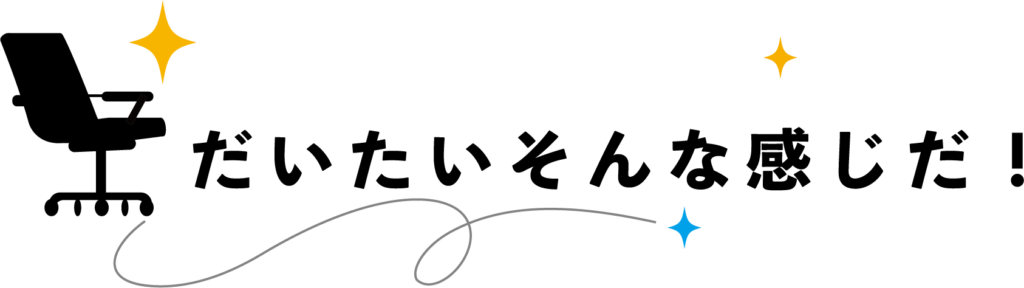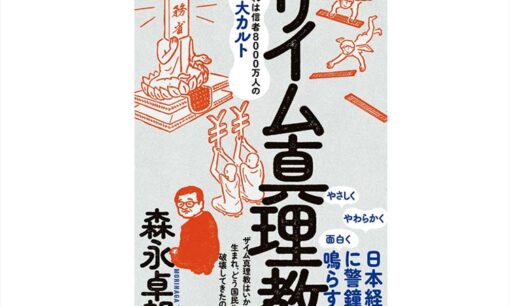いま日本の企業に必要なのは、「業界のアンミカさま」だ!
白は200色、黒は300色って当たり前?!
白は200色あるねん――。
その異色の経歴と年齢を感じさせない美貌からファッション誌やテレビ等のメディアで輝き続ける世界的モデル「アンミカ」さまの金言である。
「白は200色」は、別にアンミカさまのオリジナルではないらしい。もともとファッション業界では定説で、彼女が19歳で初めて挑戦したパリコレのオーディションで事務所から「帰って」と言われた時の言葉らしい。
何が悪いのか教えてほしい、とすがるアンミカさまに事務所スタッフが言った言葉が、「白は200色あるといわれているのに、なぜあなたは自分の肌をくすませる白を選んできたのか。もっと勉強してから再チャレンジしなさい」。
ちなみにファッション業界では黒は300色あると言われている。すべての色を混ぜ合わせると黒になるため、緑がかった黒、赤みがかった黒、瑠璃色がかった黒など、業界の人が見ればそのバリエーションは常人の想像を軽く超えるに違いない。
3色、2色でシズル感を出すスーパーのチラシ・テクニック
こう見えても(どう見えているかは知らないが)、ワタシも出版業界にちょっと関わっているので、色については一家言ある。アンミカさまの白200色の世界は知らないが、実は印刷業界にとって黒をしっかり出すのは難しく、単色の黒を刷るだけでなく、マットな黒などを重ね刷りをすることもあるし、黒に赤みを出したいなら赤すなわちマゼンダとイエローを加えたりする。
ご承知かどうかはわからないけど、通常のカラー印刷は主にオフセット印刷という方式が一般的で(ほかにグラビア印刷も知られているが、話せば長くなるので省く)、4つの原色、すなわちC=シアン(水色)、M=マゼンダ(ピンク)、Y=イエロー(黄色)にK=キープレート(黒[KだからKUROの略だと思いきやそうではない])の掛け合わせで表現されている。
最近のスーパーのチラシはこの4原色をフルに使って、ときには特色と言われる蛍光色なども使って集客しているが、地方によっては、Kを抜いた3原色でチラシを印刷することもある。1色分コストが浮くわけだ。
ワタシの若かりし頃は、そういった3色チラシは結構常識だった。
チェーン化されていない地場の2、3軒程度のスーパーでは、CとM、MとKなど2色の組み合わせでチラシを印刷するケースも多かった。
だがここに来てさまざまな原材料の高騰を受けたコスト削減やネットの進展によってチラシ事情も変わってきた。
先日は赤と黒の2色だけのスーパーのチラシが入ってきて、興奮した覚えがある。赤と黒だけで野菜や肉などを表現しているのだが、かなりシズル感のある色味となっていたのだ。赤が濃いと視覚的に補色となる緑を淡い黒が補っているのか、とくに野菜が緑っぽく見えたのには、勝手に感動した。
個人的には十分チラシの役割を果たしたと思うが、実際の集客はどうだったのか、足を運べなかったので、分からない。が、関わっているデザイナーはかなりの腕だと踏んだ。
江戸庶民はねずみ色100色、茶色48色を識別していた!?
白は200色、黒は300色はその道のプロだからこそ出てくる言葉に違いない。が、こういったセンスは意識すれば磨ける。
服装の奢侈が禁止された江戸時代には、庶民がその禁止令から色彩眼を磨いた。
江戸も寛政時代に入ると庶民の着物に絹などの高級素材を用いることが禁止されただけでなく、紫や紅、梅色などの明るい色を用いることも叶わなくなっていった。そこで彼ら彼女らが編み出したのが「粋」の文化だった。つまり灰色や茶色といった地味色にさまざまな段階と呼称をつけ、その違いを楽しんだのである。
その数は俗に「四十八茶百鼠」と言われるほどで、ねずみ色が100色、茶色が48色もあったとされる。アンミカさまの台詞の源流がここにあるように思えてくるほど豊かなバリエーションである。ねずみ色はとかくサラリーマンの代表色としてネガティブに語られるが、豊かな日本人の感性を表す代表色なのである。
雪を表す言葉、どれだけあるかご存じか?
ふだん見えている世界の構成をどう定義し、そこにどういう言葉を与えるかで、モノやコトの見え方は変わっていく。日本語はその言葉の数が優れて多い。モノやコトの状態だけを表すのみならず、そこに情感を込めた表現がデファクトとなっているからだ。
たとえば、雪。日本に住んでいる人なら雪を知らない人はまずいないだろうが、その雪の表現にどれほどのバリエーションがあるかを知り、使いこなしている人は少ないのではないだろうか?
試しに次の雪はどんな状態の雪か想像できるだろうか。
「餅雪」
「瑞雪」
「べた雪」
「水雪」
「衾雪」
「里雪」
「友待つ雪」
「薄雪」
「牡丹雪」
「微雪」
「吹雪」
「氷雪」
「玉雪」
「淡雪」
「暮雪」
「名残雪」
「涅槃雪」
「蠟雪」
「太平雪」
その雪が降るさまの表現も豊かだ。
「はらはら」
「霏霏」
「蕭蕭」
「こんこん」
「しんしん」
「綿綿」
雪そのものの名称も多様だ。雪の別称には次のような言葉がある。
「六花」
「銀花」
「雪花」
「風花」
「六出」
「雲雀殺し」
「三白」
「八日吹き」
「不香の花」
すべてイメージできただろうか?
日頃から俳句や詩歌に親しんでいる方なら簡単にイメージできるのかもしれないが、一般人なら「なんのこっちゃ」と頭をかしげる言葉も多いだろう。それでもこうした言葉からイメージを創出できることは単純に素晴らしく、それがある程度の共通概念や共感を持てるなら、なお素晴らしいと思う。
サイロエフェクト、タコツボ化に悩まされ続けた日本企業
世の中が進化し、とかく専門性が高まると、共通用語を見出すことがなかなか難しくなる。社会が専門性の高い高層ビルだらけとなり、見た目は華やかに輝いているものの、そこを横断する通路はなく、無駄な開発コストや無駄な折衝が繰り返されてしまい、気がつくと高層ビルの維持管理が難しくなり、廃墟となりかねない。
高度に専門化した組織の弊害を表す言葉に「サイロエフェクト」があるが、これは高度専門化が進むとサイロのように要塞化が進んで、中身の価値を周囲が分からず、似たようなプロジェクトや組織(サイロ)がたちあがって資源の無駄遣い、あるいは座礁資産となってしまうことを指摘したものだが、日本では1960年代から「タコツボ化」と表現し警鐘が鳴らされてきた。
で、これが解消されたかというと、サイロエフェクトなる書物やセクショナリズムといった言葉が繰り返されているのを見聞するに、もはや日本の宿痾であることは間違いない。
ワタシは教育業界やものづくり業界、サービス業界で取材することが多いが、そこにはそれぞれアンミカさまのようなプロフェッショナリズムを持った方がいることに、いつも敬服している。ただ惜しむらくは、その用語がサイロ、あるいはタコツボのなかでぐるぐる回って進化してどんどん熟成するので、外の人々からどんどん離れてしまうことだ。
いまはSNSなどでさまざまな価値観の人が繋がり、交流できるようになっているが、果たしてサイロはむしろ分厚くなってしまっている気がする。予てよりリアルな異業種交流会も広がっているが、果たして必要な出会いが必要な形で行われているか、ワタシはちょっと不安になっている。
ていうか、結構交流は既にやりつくしているのではないか。
むしろ、「白は何色か」と普段の当たり前を、その場で定義しなおすことが大事なような気がする。
品質って言っても、いろいろあるねん!
たとえば、ものづくりの世界では「Q=Quality (品質)、C=Cost(コスト)、D=Delivery(納期)」が肝要であると言われてきた。最近ではこれに「E=Environment(環境)が加わっている。いずれを優先するかは、企業の方針次第だが、長年日本企業が先頭においてきたのがQ(品質)である。ここを最優先で磨いてきたから、Made in Japanは世界の信頼を得るまでになった。
では日本のものづくり企業は品質をどう磨いてきたのか。
実は日本のものづくりでは“品質のアンミカさま”がいて、「品質って言ってもいろいろあるねん」と品質を多方面から分析して定義しているのだ。
一般的な品質は、製品の企画、設計、製造、使用の段階ごとに分けて、あるいは顧客から視点に分けて次のような種類がある。
1)製品品質
2)出来栄え品質
3)適合品質
4)狙いの品質
5)設計品質
6)供給品質
7)市場品質
8)企画品質
9)社会品質
10)魅力的品質
11)一元品質
12)当たり前品質
13)無関心品質
14)逆評価品質
個別の解説は専門書に譲るが、「ウチの製品は品質がいいんです」「当社のサービスは質がいいんです」という時、その品質とは誰に対してのどんな品質なのか、しっかり説明できるだろうか。そしてその品質は顧客や市場が求めるものなのか。必要なものなのか。はたまた、抜け落ちてしまっていないだろうか。
サイロやたこつぼのなかにはたくさんの優れた目利きがいて、芳しいまでの優れた技術やスキル、ノウハウがある。そのなかをちょっと知るだけで、新たな市場や技術革新が生まれてくるはず。
いま、日本の企業に必要なのは、他社や他業界の当たり前を、自社や自業界にさらりと説明できる“業界のアンミカさま”なのかもしれない。
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ。