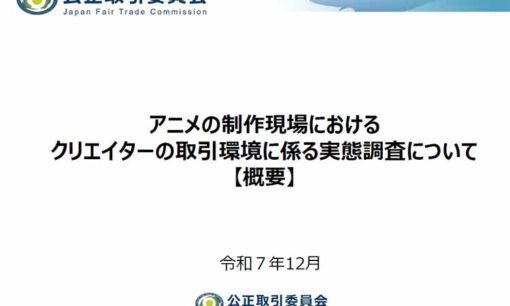大中忠夫(おおなか・ただお)
株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス代表取締役 (2004~)
CoachSource LLP Executive Coach (2004~)
三菱商事株式会社 (1975-91)、GE メディカルシステムズ (1991-94)、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタントLLPディレクター (1994-2001)、ヒューイットアソシエイツLLP日本法人代表取締役 (2001-03)、名古屋商科大学大学院教授 (2009-21)
最新著書:『持続進化経営力測定法』2022
日本経済半世紀の外部観察者の立場から
90年代のバブル破裂を境とした日本経済の半世紀にわたる栄枯盛衰。その破裂以前の20年間の高度成長と破裂後の30年間の長期低迷の日本社会の有様を、筆者は商社マン、海外駐在員、外資系経営コンサルタント、社会人経営大学院教員および研究者といった、いわば日本社会経済の外周部生活者の立場から観察分析する機会を与えられてきました。
企業内部での成功を目指した人々はその社内体験の延長線上に未来を描きます。一方、外部の人々、大部分の政治家や学者は会社経験がありません。そのため経済の絶対基盤である会社の実態を知らないままに経済成長を論じます。
これらのいずれのグループにも拘束されず、会社内部とその外部である社会経済全体、の両方を客観的に観察できた経験は、日本社会と経済の未来についても、その実現のための本質課題についても、忌憚遠慮無く提言することを可能にしてくれているようです。
また、それがこれまでの私のキャリアゲームに出演してくださったすべての人々への恩返しとも思います。そこでいま、過去半世紀の日本経済と会社の観察知見に基づいて、「新しい資本主義の実現条件」-日本経済は生き残れるか?という大命題を議論させていただきたいと思います。
日本経済の現実 | 日本企業の株価は上昇しても賃金は20年以上停滞している。
日本社会では、政府と中央銀行の積極的な金融緩和策により、株価は大きく上昇しましたが、一方で賃金は20年以上にわたり低迷したままで、その間に所得格差も貧困世帯数も拡大するばかりです。これが、2022年7月現在の日本経済の現実です。
ではなぜそのような状況が20年以上も続いているのか?
それは二つの現実が見逃され、そして一つの幻影が社会全体を支配していたことに起因しています。
まず一つ目の現実は、ひとくくりに経済と呼称されている世界が実体経済と金融経済の独立した二層から構成されているという現実です。実体経済とは社会の衣食住価値の産出と交換により利潤を産み出す経済です。
一方で金融経済とは実体経済の運営に必要な通貨資本を供給することにより利潤を生み出す経済です。この経済の二層構造の現実が見逃されていました。
もう一つの現実は、金融経済の方は、政府と中央銀行の金融政策によって成長しますが、一方の実体経済はそうはいかないという現実です。言い換えれば、実体経済に対しては、政府と中央銀行の金融政策は直接影響を与えることができないという現実です。
この現実については、米国社会では既に半世紀以上前からJ.K.ガルブレイスなど一部の経済学者によって公に指摘されていますが、それは少数意見に留まっています。米国社会でも日本社会でも、政府と中央銀行の金融政策が実体経済を直接成長させることはできないという事実が、見逃され続けてきたのです。
それらの現実がなぜ見逃されているのか?
その原因が、社会一般を支配している一つの幻影です。それは、金融経済の成長、すなわち株価の上昇があたかも景気の上昇、経済の成長であるかのような幻影です。これは実体経済と金融経済とを混同し、さらには金融経済の膨張をあたかも経済全体の成長であるかのごとく混同している結果です。
現実社会では、金融経済は、政府と中央銀行による金融緩和により直接成長あるいは膨張しますが、実体経済にはその影響が直接届くことなく、金融経済のみが一方的に膨張するのみです。この金融経済の一方的な膨張に実体経済がついていけていない現実は1980年代から現在に至る繰り返しのバブル破裂の歴史が証明しています。
具体的には、80年代の中南米、90年代の日本、東南アジア、韓国のバブル破裂、21世紀初頭では金融経済の源泉である米国でのITバブル破裂、2008年のリーマンショック、そして2022年7月現在の米国社会の急激インフレ現象がそれです。
実体経済の本質と特性 | 会社の進化成長は会社経営者と社員以外は誰も実現できない。
では、なぜ実体経済は政府と中央銀行による金融緩和政策に反応しないのか?
その原因は三段階の現実から生じています。
第一段階は、実体経済の基盤は会社の集合体であるという現実です。
第二段階は、その会社の成長は会社を構成する経営者と社員以外には、誰にも実現できないという現実です。
そして、第三段階は、会社を構成する経営者と社員の持続的な進化成長力の唯一の源泉、すなわち人間の創造力は、通貨供給の増減に機械的に対応して増減するものなどではないという現実です。
19世紀後半の産業革命最盛期には金融経済と実体経済との通貨需給は供給過少状態でした。そのような時代ならまだしも、21世紀の通貨供給過多の時代には、いくら通貨を増産供給しても、実体経済が、すなわち会社の経営者と社員の創造力が、通貨の供給に対応して自動的に高まることなどありません。
そもそも人間の創造力は人間性を基盤とするものです。人間の感情と感性に起動されるものですから、通貨供給を増やせば、あるいは資本や金融を潤沢に与えれば、自動的に起動するような、外部から機械操作できる対象ではありません。
日本株式会社の現状 | 株主第一主義という日本株式会社の衰退原因
では日本の実体経済を進化成長させるためにその基盤である会社、20世紀の高度経済成長の原動力となった日本株式会社、を再び活性化すればよいではないか!ということになります。
しかしながら、日本経済社会の現実はそれどころではありません。会社の持続的な進化成長力の土台が崩壊寸前の状況にあるからです。20世紀の高度経済成長をけん引した面影などどこにもありません。
どうしてこのような状態となったのか?
その最大の原因が、20世紀末の外資導入自由化とともに日本社会に流入浸透した米国型グローバル標準経営モデル、株主第一主義経営です。これが過去20年間に日本企業の進化成長どころか賃金の上昇すら実現できない、少なからずの数の企業では現状の維持すら危ぶまれる状況をもたらしています。
「会社は株主の財産であり、会社経営者も社員もその最大化を最優先で実現する義務がある。」との株主第一主義の使命命題が、その株主財産である当期利益最大化を最優先する経営により、会社の持続可能性を著しく衰退させてしまっているのです。
なぜそういえるか? 簡単です。株主第一主義とは、株主の財産最大化のために、他のすべての利害関係者のための価値を犠牲にすることであるからです。
社員への報酬や未来成長、社会と未来への貢献行動などは今期の利益増につながることが明らかな場合以外すべて後回し、あるいは却下されます。会社の持続進化のための投資などはその却下リストの最たるものです。
日本株式会社復興の第一歩 | 先ず株主第一主義とその強力尖兵を排除する
そこで、日本株式会社の持続的な進化成長を抑制し続けているこの株主第一主義を会社経営から排除することが必須緊急課題となります。
そして実はこの点については、株主第一主義の発祥の地である米国社会でも同様の動きが始まっています。既に2019年に、米国金融経済のシンボル的存在であるJPモルガンチェースのジェイミー・ダイモンCEOが主導する有力経営者団体である米国ビジネス・ラウンドテーブルですら、「脱」株主偏重経営(Scrapping Shareholder Primacy)を提唱しています。
これはまさに米国の実体経済の基盤である企業全体が衰退している状況判断に基づいています。金融経済自身もその基盤となる実体経済が衰弱し続ければ、バブルの破裂を繰り返しつつ、最終的には現状体制を放棄せざるを得なくなることは、洋の東西を問わず衆目一致するところとなっているのです。
株主第一主義の強力な尖兵 | 短期業績経営と総資本利益率
しかしながら、その米国においても、株主第一主義経営モデルから脱皮する効果的な具体施策は未だに提起されていません。脱株主第一と宣言はしたものの、それから先には進めていけないかのごとくの状況です。
巨大な金融経済を保有する米国とは異なり、そのような金融経済力もなく、また有力天然資源もない日本社会経済には、加工貿易を推進する実体経済を復興することが未来を拓く必須条件でもあります。
そこで、日本株式会社としては、株主第一主義が実体経済の、すなわち会社経営の、進化成長を衰退させている具体的な事象に着目してこれを排除することに取り組まざるを得ません。その具体的な原因、株主第一主義経営の尖兵ともいうべき存在が、短期業績経営とその実現効率指標であるROE (Return on Equity:総資本利益率)です。
株主第一主義そのものが必ずしも直接的に日本株式会社を衰退させているわけではなく、株主財産最大化実現の必須条件とされている短期業績最大化経営が、その未来をすべて犠牲にしても短期業績を最大化させる特性によって、未来への持続進化経営力、創造力を抑圧し続けているのです。その点を少し具体的に検証してみましょう。
短期業績経営と日本株式会社 | 短期業績経営が日本株式会社をどのように衰退させか?
まずは、当期利益の無条件最大化追求の結果、未来成長のための必須の種まきである研究開発投資が弱体化し続けました。短期業績と関連付けできる即効的な商品開発以外の長期研究開発投資が、中長期にわたる実現不確実性を理由に、当期利益を減少させる要因として一般的には排除され続けたからです。
さらには、当期利益最大化の観点からは単なる会計上のコストでしかない人件費も、さらにはそれを構成する正社員数も、着実に削減され続けてきました。企業の持続可能性を実現するために必須な創造力の唯一の源泉である「ヒト」が、株主のための生産合理性追求の観点からは、単なる労働力コストと会計判断されてしまっているのです。
特に経営者層は、当期利益の最大化を最優先する経営習慣とともに、その効率を証明する総資本利益率(ROE=Return on Equity)が8%以上であるべきとする経営義務圧力や、自社株価下落に対する不安感、を常時抱えています。そして社員層まで含めば、成果主義評価報酬制度による自己の年収の上下動が、定常的な心理ストレスとなり、それがさらに組織的な絆を破壊するのみでなく、相互協力の意欲すら低下させる個人業績競争を生み出しています。
これらが溢れる現状では、会社の持続可能性を目指すどころか現時点での存在意義を見出すことすら難しいでしょう。特に地下資源に依存できない日本経済の最重要基盤ともいえる製造業界企業群では、その極めて多くが既に20年以上にわたり、未来に向けてのエネルギーや魅力、活力を失い続けています。
新しい資本主義と日本株式会社 |「新しい資本主義」実現の大前提は短期業績経営の排除
しかし、この短期業績経営による企業の衰退は企業のみの問題にとどまりません。それらの企業群を最重要基盤とする日本経済も、当然のことながら企業の衰退とともに、同じく衰退し続けているのです。
政府による「新しい資本主義」の提言もこの日本経済の衰退傾向が深刻な状態に入りつつあることを示唆しています。新しい資本主義が目指す「成長」と「配分」も実体経済の実質的成長無しには実現できないからです。
たとえば、「資産所得倍増」はその資産運用対象である実体経済の成長無しには単なる金融経済のバブル膨張に過ぎません。また、「分配」もその原資は、金融経済のみならず、より大きな実体経済からの税収と、経済全体の、すなわちその最大基盤たる実体経済の、持続的進化を担保にした国債発行であることを忘れてはならないでしょう。
国債発行による政府と中央銀行による金融財政政策も、実体経済の実質的な成長を起動できなければ、その実情は金融経済のバブル膨張でしかありません。その膨張があたかも経済全体の成長であるかの幻影を追いかけていては日本の産業競争力復興は遠のくばかりです。
実体経済のそしてその中核母体である会社群、日本株式会社、の本質的な持続進化経営力の復興が、いまや日本経済の未来の命運を握っており、未来社会を拓けるか否かの鍵となっているのです。
では、どこから具体的に短期業績経営の摘出排除に取り組み始めるか?その切り口のヒントは、先の「新しい資本主義」の政府諮問委員会で政府が提起した、会社の「四半期決算義務の解消」、が骨抜きの内容となった事実に示されています。
「四半期決算義務の解消」は新しい資本主義の究極目標である企業の短期業績経営排除の第一歩でした。とはいえ、その四半期決算が無くなることで現状ビジネスに直接大きな損害を被る会計監査や証券業界の代表者にはその解消を支持することができないのはやむを得ないでしょう。
しかしその解消ができなかった最大の理由は、上場企業がこの四半期決算によってどれだけ中長期の進化成長活力を失っているかの実態全貌を把握し深刻に受け止めている人々がほとんどいないこと。さらには、四半期決算が象徴する短期業績経営が、日本株式会社、特に日本の上場企業群にどれだけ致命的な活力衰退をもたらしているかを定量的に証明する手段が存在していないことにあります。
次回は、日本株式会社は生き残れるか?というテーマを展開します。
また、筆者の最新著書は以下より購入することができます。
『持続進化経営力測定法』