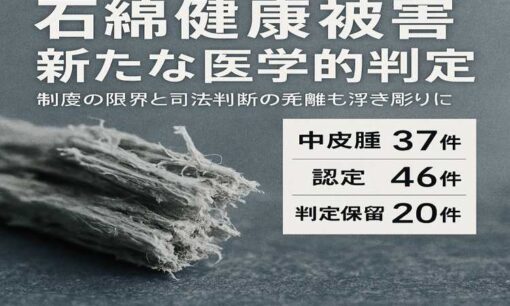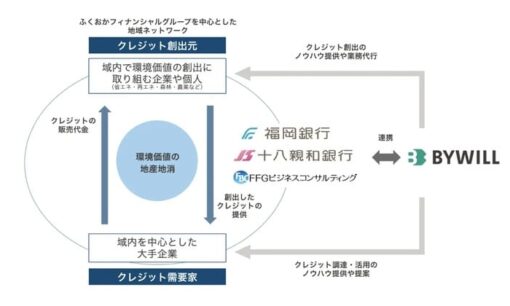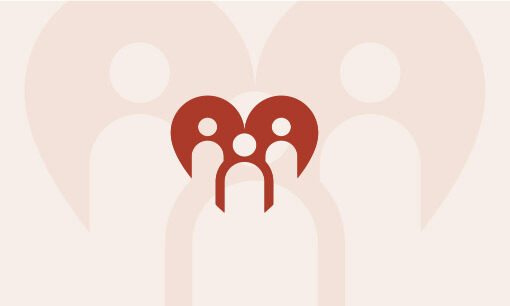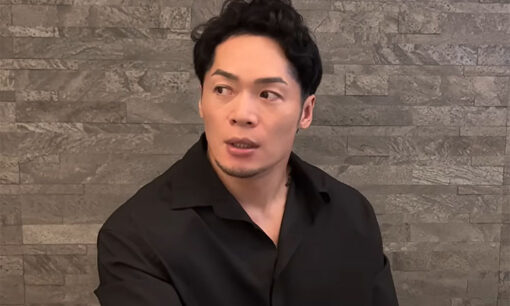悪質クレームや過度な要求によって従業員が精神的に追い詰められる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が、企業の喫緊の課題となっている。こうした現状を受けて、東京都は2025年4月、「カスハラ防止条例」を全国で初めて施行した。中小企業や飲食店を対象に最大40万円の補助金を交付する制度も新設され、現場に即した支援が始まっている。企業による自主的な対策を後押しする条例と支援金の意義と課題を探る。
顧客からの迷惑行為に歯止め 4月1日、東京都が全国初の条例施行
東京都は2025年4月1日、全国に先駆けて「カスタマーハラスメント防止条例」を施行した。これは、顧客による過度な言動から就業者を守るための法的枠組みであり、従業員に対する暴言や強要行為など、いわゆる「カスハラ」への対応を制度的に求めるものとなっている。
同条例は2024年10月に制定され、小池百合子都知事が表明した「都民ファースト」の理念の一環として位置づけられている。都内で事業を営む法人、個人事業主、国の機関などすべての事業者が対象となるほか、カスハラを行う顧客に関しては、都民であるか否かは問われない。
条例は「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と明記しており、企業や従業員のみならず、顧客にも冷静な対応を求める。特に事業者に対しては、就業者がカスハラ被害を受けた場合、加害者である顧客に対して適切な措置を講じる義務が課されている。
企業や店舗が独自に進めてきたカスハラ対策
カスタマーハラスメントが社会現象として認識され始めたのは2010年代中盤以降、接客業や小売業、医療現場などで従業員の精神的ストレスや離職が深刻な問題となったことが背景にある。企業や店舗側は、以下のような対策を積極的に導入してきた。
・従業員教育・マニュアル整備
クレーム対応のプロセスを明文化し、どのような言動がハラスメントに当たるかを明示。メンタルケアや接遇に関する研修も実施されてきた。
・録音・録画環境の整備
防犯カメラや通話録音機器の導入により、顧客とのやり取りを記録し、トラブル発生時の証拠保全を図る動きが広がった。
・従業員保護の掲示
店舗や窓口に「従業員への威圧的言動はお断りします」といった掲示を設置し、迷惑行為の抑止力とする施策が一般化している。
・外部専門家との連携
弁護士やコンサルタントによるアドバイスを受け、ハラスメント発生時の相談・対応窓口を設ける事例も増えている。
・エスカレーションルートの明確化
店舗単位で解決困難な場合には本部や管理職に引き継ぐ体制、SNS炎上対応も含めた危機管理体制の強化などが行われてきた。
こうした対策は一定の効果を上げてきた一方、特に中小規模の飲食店や小売店では予算やノウハウの不足から、十分な対策を講じられないケースも少なくなかった。
東京都の条例・補助金が果たす新たな役割
今回東京都が打ち出した「カスハラ防止条例」と奨励金制度は、従来は企業努力に頼らざるを得なかった現場の取り組みに、明確な制度的・財政的な後押しを与えるものである。
・制度的意義
カスハラを社会全体で解決すべき課題と捉え直し、顧客・事業者・従業員の三者に「責務」を明確化。社会的な規範として「悪質クレームは許されない」という意識を都民に浸透させる効果が期待されている。
・補助金の効果
特に資金面でハードルが高かったAIや録音機器の導入、マニュアル作成、従業員研修の実施などについて、最大40万円の奨励金支給によって初動の負担が軽減される。中小企業・個人事業主にも現実的な導入を促しやすい仕組みとなっている。
・抑止力の強化
記録機器の存在やハラスメント行為への注意喚起が顧客側にも伝わることで、迷惑行為の抑止につながる効果が期待できる。
こうした点から、条例と補助金は、これまで十分な対策が難しかった現場への実効的な支援策として機能し始めている。
実際のカスハラで“逮捕”も 法的処分に至ったケース
現時点で、カスタマーハラスメント(カスハラ)行為そのものに対して直接的な罰則を設けた法律は存在していない。しかし、既存の刑法等を適用することで処罰された事例は複数確認されている(『企業法務弁護士ナビ』による)。
・暴行罪(刑法208条)
賃貸保証会社の従業員に対し、顧客の男性が首を掴んで壁に押し付ける暴行を加え、現行犯逮捕された。
・強要罪(刑法223条)
大分市の運送会社において、顧客の男性が営業所長に土下座を強要し、その様子をスマートフォンで撮影。懲役10か月・執行猶予3年の有罪判決が下された。
・脅迫罪(刑法222条)
自治体職員に対し、「木刀で後ろからぶち破ってもいい」などと述べた男性が書類送検された。
・名誉毀損罪(刑法230条)
アパレル店の女性客が従業員に土下座を強要し、その画像をSNSに投稿した事件では、30万円の罰金刑が科された。
・業務妨害罪(刑法234条)
KDDIのフリーダイヤルに対し、8日間で約400回の無言電話をかけた高齢男性が、偽計業務妨害容疑で逮捕された。
飲食店や接客業の現場においては、過剰な謝罪の強要や人格否定にあたる発言などが日常的に見受けられ、従業員の心理的負担が深刻な問題となっている。こうした背景から、都内の一部事業者では録音・録画機器の設置をはじめとするカスハラ対策が進みつつある。
安全配慮義務と企業の責任 予防措置の強化が急務に
企業には労働契約法第5条に基づき、従業員に対する「安全配慮義務」が課されている。カスハラへの対応を怠り、就業環境を適切に維持できなかった場合、企業が損害賠償責任を負うリスクもある。
このため、カスハラは単なる“接客上のトラブル”ではなく、企業のガバナンスや労務管理の在り方を問われる問題として認識されつつある。東京都による今回の条例施行は、現場の声に応えたものであり、持続可能な労働環境を構築する契機といえる。
今後、国や他の自治体でも同様の法整備が進む可能性がある。現場レベルでは、接客の在り方と同時に、顧客の行動も問われる時代に入っている。