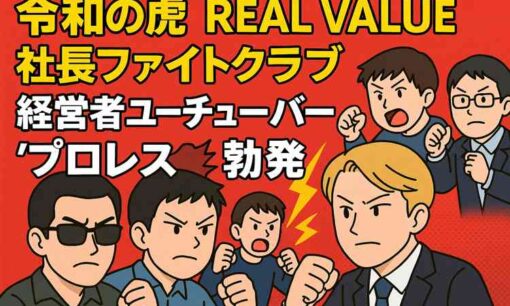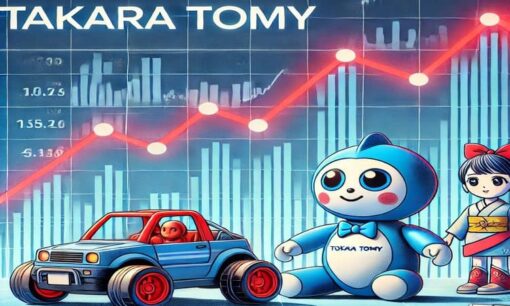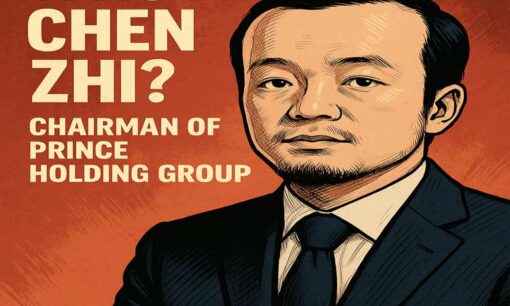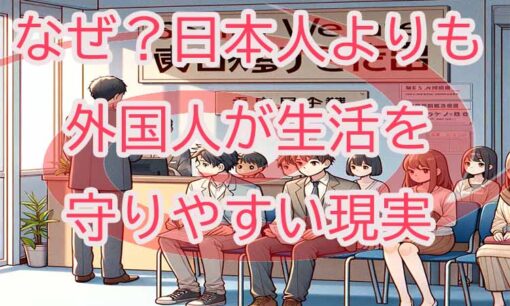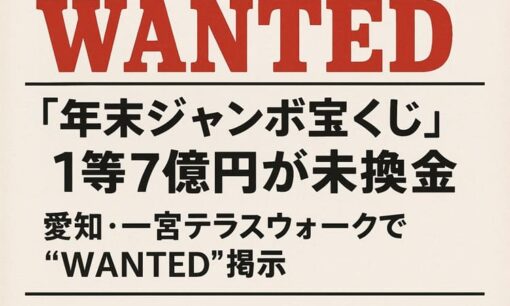株式会社JDSC(東証グロース、証券コード:4418)は13日、連結子会社であるメールカスタマーセンター株式会社の元従業員による不正行為について、外部の専門家を交えた調査委員会による報告書を受領し、取締役会において再発防止策を決定したと発表した。
JDSCは昨年11月12日、「当社連結子会社の元従業員による不正の疑いのある取引に関するお知らせ」を公表していた。2024年8月に開始された税務調査の過程で、メールカスタマーセンターの元従業員が外注先への発注額を水増しし、キックバックを受け取っていた疑いが指摘されたことを受け、調査を進めていた。
調査結果と対応策
JDSCは2024年10月に調査委員会を設置し、代表取締役CEOや取締役CFO、監査役(社外監査役を含む)らが主導する形で、外部の弁護士、公認不正検査士、税理士、公認会計士らの協力を得て調査を実施した。デジタル情報の調査・分析を通じて証拠保全などを行うデジタル・フォレンジックを含む詳細な検証を行った結果、不正行為は2016年4月から2023年9月の間に199百万円、JDSCの子会社になった2023年10月から2024年6月にかけて24百万円の売上原価の過大計上があったことが判明した。
不正行為は元従業員による個人的なものであり、類似の案件は確認されなかったとのこと。しかし、JDSCは職務分掌の不備や内部管理体制の脆弱性が、不正を許す一因になったと認識し、再発防止に向けた具体策を示した。取引担当者と承認者の職務を明確に分けるとともに、取引管理簿の作成や承認ルールの整備を進める。また、内部監査機能の強化にも取り組み、今後のガバナンス体制の改善を図る方針だ。
JDSCはまた、当該元従業員に対して刑事告訴を含めた法的措置を予定している。さらに、関連する役員についても月額報酬の一部を返上する処分を決定した。
代表取締役の加藤エルテス聡志社長は3カ月間にわたり月額報酬の30%を返上するほか、取締役(営業担当)、取締役(当社代表取締役)、取締役(管理担当取締役)についても、それぞれ月額報酬の10%を3カ月間返上する措置を講じる。
M&Aの難しさとPMIの課題
今回の不祥事が発覚したメールカスタマーセンターは、JDSCが近年M&Aにより傘下に収めた企業の一つ。JDSCが2024年8月に開示した「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」によると、M&Aを積極的に活用し、事業規模の拡大を図る戦略を取っているが、今回の件は、まさにMA後のPMI(Post Merger Integration、買収後統合プロセス)の難しさを示唆する事例となったといえるのではないか。
M&Aにおいては、買収先の企業文化や業務プロセスの統合は重要な課題となる。特に、ガバナンスの強化や内部管理体制の整備が不十分であると、上場企業であるJDSCのような高い透明性を求められる企業にとって、思わぬ不祥事につながる可能性がある。
今回の問題を受け、JDSCが今後どのようにPMIの手法を見直し、グループ全体のコンプライアンスを強化していくのかが注目される。
JDSCの事業概要と業績動向
JDSCは、AI技術を活用し、日本の産業課題の解決を目指す企業である。2013年に設立され、2021年12月に東証マザーズ(現グロース市場)へ上場。「UPGRADE JAPAN」をミッションに掲げ、産業DXを推進するためのAIソリューションを提供している。
代表取締役を務める加藤エルテス聡志氏は、東京大学卒業後、P&Gやマッキンゼー・アンド・カンパニー、米システムメーカーを経て2013年に一般社団法人日本データサイエンス研究所(JDSC前身)を設立。2021年も先頭に立って、産業DXの推進に尽力している。
経営に関しては、短期的な収益よりも中長期的な価値創造を重視し、AI市場の成長を取り込む戦略を展開している模様だ。
JDSCの事業の特徴として、産業ごとのデータ活用を促進し、単なるソフトウェア開発ではなく、産業全体の課題解決を目指している点が挙げられる。特に、東京大学の知見を活用し、データサイエンス、ビジネスエンジニアリング、コーポレートの三位一体のアプローチを強みとしている。また、M&Aによる非連続成長と、Joint R&D(共同研究開発)を通じた企業連携により、持続的な事業成長を図っている。
JDSCの強みと将来性
JDSCの強みは、AI技術を基盤にした幅広い事業展開にある。需要予測・在庫最適化の「demand insight」や、配送の最適化による不在配送問題の解決、さらには高齢者のフレイル(加齢による虚弱状態)を検知するAIプラットフォームなど、社会的課題の解決に直結するサービスを開発している。
同社は、特定のクライアント向けのカスタマイズ開発にとどまらず、産業全体の課題解決を目的とした「Joint R&D(共同研究開発)」を推進。大手企業との連携を強化し、データの蓄積を活かしたアルゴリズムの最適化を進めている。また、AIアルゴリズムを自社資産として保有し、複数の顧客に提供することで、収益の安定化を図る仕組みも整えている。
今後の展望
JDSCは今回の不正行為を受け、内部統制の強化とコンプライアンスの徹底に注力する方針を示した。M&Aによる事業拡大戦略を継続する中で、PMIの難しさが浮き彫りになったことで、今後はガバナンス強化とグループ全体の透明性向上が重要な課題となる。業績面では一定の影響があるものの、同社の事業基盤が揺らぐほどの規模ではなく、成長戦略に大きな変化はないと見られる。
今後はAI技術を活用した産業DXの推進を加速し、企業としての信頼回復に取り組んでいくことが求められる。