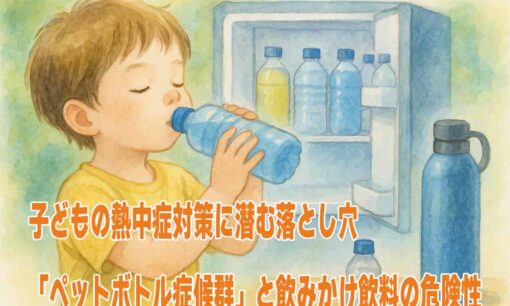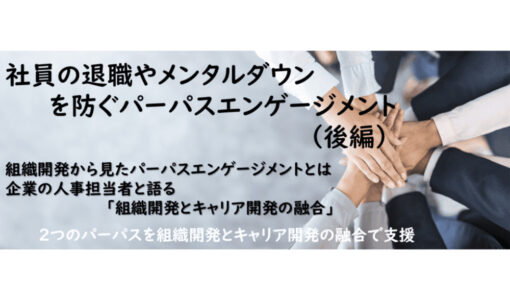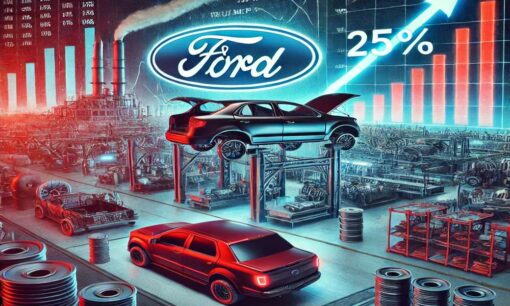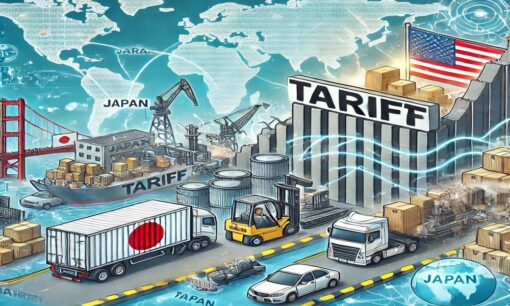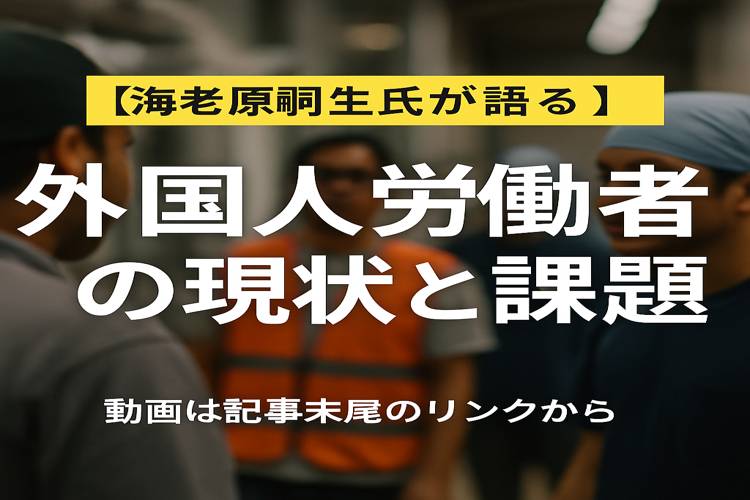
2025年7月15日、YouTubeのビジネスメディア「PIVOT」にて公開された一本の動画が注目を集めている。出演したのは雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏。「外国人政策、これが答えだ!」と題されたこの回では、日本の人口減少と労働力不足という現実に対し、留学生、技能実習制度、そして世界戦略を絡めた包括的なビジョンが提示された。
動画内での主張は大胆でありながらも論理的で、「移民=タブー」というこれまでの国内政治に風穴を開けるような議論となっている。
留学生・技能実習生が支える日本社会の現実
海老原氏が最も重視したのは、「今すでに日本は移民社会である」という現実を直視することだ。実際、厚生労働省と出入国在留管理庁の最新データによれば、2024年時点で外国人労働者数は約210万人を超え、うち留学生の就職数は年間約4万人に達している。
また、技能実習制度における在留外国人数も約32万人(2023年末時点)と高水準を維持している。
特に注目すべきは、「新卒で就職する外国人が全体の1割に迫っている」という構造的な変化だ。国籍別ではベトナム、中国、ネパールなどアジア圏の出身者が多数を占め、主に製造業、宿泊・飲食業、卸・小売業など、日本人若年層の人手が確保しづらい業種で戦力となっている。
留学生の場合、日本語学校 → 専門学校 → 就職というルートの定着率は高く、日本語学校卒業後の進学率は78%超(出入国在留管理庁 2022年)とされる。さらに特定技能制度を活用することで、卒業後も日本国内で5年、場合によっては永住権取得まで可能な環境が整っており、「留学生から労働者、そして定住者へ」という流れは既に確立されている。
「制度疲労」に苦しむ中小企業、救うのは“日本語ができる外国人”
では、こうした制度を受け入れる現場、特に中小企業ではどのような課題と期待があるのだろうか。
東京都内でコンビニエンスストアを3店舗経営する40代男性店主はこう語る。
「本音を言えば、日本人のアルバイトは定着しない。週3日しか入れない、2か月で辞める。ところが、ネパールやベトナムから来た留学生は真面目で、4年間働いてくれる。店の中核を担ってくれているのは間違いなく彼らです」
このような証言は珍しくない。実際、全国のコンビニにおける外国人留学生の就労比率は年々上昇しており、直近の統計ではコンビニ従業員のおよそ4人に1人が外国人(JFA 2024年)とされている。
一方、地方の中小製造業では別の課題も浮かび上がる。cokiでも取材した部品加工業(従業員50名)の経営者は次のように語る。
「技能実習生には感謝しているが、書類対応や監理団体とのやりとりは非常に煩雑。現場で使える人材でも、なかなか制度が追いついていない。あとは途中で脱走してしまったり、当社の場合は寮まで完備していたが、脱走した者たちが事件を起こし、けっこうな問題になってしまった」
この“制度疲労”の背景には、技能実習制度が元来「人材育成」の名目で設計されたため、労働力供給制度としての現実と齟齬が生じている点がある。海老原氏が主張するように、制度の正当化よりも、現実に即した「戦力人材」としての位置づけを明文化し、特定技能制度への移行を加速させる必要がある。
国家戦略としての「帰国後ファン作り」
本動画で最も革新的だったのは、「帰国後の外国人材を活用した世界戦略」だ。日本での就労経験を経て母国に戻った人材は、日本語や日本文化に精通しており、彼らを「非公式外交官」としてネットワーク化するべきと海老原氏は訴える。
実際、国際協力機構(JICA)でも「元研修生ネットワーク(Ex-Participants)」を活用したODA支援や人材育成が一部で進められており、日本に“友人”を持つ国づくりは現実的な構想である。
「日本語を学んだ人が世界で1000万人を超える時代が来れば、日本語は世界言語になる」──海老原氏の提言は、今は荒唐無稽に映るかもしれない。しかし、20年後の国際舞台で存在感を示す日本を構想する上で、避けて通れない問いでもある。
「ゲットー化」か、「同化」か──開かれた議論を
外国人受け入れ政策において避けるべきは、ドイツやフランスで問題となった「ゲットー化」の進行である。海老原氏は「同じ出身国だけで固まって暮らし、日本社会と断絶した状態」は排すべきとし、日本社会への同化こそが永住権付与の条件であるべきと提起した。
この点についても、中小企業側からは「寮ではなるべく多国籍メンバーにし、地域行事にも参加してもらっている」という工夫が実践されており、受け入れ側の努力も欠かせない。
詳しくはぜひ、以下の動画をご視聴いただきたい。本記事で紹介したのは、約1時間に及ぶ熱量ある議論の一端にすぎない。外国人政策の「現実」と「可能性」に正面から向き合う第一歩として、全編を通して観る価値は極めて高い。