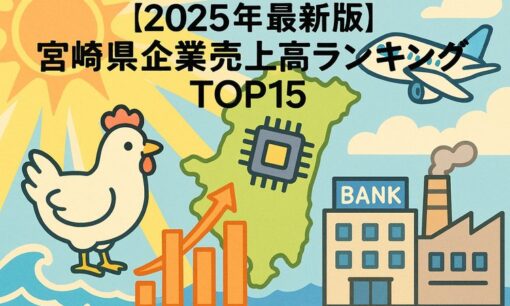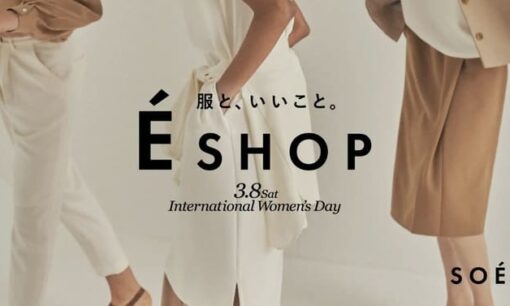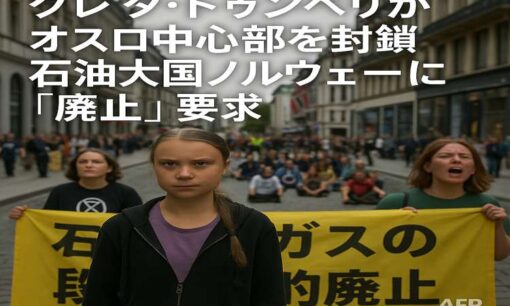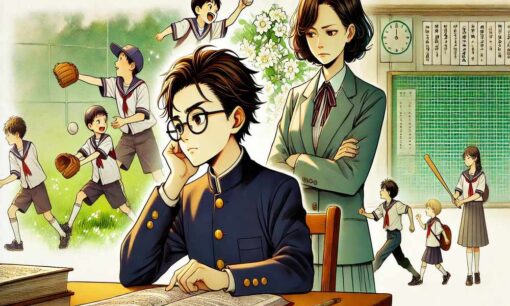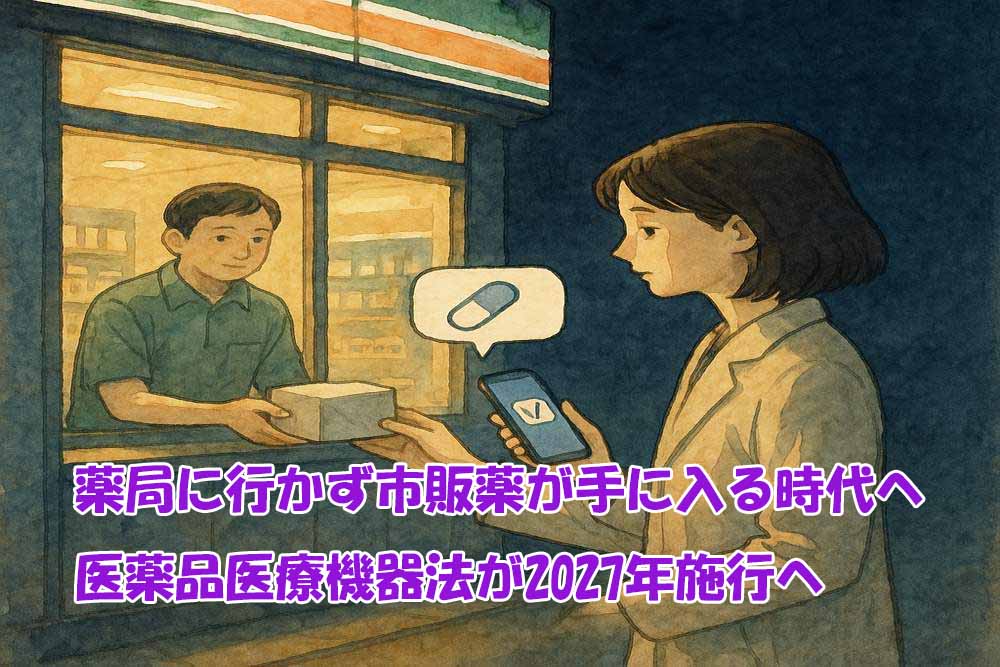
2025年5月14日、参議院本会議において改正医薬品医療機器法が可決・成立した。今回の法改正により、これまで薬剤師の常駐が必須とされていた一般用医薬品(市販薬)を、薬剤師がいないコンビニエンスストアなどで受け取ることが可能になる。施行は2027年春ごろを予定しており、事前にオンラインによる薬剤師等の説明を受けることが条件となる。
離島や山間部における“薬の空白”を埋める狙い
この改正は、医療資源が限られた地域に住む人々の医薬品アクセスを改善することを主な目的としている。とくに薬局の少ない離島や山間部では、ちょっとした風邪薬や鎮痛剤の購入も困難になるケースがあった。
厚生労働省は今回の改正によって、居住地や時間帯に左右されない“薬の入手経路”を拡充することで、地域医療の底上げを図る。自動販売機への拡大も検討されており、夜間や休日でも対応可能な新たなモデルとして期待が寄せられている。
消費者のメリット:24時間いつでも入手可能に
消費者にとって最大の利点は利便性の高さにある。コンビニの24時間営業体制を活かせば、従来の薬局の営業時間に縛られることなく、いつでも必要な市販薬を手に入れることができる。
また、オンラインで薬剤師から服薬に関する説明を受けたうえで、メールなどで受け取った確認証を提示すれば商品を受け取ることができるため、忙しいビジネスパーソンや子育て中の家庭にも恩恵は大きい。
安全性と理解度の確保に課題も
一方で、オンライン説明によって使用上の注意が適切に伝わるのかについては懸念もある。特に高齢者やITリテラシーが高くない層にとって、非対面による説明が十分な理解につながるかどうかは検証が必要である。
また、副作用や併用禁忌に関する判断を薬剤師の対面なしで正しく行えるかどうか、制度設計には慎重さが求められる。
コンビニ店舗にも新たな運用負担
店舗側にも一定の負担が生じる。現在、全国約5万7000店あるコンビニのうち、市販薬を取り扱っているのは0.7%に過ぎない(2023年2月時点、業界団体調べ)。多くの店舗は薬の扱いに不慣れであり、確認証の提示確認や誤受け取り防止のための業務フローの整備が必要となる。
また、冷暗所での保管や品出しのタイミングなど、食品や雑貨とは異なる管理体制の構築が求められる。
薬剤師・薬局への影響と制度設計の今後
薬剤師にとっても、オンラインでの説明対応が新たな業務として加わる。これまで薬局内で行ってきた接客業務が外部化されることで、業務量や対応時間帯の変化が想定され、労働環境への影響も少なくない。
加えて、従来は薬局での対面販売によって得られていた収益が減少する懸念もある。薬局は相談機能や調剤における専門性の強化を通じて、新たな役割を見出す必要があるだろう。
利便性と安全性の両立なるか
制度の施行までには、オンライン説明の品質確保、確認証の偽造防止策、緊急時の問い合わせ対応体制など、多くの課題が残されている。利便性を追求する一方で、安全性の確保をどのように担保するかは、今後の大きな焦点となる。
市販薬が“いつでも、どこでも”手に入る時代が到来することで、人々の暮らしはより快適になる可能性を秘めている。しかし、その一方で「薬を安全に使うための仕組み」への理解と信頼がなければ、制度の形骸化を招く恐れもある。
制度の根幹には、医薬品に対する消費者の責任ある使用が求められるという視点が、欠かせない。