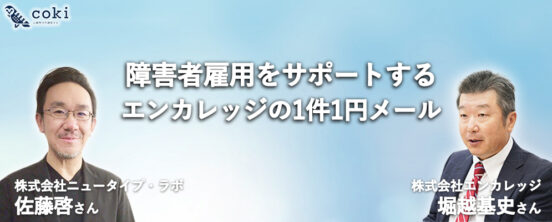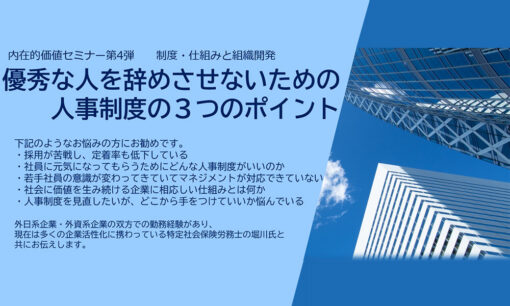後期高齢者医療制度における「紙の保険証」の新規発行終了が目前に迫っている。75歳以上のすべての人に影響するこの変化に対し、いま何を確認し、どのような準備を進めるべきか。本稿では、マイナ保険証移行の流れと、見落とされがちな医療費自己負担割合の注意点について、分かりやすく解説する。
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の者を対象とした公的医療保険制度である。75歳の誕生日を迎えた時点で自動的に、これまで加入していた健康保険組合や国民健康保険から後期高齢者医療制度へと切り替わる仕組みとなっている。
75歳未満であっても、一定の障害認定を受けた者については、例外的に加入対象となる場合がある。
この制度の運営は各都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が担い、保険料は個々の所得に応じて決定される。少子高齢化が進行する中、医療費財源の確保と世代間の負担調整を意図して設計された制度である。
紙の保険証からマイナ保険証へ
これまで後期高齢者には「後期高齢者医療被保険者証(紙の保険証)」が交付されてきた。しかし、2024年12月をもって新規発行は終了し、以降はマイナンバーカードを健康保険証として用いる「マイナ保険証」への移行が推進される。
現行の紙の保険証は、最長で2025年12月1日まで使用可能である。ただし、それ以前に有効期限が切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合には、その時点で失効となる。
各自で手持ちの保険証の有効期限を確認し、適切な対応を進める必要がある。
マイナ保険証を利用しない場合は「資格確認書」を申請
マイナ保険証への移行が進められているとはいえ、マイナンバーカード未取得者や、登録手続きに不安を抱える高齢者も少なくない。
そのため、希望者には「資格確認書」が交付され、紙の保険証の代替手段として機能する。
資格確認書は、マイナンバーカード未取得者や、健康保険証利用登録をしていない者には申請不要で交付される。また、要配慮者(高齢者や障害者など)で、受診時の配慮が必要な場合も、申請により交付が受けられる。
この資格確認書により、マイナ保険証を持たずとも医療機関で受診が可能となる。
資格確認書が交付されないとどうなるか
紙の保険証の有効期限が切れた場合、マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしていない者については、原則として自治体から「資格確認書」が交付されることとなっている。
資格確認書を所持していれば、医療機関等で保険診療を受けることが可能であり、窓口負担も通常どおりの割合で済む。しかし、資格確認書を受け取っていない、あるいは紛失した場合には、保険証の提示ができない状態となり、医療費を一時的に全額負担しなければならないケースも想定される。
そのため、紙の保険証の有効期限が近づいている場合には、資格確認書が手元に届いているかを必ず確認し、紛失した際は速やかに自治体へ再発行申請を行うことが求められる。
資格確認書の申請・再発行手続きまとめ
資格確認書の申請や再発行の流れについて、以下のように整理できる。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 必要かどうかを確認 | マイナ保険証を使っていない、または受診に困難がある場合は資格確認書が必要 | 紙の保険証の有効期限にも注意 |
| ② 市区町村窓口に申請 | 本人または代理人が窓口に出向き申請 | 電話や郵送申請が可能な自治体もあるため、事前確認が望ましい |
| ③ 申請時に必要な書類提出 | ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・代理人申請の場合は委任状 | 追加書類を求められる場合がある |
| ④ 資格確認書の交付 | 手続き完了後、資格確認書が交付される | 交付までに日数がかかる場合がある |
| ⑤ 紛失・破損時は再発行申請 | 窓口で再発行申請を行う | 破損時は可能であれば旧資格確認書も持参 |
| ⑥ 再発行時に必要な書類 | ・本人確認書類 ・(破損時)旧資格確認書 ・代理人申請の場合は委任状 | 紛失・破損理由を申し出ること |
医療費の自己負担割合にも注意
後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、一般に1割とされている。しかし、一定以上の所得がある場合、2割または3割負担となる点に留意が必要である。
具体的には、課税所得が28万円以上、かつ一定の年金収入やその他所得が基準額(単身で200万円以上、夫婦など世帯で320万円以上)を超える場合、2割負担に引き上げられる。また、課税所得が145万円以上ある場合は3割負担となる。
特に、年金以外に事業収入や給与、株式売却益などがある場合には、自己負担割合が増加する可能性があるため、収入状況を正確に把握しておきたい。
まとめ
後期高齢者医療制度は、日本の高齢化社会に不可欠な制度である。
2024年12月以降の紙の保険証新規発行停止に伴い、マイナ保険証への移行は避けて通れないが、手続きに不安がある場合は「資格確認書」による対応が可能である。
また、医療費の自己負担割合についても、収入によって変動することを理解し、適切に備えることが求められる。
一人ひとりが、制度の変化に合わせて必要な対応を早めに進めることが重要である。