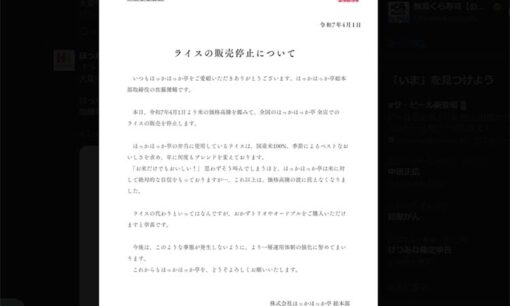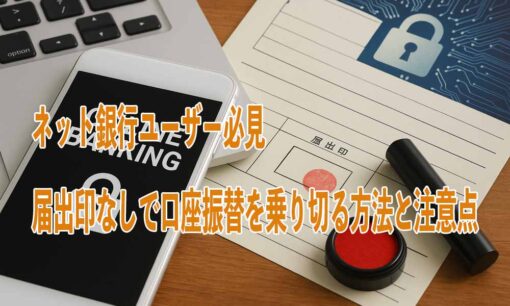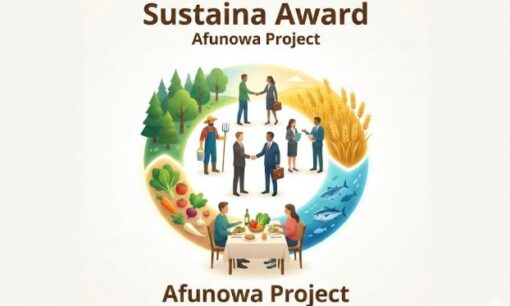日清食品が展開する栄養バランス食品シリーズ「完全メシ」の新CMに、実業家の堀江貴文氏を起用したことが波紋を呼んでいる。Xでは批判的な意見が相次ぎ、関連ハッシュタグ「#日清食品不買運動」がトレンド入りするなど、ネット上での議論が過熱している。
「すべて不快」――感情的拒否反応が爆発
問題のCM動画に対し、Xでは「冒頭から終わりまで全て不快」「精神衛生上の悪影響が出そう」といった投稿が散見される。味や栄養設計以前に、「この人物を“見ること”そのものがストレスだ」とする声が数多く寄せられた。
感情的な拒否反応は、しばしば論理的な製品評価とは切り離されており、これは広告デザインにおける「共感設計」が失敗した一例といえる。特にSNS時代においては、CMに登場する人物そのものが強烈な印象を与え、視聴体験全体を左右することがある。
「なぜ彼なのか」問われる日清の人選と説明責任
堀江氏は近年もSNS上での過激な発言を繰り返しており、ネット上では「更生していない」「常に誰かを攻撃している」といった声が絶えない。あるユーザーは「特定個人ではなく、集団に対する悪口を繰り返してきた」「好かれるわけがない」と批判し、企業の判断を疑問視した。
これに対し日清食品は、「完全メシは、栄養バランスを考え抜いた商品。根拠がなければ勧められない」として、起用の理由を一定程度説明している。しかし、タレントの選定においてその人物の「発信力」だけでなく「社会的受容度」も重視すべきではないかとの議論が生まれている。
広がる「不買運動」消費者との信頼関係が揺らぐ時
X上では、「#日清食品不買運動」のタグと共に、具体的な商品名を挙げた購入拒否の呼びかけが相次いでいる。中には「堀江を降ろすまでは沈黙を保つ」として、日清食品への態度保留を宣言する投稿もある。
こうした動きは、企業にとって単なるCM批判にとどまらず、ブランド全体への信頼を損なうリスクを伴う。炎上を火種とした「心理的距離の拡大」は、製品の優秀さだけでは埋め難い問題だ。
炎上の構造
今回の問題は、「共感の欠如」が最大の失敗要因として浮かび上がる。企業がどれだけ合理的な起用理由を持っていたとしても、消費者の感情に寄り添わなかったことが反発を招いた。
視聴者は、単に「誰が登場したか」ではなく、「自分たちにとってこの人物がどう映るか」という感覚でCMを受け取る。つまり、「正しい」よりも「心地よい」が選ばれる時代において、企業は共感設計の解像度を一段高める必要がある。
「嫌われ者」の起用は是か非か、問われる表現の自由
一方で、堀江氏には熱心な支持層も存在する。起業家としての実績や、既成概念にとらわれない発信は多くの共感も集めており、今回のCMも「彼らしい」「完全メシの合理性に合っている」と評価する声が一定数存在するのも事実だ。
むしろ、こうした批判を恐れるあまりに企業が起用の自由を狭めてしまえば、表現の幅が失われ、社会にとって健全とは言えない。日清食品のような大手企業が、賛否ある人物をあえて起用する姿勢は、マーケティングの自由度を守るうえでも一定の意義を持つだろう。
今後の対応に注目──企業姿勢が問われる時代
日清食品は現時点で本件に対する公式な謝罪や声明を出していないが、今後の対応いかんによってはさらなる炎上やブランド毀損につながる可能性もある。SNS上での消費者との対話、タレント起用における透明性、そして「共感を前提とした広告作り」が、企業にとっての新しいスタンダードとなりつつある。
時代の変化に応じて企業がどのような「共感設計」を行うか。同時に、あらゆる批判に萎縮せずに独自の表現を貫けるか。今回の騒動はその両立の難しさを浮き彫りにしている。