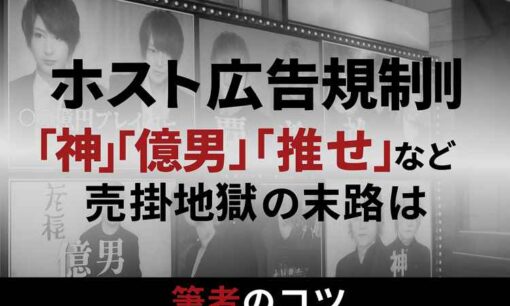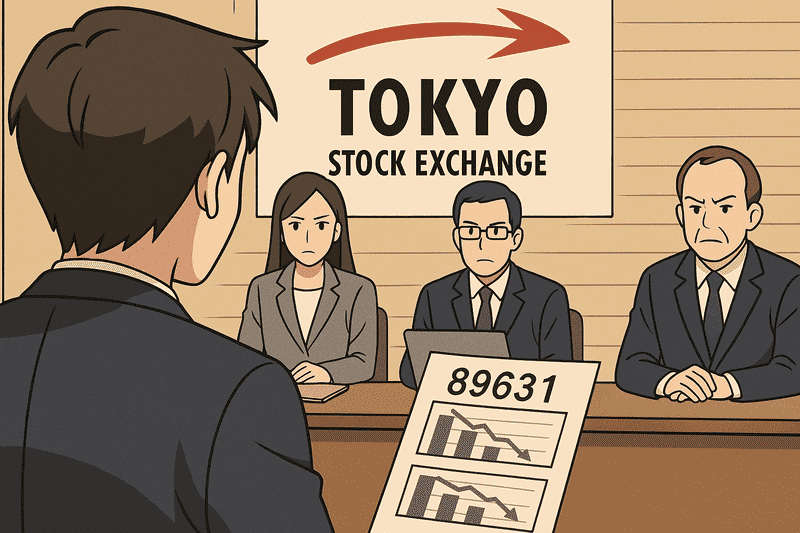
東証が経過措置を打ち切り、259社が「改善期間」に入った。制度改革の本格運用で企業の選別が始まり、資本市場に緊張が走る。
経過措置の終了で259社が「改善期間」に突入
東京証券取引所は、2022年4月に実施した市場再編に際し導入していた「経過措置」を、2025年3月末で順次終了した。対象となるのは、プライム市場69社、スタンダード市場143社、グロース市場47社を含む計259社。全上場企業の約7%にあたる。これらの企業は4月1日より「改善期間」に入り、1年以内に上場基準を満たせなければ、原則半年後の2026年10月1日に上場廃止となる。
基準未達の実態:プライムでも69社が崖っぷち
名目上は日本の最上位市場とされるプライム市場においても、69社が上場基準を満たせていない現実が浮かび上がった。東証が求めるのは、流通株式時価総額100億円以上、流通株式比率35%以上、株主数800人以上といった明確な数値基準である。基準に満たないまま上場を維持してきた企業は、今後1年間で構造的な課題と正面から向き合う必要がある。
流通株式・株主数・IR不足…企業体質の弱点があらわに
基準未達の背景には、複数の要因が絡んでいる。とりわけ流通株式時価総額の不足が目立ち、プライム市場の経過措置対象企業の約8割がこの項目で基準を満たせていない。特定株主による持株比率が高い企業では、市場での流動性が乏しく、改善のためには株主構成の見直しや資本政策の再設計が不可欠となる。
加えて、株主数や流通株式比率の未達も課題である。こうした基準は形式的な数字ではなく、企業のガバナンスや開かれた資本市場との関係性を示す指標として重みを持つ。IR(投資家向け広報)活動が不十分な企業では、情報発信力の不足も響いている。制度変更は、こうした企業体質を問い直す契機となっている。
制度改革の本質:過去の市場再編との決定的な違い
過去の市場区分再編、たとえば2000年代のマザーズ創設やジャスダック統合では、市場拡大や成長企業の取り込みが主眼だった。しかし今回の改革は、明確に企業の選別と質的向上を目的としている。長年、東証1部において多様な企業が混在していたことが、ガバナンスや成長性に対する信頼を損なっていた。新たな区分は、投資家の選別眼に応える市場構造を志向するものである。
国際的な投資マネーを呼び込むうえでも、上場企業の質は問われている。単なる数合わせではなく、企業価値の根幹に関わる基準をどれだけクリアできるかが、市場全体の信頼性にも直結している。
『投資家視点』あなたの保有銘柄は大丈夫か?今すぐ確認すべきチェックポイント
投資家にとっても、今回の経過措置終了は注視すべき動きである。保有銘柄が対象企業に該当する場合、基準達成に向けた計画やIR姿勢に注意を払う必要がある。
具体的には、有価証券報告書や決算説明資料を通じて、未達項目と改善方針を確認することが求められる。特に、プライム市場の銘柄であっても、時価総額や浮動株比率が低い場合は、基準未達による株価変動リスクを抱えている可能性がある。短期的な対応策だけでなく、中長期の経営戦略や資本政策の一貫性にも目を向けるべきだ。
生き残りの選択肢:統合か非上場か、問われる経営の覚悟
基準達成が難しい企業にとっては、統合や株式非公開化といった選択肢も現実味を帯びている。流通株式比率の改善が困難な場合や、大株主が株式を手放さないケースでは、他社との資本提携やM&Aが選択肢となり得る。
また、上場維持のための対応コストが重荷となる場合、非上場化を決断する企業も今後現れると見られる。とくに地方の中堅企業では、上場による成長資金調達よりも、安定的な経営基盤の維持を優先するケースもあるだろう。
ただし、非上場化は市場との接点を失うことも意味する。上場企業としての開示責任やガバナンス評価を手放すという選択が、本当に企業価値の向上につながるのか。慎重な判断が求められる。
経過措置の終了は、単なる制度変更ではない。企業にとっては、自らの経営体制と資本市場との関係を根本から問い直すきっかけとなっている。
市場に試される信頼:今こそ問われる「真の企業価値」
259社に与えられた1年間の改善期間は、数字の調整だけでは乗り越えられない。本質が問われているのは、企業の開示姿勢や成長戦略、そして株主との対話力である。
経過措置の終了によって、企業は「選ばれる側」であると同時に、市場に対して説明責任を負う存在としての覚悟を改めて問われている。資本市場の信頼を取り戻すには、企業と投資家、そして市場運営者の三者が、それぞれの立場で真摯に向き合う必要がある。
日本の市場構造は、今まさに転換点に立っている。