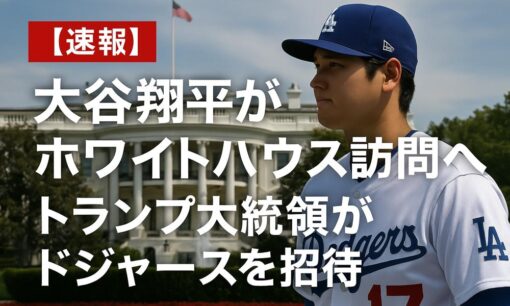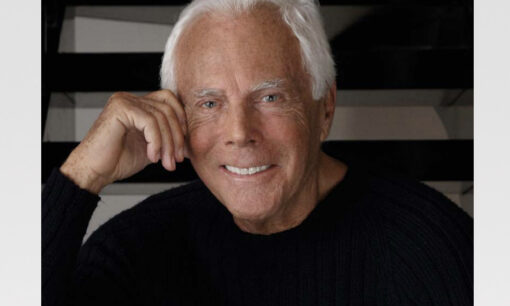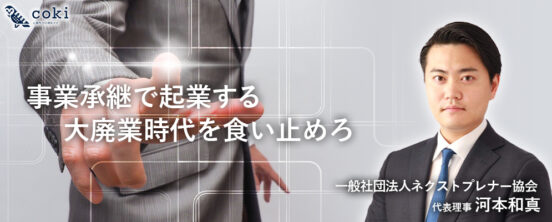スマホ、バッテリー製品の誤廃棄が火種に 製品設計と制度の隙間を突く「見えない危険」
リチウムイオン電池を原因とする火災が全国のごみ処理施設で相次いでいる。埼玉県内でも2023年末以降、上尾市と川口市の施設でそれぞれ火災が発生し、市民生活や自治体財政に深刻な影響を及ぼしている。背景には、製品構造や分別制度の複雑さ、情報提供の不足といった要因が重なっている実態がある。
上尾市西貝塚環境センターで出火 「一歩間違えば長期停止」
上尾市のごみ処理施設「西貝塚環境センター」では、2023年12月25日午後、ごみを粉砕機に運ぶコンベヤー上で火災が発生した。鎮火までに2時間を要したが、けが人はおらず、施設稼働にも影響はなかったという。
センターの担当者は、出火原因について「リチウムイオン電池の可能性が高い」とし、「一歩間違えれば、長期の稼働停止につながっていた」と振り返る。日々の処理工程では高温のごみを検知するセンサーが作動することも多く、その大半は電池を内蔵した製品が原因だという。
リチウムイオン電池は、軽量かつ長寿命、繰り返し充電が可能な特性から、スマートフォンやモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、コードレス掃除機、加熱式たばこ機器など、あらゆる小型電化製品に搭載されている。一方で、内部には可燃性の有機溶媒を含む電解液が使われており、強い衝撃によりショート・発火しやすい性質がある。
火災は収集時や破砕時の物理的衝撃によって発生することが多く、上尾市では2020年にも同センターで火災が起きている。毎日新聞によると、当時の修繕などには5億円以上を要したという。
「なぜ簡単に捨てられるのか」──制度の盲点
リチウムイオン電池を内蔵した製品が誤って可燃ごみなどに混入する背景には、複数の要因がある。以下に、主な理由とその影響を整理する。
| 理由カテゴリ | 具体的な理由 | 結果としての影響 |
|---|---|---|
| 製品設計上の問題 | 電池が製品内部に組み込まれており、外見からは電池入りとわかりにくい | 使用者が一般ごみに混ぜて廃棄してしまう |
| 制度上の問題 | 自治体ごとに分別ルールが異なり、統一的な基準がない | 市民が正しい出し方を把握できず、誤廃棄が起きる |
| 情報提供・啓発の不十分さ | 正しい捨て方が周知されておらず、住民が誤認しやすい | 火災リスクに対する意識が低くなる |
| 生活動線・利便性の障壁 | 回収ボックスの設置場所が少なく、処分が手間に感じられる | 適切な回収がされず、ごみに紛れて処理施設へ |
| 市場・製品流通の変化 | 安価な非正規品が流通し、説明書や廃棄情報が不十分なまま使われている | 回収対象外の製品が急増し、ごみ処理現場でトラブルが増加 |
こうした構造的な問題が複雑に絡み合い、火災の根本原因となっている。
上尾市では対策として、ホームページでリチウムイオン電池を搭載した製品をイラスト付きで紹介し、市役所や公共施設に「小型家電回収ボックス」を設置して回収を促している。
川口市・朝日環境センターではごみ収集停止 復旧に65億円超の見込み
今年1月3日には、川口市の「朝日環境センター」で火災が発生した。ごみピット内で出火し、市内のごみ収集が一時全面的に停止された。未回収のごみが各地の収集所にあふれ、市民生活への影響が広がった。
施設の一部再開は2025年12月、完全復旧は2026年3月を見込んでいる。復旧費や他自治体・民間事業者への処理委託費などは65億円以上に達する見通しだが、詳細な内訳は明らかにされていない。
出火原因は現時点で特定されていないが、市はリチウムイオン電池などの発火物が混入していた可能性を視野に入れている。今後、発火監視システムや自動放水銃の導入を予定する。
所長の平山英俊氏は「リチウムイオン電池は絶対に一般ごみに混入させず、『金属類』として出してほしい」と呼びかけている。金属類として出されたごみは圧縮せずに回収され、市が再資源化のための分別を行っている。
ごみ火災、全国で年1万件超 自治体の35%は回収体制なし
環境省によると、リチウムイオン電池が原因とみられる火災は、2020年度に約1万2700件確認されている。また、2023年度の自治体調査では、約35%が「不要となったリチウムイオン電池の回収を実施していない」と回答している。
回収制度の地域差、安全な廃棄方法に関する周知不足、そして住民意識の課題が横たわるなか、自治体と国の対応は待ったなしの段階にある。