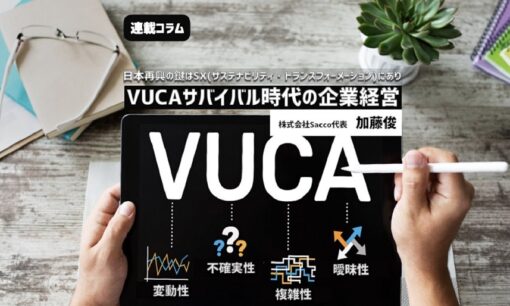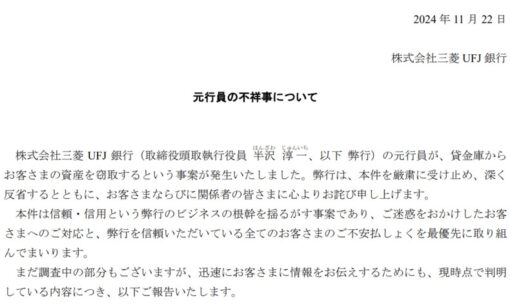水産庁は、太平洋側のサバ類の漁獲枠を現行の35万トンから8割削減し、6万8千トンとする案を検討している。資源量の悪化が背景にあり、価格高騰の可能性が指摘される。庶民の魚であるサバは今後どうなるのか。
サバ漁獲枠の大幅削減が検討される背景
水産庁は5日、太平洋側のマサバやゴマサバの漁獲枠を7割から8割削減する方向で調整していることを明らかにした。現在の35万トンから、6万8千トンまたは10万9千トンへと引き下げる2つの案が示されており、3月にも最終決定がなされる見通しだ。
この大幅な削減の背景には、サバ資源量の悪化がある。近年、漁獲量は減少の一途をたどっており、2018年には54.5万トンあった漁獲量が2023年には26.1万トンと半減している。特にマサバは、成長が鈍化し、成熟する前に漁獲されるケースが増えていると専門家は指摘する。
価格高騰の可能性と消費者への影響
漁獲量の減少に伴い、サバの価格はすでに上昇傾向にある。2014年に1キロ387円だった卸売価格は、2024年には565円と約1.4倍に上昇した。鮮魚店では、1匹732円で販売されているケースもあり、消費者からは「手に取りやすい価格帯だったが、これ以上上がると厳しい」との声が上がる。
さらに、漁獲枠の削減が決まれば、1匹800円から900円になる可能性も指摘されている。輸入サバへの依存が進む可能性もあるが、円安や輸送コストの影響もあり、価格が安定する保証はない。
サバ缶市場の動向と成長見込み
世界のサバ缶市場は成長を続けており、2022年には約8億2,180万米ドルだった市場規模が、2031年までに約14億8,500万米ドルに達すると予測されている。特に、すぐに食べられる加工食品の需要が高まる中、サバ缶の栄養価の高さや保存性が評価され、消費が拡大している。
アジア太平洋地域では、インド、中国、日本などでサバ缶の消費が増加しており、特に健康志向の高まりや、手軽に摂取できるシーフードの需要増が市場成長を後押ししている。漁獲枠の削減により、原材料価格が上昇すれば、サバ缶の価格にも影響を及ぼす可能性があり、業界関係者は代替品の開発や供給網の確保を進めている。
サバの代替品として期待される魚種
サバの漁獲量減少に伴い、代替品としていくつかの魚種が注目されている。イワシはサバと同じ青魚で、オメガ3脂肪酸が豊富であり、缶詰や塩焼き、味噌煮にも適している。価格も比較的安定しており、市場拡大が期待される。ホッケも脂がのった身質を持ち、焼き魚や加工食品に利用される。ニシンは欧州では缶詰や燻製で広く消費され、日本市場でも代替品として活用が進む可能性がある。サーモンは市場での認知度が高いが、価格がサバより高いため、普及には課題がある。メカジキは脂ののりが良く、煮付けやステーキ向きだが、高価なため、一般的な代替品としての広がりには慎重な対応が求められる。
今後、これらの魚種の市場拡大が進む可能性があるが、価格や供給の安定性が課題となる。
漁業者や市場関係者の反応
漁業関係者の間では、今回の漁獲枠削減に対して懸念の声が広がっている。一方で、長期的な資源管理の観点からは「資源を守るためにはやむを得ない」という意見もある。実際に、日本海や東シナ海のサバ資源は回復傾向にあり、適切な管理が効果を上げる可能性もある。
市場関係者は「価格高騰が続けば、消費者の需要が落ち込む可能性もある」として、代替魚種の検討や、加工食品としての利用促進など、新たな販売戦略を模索している。
今後の展望と求められる対応
水産庁は、3月にも最終的な漁獲枠を決定する予定で、今後の動向に注目が集まる。資源管理と経済的な影響のバランスをどのように取るかが問われている。
消費者にとっては、今後の価格動向を見極めつつ、輸入品の活用や代替魚の検討が求められるだろう。飲食業界にとっても、価格変動を見据えたメニューの工夫や仕入れ先の多様化が不可欠となる。
日本の食卓に欠かせないサバの安定供給を守るため、持続可能な資源管理と流通の工夫が急務となっている。