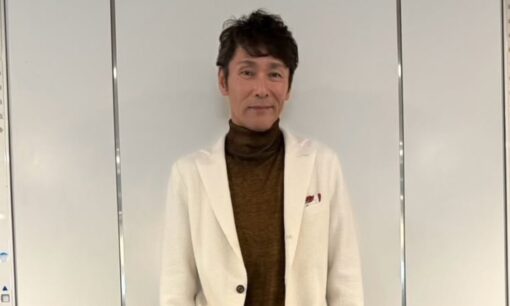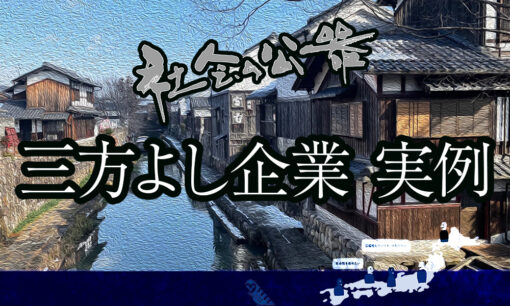メガネブランド「Zoff」が10月24日、2018年キャンペーンで使用した江口寿史氏のイラストに関する調査結果を公表した。
問題となったのは、4点のうち2点が雑誌掲載の写真を“無許諾で参考”に制作されていたこと。
SNS上での“トレパク疑惑”から広がったこの問題の核心は、技法そのものではなく、権利への配慮不足にあった。
SNSで浮上した“トレパク疑惑”の発端
10月初旬、江口寿史氏が手がけた『中央線文化祭2025』(ルミネ荻窪)の告知ビジュアルをきっかけに、SNS上で「無断トレースではないか」という指摘が相次いだ。
当初はイベント側の対応に注目が集まったが、過去の仕事にも疑念の目が向けられる。
その一つが、2018年にZoffが実施したキャンペーンだった。
当時、江口氏のイラストは全国の店舗でポスターやショッパーに使用され、ブランドの世界観を象徴するような存在だった。
Zoffが公式に認めた「2点は無許諾参照」
Zoffが24日に発表した調査報告では、イラスト4点中2点が「雑誌に掲載された写真を、権利者の許諾を得ず参考に制作された」と説明。
制作当時、その事実は広告代理店やZoffに報告されておらず、同社は「経緯を把握していなかった」としている。
残る2点は知人をモデルに、江口氏自身が撮影した写真をもとに制作されたという。
Zoffはモデル本人・所属事務所・出版社に経緯を説明し、謝意を伝達。関係者からの宥恕(ゆうじょ)を得た上で、補償については「江口氏と広告代理店、関係者間で協議中」としている。
Zoffが示した姿勢 “表現”ではなく“手続き”の問題
声明では、「江口氏の創作活動や表現手法そのものを否定するものではない」と明言。
「トレースや写真を参考にすること自体は、イラスト表現の一つとして尊重されるべき」としたうえで、
問題の本質は“権利配慮と報告の欠如”にあるとした。
企業としては、制作過程における権利確認や管理体制の見直しを進め、再発防止を誓う。
SNS炎上を経て、Zoffは“透明性”をもって対応する姿勢を示した格好だ。
創作と権利の境界線 現代のクリエイターが直面する課題
トレースやオマージュは、表現の世界で常に議論の的だ。
影響を受け、模倣し、そこから新たな創造が生まれる。芸術とは、そうした連鎖の上に成り立ってきた。
しかし、商業利用の場では「表現の自由」と「権利保護」のバランスが求められる。
今回のケースは、単なる“炎上”ではなく、現代のクリエイターが抱える倫理観・リテラシーの課題を浮き彫りにしたとも言える。
Zoffが示したように、“何を描くか”よりも“どのように描くか”が問われる時代に入っているのかもしれない。