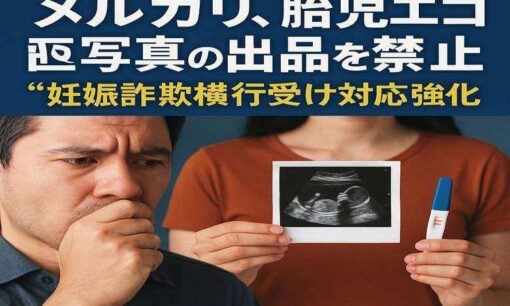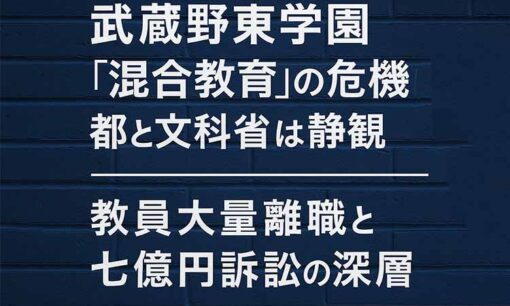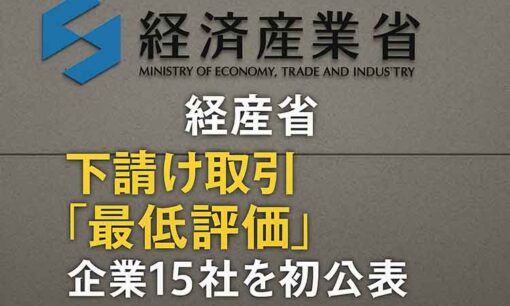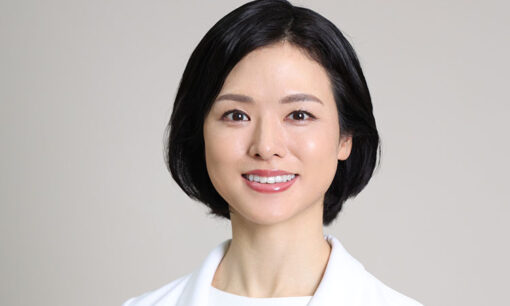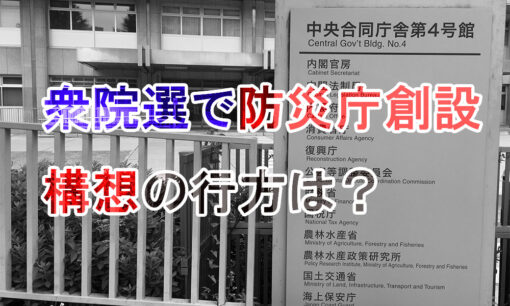フリマアプリ大手メルカリの社員に「無能」などとSNS上で発言したとして、インフルエンサーで個人投資家の田端信太郎氏(50)が警視庁麻布署により侮辱罪で書類送検された。かつてライブドアやLINEの執行役員を歴任し、今は“趣味は炎上”を自称する田端氏。
物言う株主として、メルカリの経営姿勢を公然と批判してきた同氏が刑事事件の被告発人となった構図は、企業ガバナンスとSNS社会の危うい接点を浮かび上がらせている。
侮辱罪の「具体的要件」と田端氏の投稿
今回の書類送検は、2024年11月から12月にかけて田端氏がX上で「無能を雇うのを株主からしたらやめてほしい」「クソな無能」と投稿したことが発端。対象となったのはメルカリが公式に公開していた社員インタビュー記事で、特定の担当社員の姿勢に苦言を呈したものとされる。
本件を受理した麻布署は、これらの発言が「公然と他人を侮辱した行為」にあたり、侮辱罪の構成要件を満たすと判断。被害者は告訴状を提出し、メルカリも「全て事実」と認め、従業員を守るために法的措置を講じるとコメントしている。
侮辱罪をめぐっては、2022年の法改正で上限刑が「1年以下の拘禁刑」に引き上げられた。背景には「テラスハウス」出演者・木村花さんの問題がある。SNS上の心ない投稿が人の命を奪う現実を前に、厳罰化の流れは当然のものと受け止められてきた。
しかし、それでもなお今回の田端氏のケースに対しては「これは明らかな言論統制ではないか」との反発も渦巻いている。
別件で浮かぶ「ネットリンチの構図」
田端氏をめぐるトラブルはメルカリにとどまらない。集英社オンラインの記事によると、過去には別の広報関係者との間でも侮辱や名誉毀損をめぐる問題が警察に持ち込まれたという。当人は「ネットリンチにあった」と語っているが、しかし、当時を思い返してみれば、当初の発端は、上場企業の役員としての過去の経歴に、一部のキャリアを少々誇張して書いているのではないかという、いわば“可愛らしいデコレーション”を田端氏に揶揄されたに過ぎないものだった。
この点について本人はXで正面から答えず、やりとりを「炎上」や「ネットリンチ」という問題にすり替えて幕引きを図り、田端氏とのやりとりを終了させていた。当時のSNSでは「本質から目をそらした対応ではないか」といった疑問の声が聞かれていたものだった。
「小物すぎる」対応か、正当防衛か
SNS上では、メルカリ側の対応を「小物すぎる」と揶揄する声も目立つ。あるユーザーはこう皮肉った。
「株主が会社に文句を言ったら刺してくるのは小物すぎるだろ。ましてや田端さんにこんなことをしたら、より燃え広がってマイナスになるのを想像できないのか」
株主の声を司法の場で封じる構図は、ステークホルダーエンゲージメントとは程遠い。メルカリは株主の批判に対し、対話や説明で応える道もあったはずだ。それを選ばず対応を一足飛びに、さながらクレーマー同等に扱い、警察に委ねたことで、逆に「言論弾圧」のレッテルを貼られるリスクを招いたのではないか。
もっともネット上では田端氏に否定的なアンチなどは現況を大喜びの体ではある。
田端信太郎氏、YouTubeでの反論
こうした状況下、9月21日、田端氏は自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿し、現状を説明した。彼は「書類送検は単なる事務的な手続きに過ぎず、起訴されるかどうか、有罪になるかどうかは今後の判断だ」と語った。
その一方で「一株主として公開情報をもとに役員や社員の行動を批判するのは正当な活動であり、不適切な言葉が含まれていたとしても、それは企業側が反論すればよいだけの話。警察を介入させること自体が強い違和感だ」と主張した。
また「これでアクティビスト活動をやめるつもりは全くない」と強調し、株主としての批判や提言を続ける姿勢を明言した。
「株主から意見されたことにいちいち警察に訴える世の中は、生き苦しく資本主義の根幹を揺るがす」と語り、言論の自由と株主権限を守る重要性を訴えた。
SNSで広がる「田端劇場」の見方
田端氏の動画公開後、SNSでは今回の件を逆手にとった皮肉も飛び交っている。
「メルカリが田端さんを訴える → 田端さんがXやYouTubeでネタにする → フォロワーや登録者が爆増する → 田端さんがパワーアップ → 再びメルカリ株を購入 → またバトル → 株価が注目され上昇 → 田端さんが売り抜ける」
まるで一人芝居のように繰り返される「田端劇場」が予想される、と揶揄する声もある。皮肉交じりながらも、炎上が新たな経済活動を生むという倒錯した構図を映し出している。
長谷川豊氏「これは言論の自由」
また元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏もXで発言した。
「これ、田端さん悪いか?『能力が無い』と書いて『無能』。理由があって強い言葉を使ったなら言論の自由の範疇だ。バカ、アホが侮辱罪なら日本人の8割が逮捕される。僕は以前から田端さんに色々言われた側だが、言論の萎縮は民主主義社会にとって良くない」
自身も田端氏から批判を受けてきた立場であるにもかかわらず、今回の書類送検には疑問を呈し「臆せず自由闊達に発信を続けてほしい」とエールを送った。
言論弾圧とも感じられるステークホルダー軽視の企業姿勢
今回のメルカリの対応には疑問を持たざるを得ない。田端氏がもしメルカリの株主でなかったなら、メルカリの対応はまだ理解できる。だが、実際には最も重要なステークホルダーの一つである株主であり、一連の発言はどこをどう切り取っても、企業価値向上を願っての発言だった。そうした株主からの提言を「誹謗中傷」と翻訳し、警察を介入させたメルカリの姿勢は、株主との対話を軽視した「言論封殺・言論弾圧」と映る。
もちろん、メルカリや他の訴えを起こした者たちの言い分として「田端氏と直接やりとりをすれば、その過程をSNSで全て開示され、再度炎上する」との懸念があっただろうことは予想できる。
しかし、それであっても、まずは直接のコミュニケーションを試み、「開示をしないでくれ」とお願いをしたうえで再度コミュニケーションを試み、それでも事態が収拾できない場合になって、はじめて警察という選択肢が考えられるというのが正しい道だったのではないだろうか。
個人投資家の声を最初から司法で封じる姿勢は、ステークホルダーエンゲージメントをないがしろにする「がっかりな対応」である。
田端氏の批判は、多くの個人投資家が抱えてきた不満を一部代弁するものであった。だからこそ、SNS上で一定の拡散を見たのだろう。その声を「言論弾圧」で抹殺するかのような今回の対応には、メルカリに好意的な人の多くも失望に繋がっただろう。
ましてや田端氏が言及した社員はダイバーシティやインクルージョンを担当するDEIにも言及していた社員であった。もし、彼女のたっての行動としての今回の警察に泣きを入れる行為だったのだとすれば、それは多様性や包摂の意味をはき違えているとしか思えない行動である。ダイバーシティとは出自や肌の色などだけではなく、意見の違いをも尊重することのはずである。それが、異論をこれほどド直球のストレートで司法で排除するやり方は「多様性や社会包摂のはき違え」と言わざるを得ない。
確かに田端氏の表現は過激すぎる面があったのだろう。しかし、だからこそ「対話で受け止め、反論で返す」姿勢こそがDEIの人間やコミュニケーションのプロである広報には必要なスマートさだったハズであるし、それがプロなのではないか。炎上の被害にあった者にとって、見えない多数を煽動され批難にさらされる、それは本当に恐ろしいことだったのだろう。
しかし、自分たちがとった行動が、警察という「暴力装置」を安易に用いることでの返礼であったというのは、これ以上に暴力的な行為はないし、それはもう、SNSでの罵詈雑言の比ではない、最悪の悪手、企業人として正しい行為とは思えない行為に映る。
メルカリはこれでよかったのだろうか。
こんな形でステークホルダーエンゲージメントを軽視する企業だったということに、少なからずショックを覚える。
言論と統制の狭間で
侮辱罪の事例集を見れば、路上で「デブ」と叫んだだけで9900円、Googleマップに「最低」と書けば20万円の罰金が科されるようだ。社会全体が「言葉の重さ」を問い直す流れにあるのは事実だ。その一方で、企業と株主の関係に刑事罰が持ち込まれた今回のケースは、法の運用が「正義」か「言論統制」かを問う分水嶺に立っている。
田端氏の発言は過激で不適切だったのか、それとも正当な株主提言の一環だったのか。メルカリの対応は社員を守るための正当防衛か、それとも株主の声を封じる「小物対応」か。
裁判所の判断は、単なる炎上騒動を超え、日本の株主社会における“言論の自由”の境界線を画することになりそうだ。
かつて、伝統的な日本型経営の価値観に勢いがあった時代、日本企業はどこもおおらかであった。週刊誌は羽織ゴロと言われ、酷い罵詈雑言・悪罵を企業に吐いたものだが、言われた側の企業は、指摘をバネに、なにくそ見返してやるぞ!という、気概をもっていた。日本企業が弱くなったのに歩調を合わせて、多少のトラブルさえ自己解決を試みない、軟弱者が増えてしまったことは残念である。
SNSによる炎上の被害はかつてはなく、それは怖いものあろうが、安易に警察といった司法の「暴力装置」に訴えるスタンスの方が、よっぽど怖い社会の到来を予感させるものである。