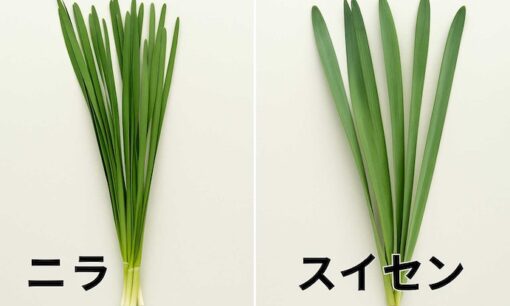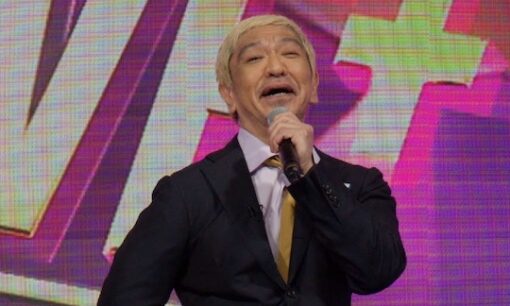選挙のたびにSNSがにぎわう。公約、演説、候補者の素顔──すべてが手元のスマホに流れてくる時代。特に若い世代は、新聞やテレビではなくSNSを通じて政治に触れている。しかし、そこに流れる情報は本当に信頼できるのか。世代間の違いやリスクも含めて、SNSと選挙情報の関係をリベラルな視点から見つめ直したい。
政治を知る入り口としてのSNS
近年、選挙前になるとSNSが情報の主戦場となる。X(旧Twitter)では候補者の政策がタグと共に拡散され、Instagramでは日常の様子を通じて親しみを演出。YouTubeでは長尺の演説動画、TikTokでは政治系コンテンツを編集した短尺動画も人気だ。
特に10代〜20代の若者にとって、SNSは「政治を知る最初の入り口」になっている。文字だけでなく動画や画像を使って伝える形式は、従来の新聞や選挙公報よりも圧倒的に身近で分かりやすい。気候変動、ジェンダー平等、教育格差といったテーマも、SNS上の議論を通じて注目されるようになった。
リベラルな視点から見れば、これは歓迎すべき変化だ。これまで届きにくかった若年層やマイノリティの声が、政治空間に参加するきっかけになり得るからだ。
SNSの落とし穴…偏りと分断の構造
しかし、SNSには明確な弱点もある。それが「情報の偏り」だ。SNSのアルゴリズムは、ユーザーが「好む情報」を優先的に表示する。リベラルな立場の人はリベラルな情報ばかりに触れ、保守的な情報には出会いにくい。結果として、「エコーチェンバー」と呼ばれる、同質な意見に囲まれた状態が生まれる。
この偏りは、他者との対話の機会を奪い、社会全体の分断を深める。さらに、切り取られた発言、誤解を招く編集、事実と異なる投稿も日々飛び交う。SNSでは、事実よりも「拡散力」が優先される構造があるため、フェイクニュースが一瞬で広まることも珍しくない。
政治参加の促進と引き換えに、民主主義の健全性が揺らぐリスク──これが、SNSに潜むジレンマだ。
世代で異なるSNSとの付き合い方
SNSを選挙情報の参考にするかどうかは、世代によっても大きく異なる。10〜20代は、政治情報の主要な入手先としてSNSを活用している。総務省の調査では、若年層の3割以上が「信頼できる情報源」としてSNSを挙げている。
30〜50代は、テレビや新聞などの既存メディアとSNSを併用する傾向にある。SNSの情報を鵜呑みにすることは少なく、比較的冷静に情報を判断している。
60代以上では、SNSの利用率自体は低いが、YouTubeやLINEなどを通じて政治情報に触れている層も増えている。ただし、「SNSは信用しない」と言いつつも、LINEで届いた未確認の情報をそのまま共有してしまう例もある。
世代ごとにSNSとの距離感は異なるが、いずれにも共通しているのは、情報の正確性を見抜く力=リテラシーが求められている点だ。
「信じすぎず、使いこなす」ために
SNSは便利な道具だが、使い方を誤れば危険な情報の入り口にもなる。だからこそ、政治に関心を持つきっかけとしてSNSを使うことは肯定しつつ、その情報を鵜呑みにしない習慣を持つことが大切だ。
たとえば、候補者の発信が本当に過去の発言や実績と整合しているか、SNSで話題になっている政策が現実的なのか。SNSを入り口に、信頼できる報道や公式資料で裏取りをするという行動が、これからの有権者には求められる。
「批判的に読む力」を育てることが、SNS時代の政治参加の前提条件となる。
SNSを民主主義の“味方”にするために
SNSが政治を遠くから近くへと引き寄せたのは事実だ。だがそれが「分断」ではなく「対話」につながるためには、使う側の意識と責任が問われる。
リベラルな社会とは、多様な意見が共存し、異なる立場に耳を傾ける姿勢がある社会だ。SNSはその理想を支えるツールにもなり得る。問題なのはSNSそのものではなく、私たちがどう使うかにある。
選挙情報にSNSを活用するなら、「選ぶこと」と「調べること」はセットで考えたい。情報を見極め、意見を交わし、行動に移す──その積み重ねが、よりよい民主主義を支えていく。