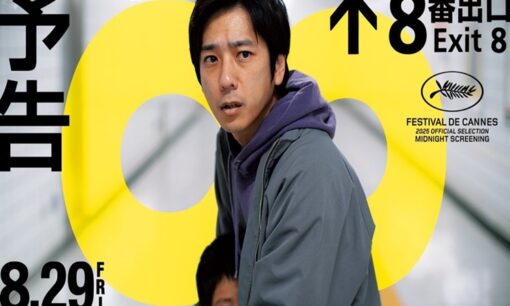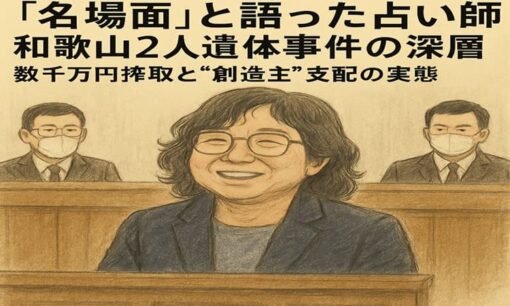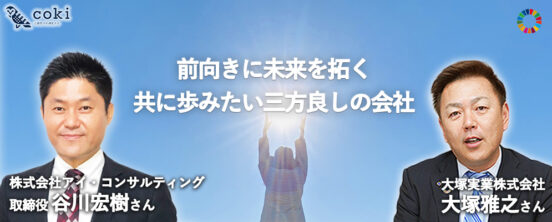千葉県市川市立塩焼小学校に勤務していた教頭・小林佳巨(52)が、保護者から徴収した修学旅行費や教材費などの学校徴収金約1330万円を着服していたことが明らかになった。千葉県教育委員会は5月26日、小林教頭を懲戒免職処分とし、千葉県警が横領事件として捜査を進めている。
発覚は校長の通帳確認から 2年間気づかれなかった着服の手口
着服が行われたのは、令和5年6月から令和7年3月までの約2年間にわたる。事件の発端は、塩焼小学校の校長が学校徴収金に関する通帳を確認したことだった。帳簿と通帳残高に不自然な差が見つかり、調査の結果、少なくとも13,310,242円が不正に引き出されていたことが判明した。
教育委員会の事情聴取に対し、小林教頭は「生活費などに使った」と着服を認めた。公金を私的に流用する行為は重大な職務違反であり、地方公務員法に基づいて即日免職とされた。なお、事件の監督責任を問われた校長に対しても、減給処分が下されている。
小林教頭による着服は、通常であれば早期に発見されるべきものである。しかし、2年近くにわたり発覚しなかった背景には、学校内の会計監査体制の甘さがあったとの見方が強まっている。
SNSの声 なぜ着服できたのか、広がる謎
SNS上では、「保護者が積み立てたお金は学年ごとに管理され、使途や残金は明確に報告されるはず」「学校が何百万円もの現金を管理していたこと自体が驚き」「今では修学旅行費は外部業者を通じてコンビニ払いやクレジット決済が一般的。現金を扱う必要はない」といった意見が目立つ。保護者や教育関係者からは、学校の会計処理の旧態依然とした仕組みが今回の不正を可能にしたとする批判が噴出している。
また、教員経験者からは「通帳は金庫で保管し、現金の出し入れは複数の教職員の確認が必要」「保護者会長らによる会計監査が実施されているのが普通で、誰かが旅行費や教材費を個人的に引き出せる状況など考えられない」といった声も上がる。つまり、今回の事件は小林教頭個人の不正にとどまらず、学校全体の運営体制の欠陥をも示している。
教育委員会が緊急対策 再発防止に向けた研修と制度見直しを指示
県教育委員会はこの事態を重く受け止め、全教職員に対し緊急研修を実施するとともに、各学校に対して会計処理体制の緊急点検を指示した。あわせて、再発防止に向けた年間計画の作成と共有を義務付け、学校長を中心とした組織的な監査・情報共有体制の強化を求めている。
また、県としては現金取扱の最小化や外部監査制度の導入など、根本的な仕組みの見直しも視野に入れている。県教育委員会は「県民の信頼を著しく損なう行為が発生したことを深く反省している」との声明を発表し、綱紀粛正に向けた取り組みを本格化させる構えだ。
保護者の善意による積立金が不正に流用された今回の事件は、教育現場の信頼性そのものを揺るがすものである。着服の責任は当然ながら小林佳巨元教頭個人に帰すべきものだが、同時に制度や監督体制の不備が不正を許したこともまた、厳しく問われなければならない。教育現場における信頼の回復と再発防止に向けた取り組みが、今後強く求められている。