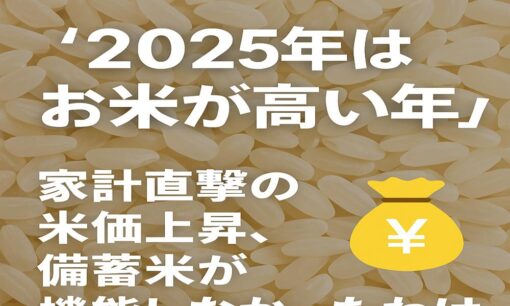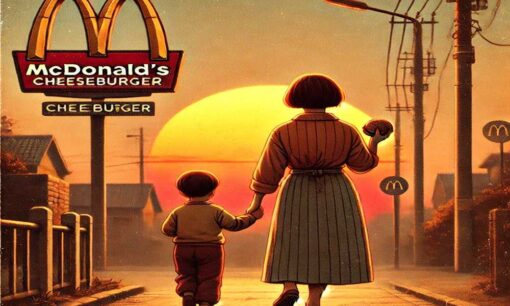江藤前農水相の“縁故米発言”が引き起こした波紋
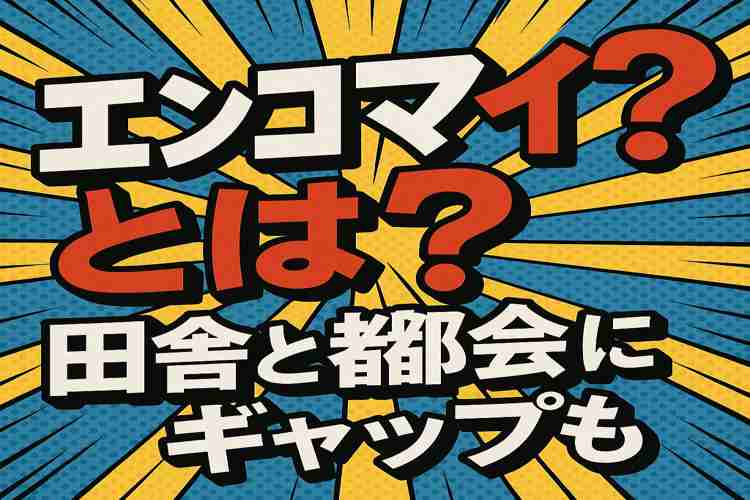
「縁故米(えんこまい)」という言葉が、思わぬ形で国政の焦点となった。発端は江藤拓・前農林水産大臣が佐賀県での講演で発した次の一言だった。
「私はお米を買ったことがありません。支援者の方にたくさんもらうから。売るほどある」
この発言が世に出るや、SNSを中心に「生活者感情を逆撫でしている」「価格高騰に苦しむ庶民を理解していない」といった批判が瞬く間に拡散。結果として、江藤氏は事実上の更迭に追い込まれた。後任には小泉進次郎氏が就任し、若手ながら農政の刷新を期待される立場となっている。
縁故米とは──“見えないお米”が社会の分断を照らす
では、その「縁故米」とは何か。これは市場を介さず、親戚や知人などから無償で贈られるお米のことを指す。地方、特に農村部では秋の新米が穫れた際、家族や恩人に送るという文化が根強く残っており、それはギフトであり、心のこもった便りでもある。
だが、この縁故米という言葉自体、都市部の住民には聞き馴染みがない。SNSでは「都会の奴らは縁故米を知らないのか」「こんなことも知らずに米の価格を語るのか」など、地方出身者や農家関係者から驚きや苛立ちを込めた投稿が散見され、都市と地方の感覚のズレがあらわになった。
田舎の“物々交換経済”と都会の“貨幣経済”の断絶
この反応の背景には、都市と農村における経済観のギャップがある。農村では野菜や米の“おすそ分け”が今も日常的で、贈答の文化も根強い。収穫物を余らせず分け合うことが、生活の知恵として機能してきた。一方、都市では流通や価格がすべてであり、「タダでもらえる米」が存在すること自体に驚きがある。
縁故米は、統計上は見えない流通に属するため、都市住民にはブラックボックスのように映る。だが、これは「ローカルフードシステム」としても注目される代替的な食料循環であり、フードマイレージの削減やトレーサビリティの確保といった観点でも意義がある。
石破総理、農政転換を明言 “コメ5キロ3,000円台”の約束
江藤氏の失言と更迭によって高まった農政批判を受け、石破茂総理と国民民主党代表・玉木雄一郎氏との間で行われた党首討論では、農政の将来像に関する重要な発言がなされた。
石破総理はこの討論の中で、「コメは5キロ3,000円台でなければならない。価格が下がらなければ責任を取る。コメは増産が必要だ」と明言した。これは従来の需給調整による価格維持から一転して、安定供給と価格抑制の両立を目指すという方向性を打ち出したものだ。
玉木氏も「中身のあるやり取りができた」と評価し、この答弁が農政の大転換につながる可能性を示唆した。
“縁故米”が照らす、日本の未来の食のかたち
縁故米は、単なる「コネ」や「特権」といった否定的なイメージでは語り切れない。そもそも「縁故」とは、人と人とのつながりを意味し、その象徴としての縁故米は、地域の助け合いや贈答の文化そのものだ。これは有機農業の分野で「CSA(Community Supported Agriculture)」や「産消提携」として制度化されているものとも通じる。
政治的失言がきっかけとなったとはいえ、「縁故米」という存在をめぐる議論は、私たちが“食”をどのように捉え、誰と分かち合っていくのかという根源的な問いを突きつけている。都市と農村の距離が離れる現代において、こうした見えない絆の再発見は、単なる懐古趣味ではなく、次代のサステナブルな食料政策の一端を担う可能性すらある。
石破政権の下、コメ政策の転換が実現するのか。縁故米をめぐる騒動は、日本の農と食の未来に一石を投じた。