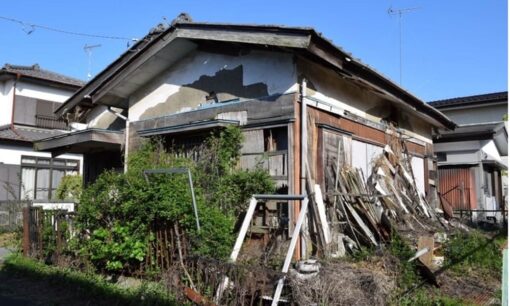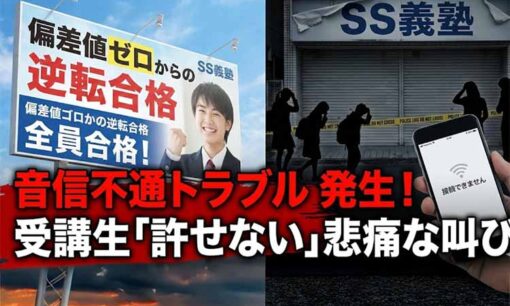高齢化が進む日本で、終末期医療のあり方が問われている。特に、回復の見込みがなく、強い苦痛を伴う患者が自身の意思で人生の終止符を打つ「安楽死」の是非について、議論が求められている。
産経新聞が2月9日に報じたカナダの安楽死制度についてのニュースをきっかけに、日本国内でも安楽死の是非をめぐる議論が活発化している。SNSでは「現役世代の負担を考えれば必要」「安楽死があれば無駄な延命治療を避けられる」などの声が相次ぎ、制度の在り方について賛否が交わされている。
カナダでは2016年に「死への医療的援助法(MAiD)」が成立。さらに2021年には「死期が予見できる」要件が撤廃され、適用対象が拡大された。これにより、末期患者だけでなく、回復の見込みがなく強い苦痛を抱える患者も安楽死を選択できるようになった。しかし、その判断が医師の裁量に委ねられすぎているとの指摘もあり、制度の運用には慎重な検討が求められている。
日本の医療制度は持続できるのか? 高齢化社会が直面する課題
日本では、寝たきりの高齢者に対する延命治療が保険適用され続けているが、これが今後も持続可能なのかは疑問だ。医療財政の逼迫に加え、家族の経済的・精神的負担も大きく、胃ろうなどの苦しさを思うと「本人も延命を望まないのではないか」との意見がある。
ただ、難しいのは、高齢患者の年金をあてにして生活している家族が是が非でも患者の延命治療を乞うというこの世の地獄のようなケースがままあることであり、これは同時に、8割以上が医業利益赤字ともいわれる病院側にとっても大きな飯のタネになっているという問題だ。さながら、複雑に絡まり解けなくなった糸玉のような問題だが、日本社会の未来を考えたときに、いち早く是正が必要な澱と言える。
また、認知症患者についても同様だ。介護が長期化することで家族の負担が増すリスクもある。現役世代の介護離職が増えれば、経済全体への悪影響も避けられない。高齢化率は今後2040年には35%近くまで上昇すると予測されており、「限られた社会資源をどこに投入すべきか」という議論が避けられない状況になっている。
SNSでも「現役世代が支えきれなくなる前に制度設計をすべき」「負担が大きすぎて共倒れになってしまう」といった声が多く見られる。もはや「命は尊いから」という綺麗事では済まされない現実がある。
安楽死制度の導入は可能か? 臓器提供カードのような意思表示がカギに
カナダでは、安楽死の可否を決める際、医療従事者が慎重な議論を重ねる仕組みが整えられている。例えば、一部の病院では福祉専門家やカウンセラーを含むチームを設置し、患者や家族とともに最良の選択肢を探る。
日本でも、交通事故時の臓器提供意思カードのように、健康なうちに人生の終末について意思を示せる仕組みが求められているのではないか。これにより、突発的な自殺を防ぎ、本人の希望に沿った医療を提供できる可能性が高まる。
ただし、制度を運用する上での課題もある。カナダでは年間1万5000件以上の安楽死が実施されているが、審査機関が州によって異なり、基準にばらつきがあるとの指摘もある。こうした問題を避けるためには、日本でも医療や福祉の専門家による厳格な審査基準を設けることが不可欠だ。
「安楽死=是か非か」ではなく、どう運用すべきかを議論すべき時
日本が安楽死制度を導入するか否かの議論は今後も続くだろう。しかし重要なのは、「制度が必要かどうか」ではなく、「どのような仕組みならば適正に運用できるか」という視点だ。
SNSでは「カナダのように議論を深めてルールを作るべき」「先送りせずに、社会全体で最適な制度を考える必要がある」との意見も多い。日本が直面する高齢化と医療財政の課題を考えると、安楽死の是非を問うだけでなく、どのような仕組みを整えれば適切に機能するのか、具体的な議論を進める時が来ている。