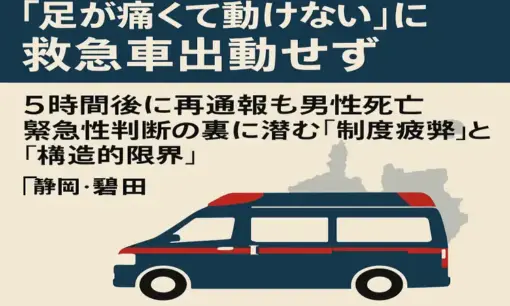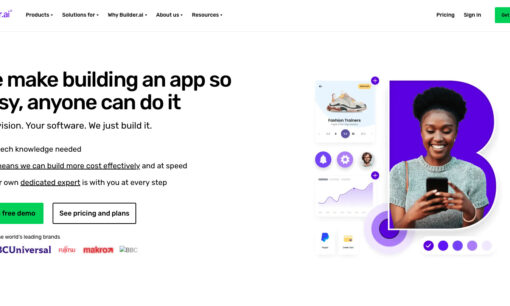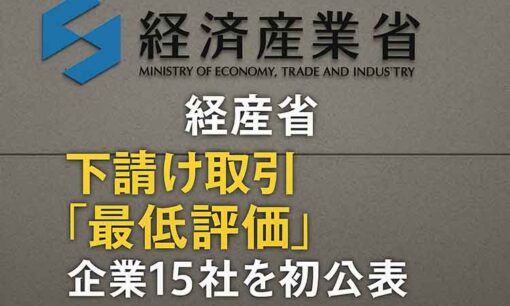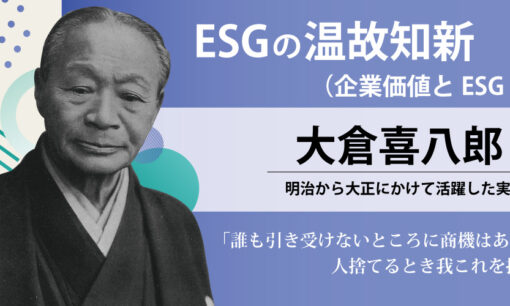スーパーの値札はひそやかに、しかし確実に上がり続け、家計は静かに悲鳴を上げている。そんな中、政府がまとめる新たな経済対策が明らかになった。
児童手当に「子ども1人2万円」を上乗せ給付する方針だ。
だが、物価高はすべての国民に等しくのしかかっている。なぜ子育て世帯だけが対象なのかという疑問や不満が、街のあちこちでざわつきのように響き始めている。
20兆円超の経済対策で何を救おうとしているのか
永田町の会議室では、夜遅くまで灯りが落ちない日が続いている。机には分厚い資料が積み上がり、予算と政策の綱引きが静かに、しかし熾烈に行われている。
今回の経済対策は、補正予算と減税を合わせて20兆円を超える規模になる見通しだ。物価高に苦しむ生活者を救う即効的な処方箋として位置づけられる。
しかし、その多くは新たな国債発行に頼る形となる。
短期的な支援の裏側で、将来世代にどれほどの負担を残すのか。今回の対策は、国の財政構造そのものに影を落とし始めている。
児童手当「子ども1人2万円」上乗せ給付の実像
今回もっとも注目を集めているのが、児童手当への一時的な上乗せだ。
0〜18歳の子どもをもつ家庭に対し、1人あたり2万円を追加で給付し、所得制限は設けないという。
給付は既存の児童手当と同じ口座に振り込まれるため、手続きは最小限で済むと見られる。一方で、子どもがすでに成人した家庭、あるいは子どもがいない世帯には恩恵がない。
街で話を聞くと、複雑な思いがにじむ。
ある女性は、大学生の子をもつ自分は対象外であり、これまでの増額タイミングにも一度も当たらなかったと語る。
別の男性は、産休や育休が整備されていなかった時代に子育てをし、税金を払い続けてきたにもかかわらず、「自分の世代には支援がほとんどなかった」と憤りを隠さない。
支援の必要性を感じている子育て世帯でさえ、「一度きりの2万円では将来の見通しまで明るくなるわけではない」と口を揃える。
おこめ券、電子クーポン、水道料金減免…
物価高対策の柱として位置づけられるのが、地方自治体が活用できる交付金だ。食料品の高騰を踏まえ、1人3000円相当のおこめ券や電子クーポンの配布、さらに水道料金の減免など、各自治体が自由に使える枠が設けられる。
しかし、地方に住む人々からは戸惑いの声も上がる。
ある住民は「券が使える店が限られており、結局ほとんど使えなかった」と振り返る。広い地域に店舗が少ない地方では、クーポン自体が実質使えない支援になるケースもあるのだ。
一方で、冬場の光熱費補助は家計にとって即効性がある。寒さの厳しい地域では、ただでさえ電気代が跳ね上がる。
一般家庭で合計7000円台に補助が引き上げられる見通しは、確かに一定の安心材料になる。
とはいえ、これらの対策はいずれも一時的。
生活の基盤そのものを変える力は持っていない。
即効的だが一時的 専門家が指摘する給付金政策の限界
経済対策の発表後、複数の専門家が口を揃えたのは「即効的だが一時的」という評価だった。
給付金やクーポンは、受け取った直後こそ消費を押し上げる。しかし、裏を返せば、効果が短期間で消えるということでもある。
物価高の背景には円安、賃金停滞、エネルギーの海外依存など、構造的な問題が横たわっており、そこに手が届かないままでは、家計の不安は解消されない。
さらに、子育て世帯への給付は、対象が全体の一部に限定されている。そのため景気刺激策としての広がりは小さく、物価高対策としても限定的になる。
ネット上に噴き上がる不公平感と取り残された世代
ネット上のコメント欄には、政策への賛否が渦巻いている。
ある投稿では、「物価高は全員にのしかかっているのに、なぜ特定の層だけ支援されるのか」と疑問を呈す声が寄せられた。
また、常に給付金の対象が「子育て世帯」と「非課税世帯」に偏ることに、長く働いて税金を納めてきた世代から不満が上がっている。
地方在住者からは、地域商品券の使い勝手に対する不満も多い。
利用できる店舗が限定され、実質的には「現金のほうがはるかに助かる」という切実な声もある。
一方で、子育て世帯からは感謝の言葉もある。だが、その多くは「ありがたい、しかし根本解決にはならない」というニュアンスを含んでいる。
世代間・地域間の温度差が、今回の政策によっていっそう浮き彫りになった。
一時金の連続から脱却するために必要な視点とは
今回の経済対策は、短期的な家計支援としての意味はある。
しかし、これを繰り返すだけでは、物価高に耐えうる経済構造は作れない。
必要なのは、賃金を持続的に押し上げる政策、円安を是正する金融・財政の見直し、社会保険料の負担軽減、エネルギー構造の改革、地方経済の底上げ。いずれも長い時間がかかるが、避けて通れない課題だ。
今だけ助かる政策から、“将来まで続く政策”へ。
今回の対策が、その転換点になるのかどうか。
物価高に揺れる国民は、その行方を固唾をのんで見つめている。