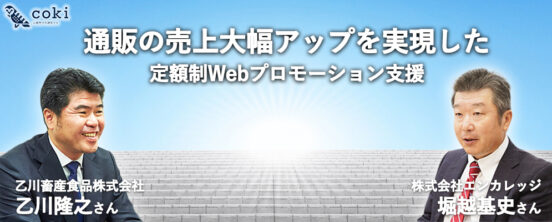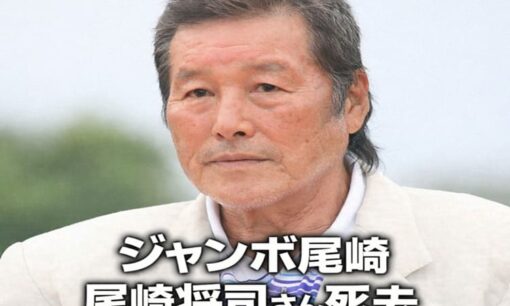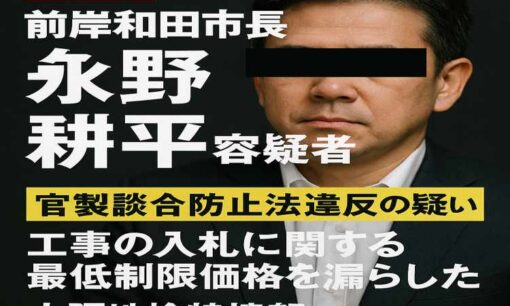八木橋パチの #ソーシャルグッド雑談、今回の雑談相手は、現在「人事のほけんしつ」というキャッチコピーで、障害者就労を多面的に支援しているシチロカ合同会社 ソーシャルデザイン事業部 代表の廣田 朱さんです。
まずは、福祉の世界へつながるきっかけを聞いてみました。
● 福祉の就職フェアで偶然選んだ入所施設の道が、人生を変えた。
● 「働きたい」その気持ちを消す権利なんて、一体誰にあるのか?
● 「もうここにはいられない」。正しいことをしたのに壊れる信頼
● 仮面をかぶり役割を演じる中で、自分が消えていきそうだった
● 定着させるのではなく、「ここで生きたい」を一緒に探す

廣田 朱(ひろた あや)
シチロカ合同会社 シチロカソーシャルデザイン代表
大学で社会福祉を専攻。知的障がい者の入所施設、就労継続支援B型施設にて生活から就労支援全般を経験。東京労働局の専門職「精神障害者雇用トータルサポーター」としてハローワークにて精神・発達障害の方のキャリア支援、企業の障がい者雇用促進支援に携わる。福祉サービスの設立(B型、自立訓練)や運営(B型)経験あり。【 資格 】社会福祉士、教員免許(特別支援学校 他)
(「シチロカについて – 人事のほけんしつ~産業ソーシャルワークサービス~ byシチロカ合同会社」より)
八木橋 パチ(やぎはし ぱち)
バンド活動、海外生活、フリーターを経て36歳で初めて就職。2008年日本IBMに入社し、社内コミュニティー・マネージャーおよびコラボレーション・ツールの展開・推進を担当。社内外で「#混ぜなきゃ危険」を合い言葉に、持続可能な未来の実現に取り組む組織や人たちとさまざまなコラボ活動を実践してきた。近年は「誇りある就労」をテーマに取材・発信している。
● 福祉の就職フェアで偶然選んだ福祉の道が、人生を変えた。

パチ
「障害者支援」がキャリアとなったのは偶然みたいなものだったって、なにかで目にしたんだけど。そうなの?

廣田
そうそう。大学生で、「まあ就職しないとなあ」って参加した福祉のお仕事就職フェアで、一番列が短かったブースに行ったの。そこがたまたま障がい者入所施設で。

パチ

廣田
行かなかった。なんとなく「あ、ここで雇ってもらえそうだな。じゃあここでいいや」って。

パチ
それはなかなかすごい話だね。でも、福祉に興味を持っていたから、福祉系の大学に通っていたんでしょ?

廣田
私ね、中高生のときは、JICAで青年海外協力隊のメンバーになりたいと思っていたの。それで海外に行って、支援活動に関わりたいと思ってたのよ。
そんな思いを中学校で先生に相談したら、「教員免許を持っていると、道がつながりやすいし広がりやすいよ」って言われて。
それで、教員免許を取れる大学受けて、受かったのが福祉の大学だった…。

パチ
海外協力隊かぁ、ちょっと意外。どこに行きたかったの?

廣田
あんまり具体的じゃなかったかも。アフリカのどこか、くらいの感じで。
その中学の先生ね、海外協力隊で活動した経験を持っていた人だったの。田舎の中学生にはとっては、その体験話はとても魅力的だったなぁ。わざわざ長崎の離島・対馬に赴任してくるところも変わっているよね。
私はその先生に自由を感じていたのね。やっぱり小さな島だし、少し排他的なところもあって、私も息苦しさを感じていたんだよね。
それで「外国で仕事っていいな~」+「私も困っている地域や国で、子どもたちを支えたい」と思うようになったの。

パチ
なるほどね。でも、なんだからこうして聞いていると「誰かを支援したい」とか「伴走したい」とか、当時からそういうところに意識が向いていたのかもね。
 高校生となり、対馬を離れて福岡へと向かう廣田さん。メチャ嬉しそう!
高校生となり、対馬を離れて福岡へと向かう廣田さん。メチャ嬉しそう!
この後、話は脱線して私パチが読み終えたばかりだったベストセラー『対馬の海に沈む』に。廣田さんが幼少期を過ごした人口3万人ほどの離島・対馬を舞台にしたノンフィクション作品です。
JA対馬の地域ぐるみの大がかりな不正も衝撃的ですが、おれ的には、粘り強い調査で事実を探り続ける著者の姿がとても印象的でした(って、ここでも脱線してしまいました(笑))。 |
● 「働きたい」その気持ちを消す権利なんて、一体誰にあるのか?

パチ

廣田
福岡のすごい田舎の山の中にある知的障がい者の入所施設だったの。
入所施設なので、「日常生活における支援」が日々の中心で、「働く」と言ってもお金をいただくような作業とかじゃなく、日中の活動の一環で、みんなで畑やったり陶芸やったりって感じで。
でも、あるとき「僕は外で働きたい。仕事をしたい」って利用者さんが現れたの。

パチ
ふむ。そうだよね。障がいの有無に関わらず「働いてお金をもらいたい。好きなことに使いたい」って思う人はいるわな。

廣田
でも、その社会福祉法人のスタッフの間では、その声にどう応えるかが大課題になったのよ。
「変に夢を見させるな」って言う職員も結構いて、「傷つくのは本人だぞ。ご家族だぞ」なんて声もあってね。
でもね、私は「働きたいって気持ちを止めさせる権利なんて、周りにあるのかな? 彼にだって、失敗する権利だって傷つく権利だってあるはず」って思ったのよ。
それで、その彼と「そうだよね。働きたいよね。よし、じゃあ仕事を見つけよう」って一緒に活動をしたの。新聞の折込求人広告なんかを一緒に見ながら、「これはどうだろう。こっちはどうかな?」って。

パチ
へ〜。いいじゃない。彼にとっても仲間ができた感じだね、きっと。

廣田
それで、そうしている間に彼はどんどん変化していって。「一体これはなに? 人ってこんなに変わるものなのか!」って私びっくりしちゃって。
だって、それまでは昼夜を問わず施設を脱走したり、ちょっと口には出しづらい残酷な行為を通じて意思や感情を表現したりする人だったんだよ。
それが、私と一緒のときは、他の職員と一緒のときに見せる姿とは違うようになって。私が宿直当番の日は、逃げるようなことも悪さをすることもなくなって。
そのうちに、じょじょにだけれど、落ち着いて穏やかに暮らせる時間も増えていったの。

パチ
それはすごい体験だね。人がそんなふうに変化していく姿を間近で目にするだけでもものすごいことなのに、それに自分がガッチリと関われるなんて。
教師でも海外協力隊でも、経験できない人の方が多いかもしれないよ。
もちろん大変なところもたくさんあるであろうことはわかっているつもりだけど…でも、やっぱりとてもステキな仕事だね。

廣田
うん。私もそう思う。
…あの事件がなかったら、もしかしたら今もそのまま働いていたかもね…。
 青年海外協力隊に憧れていた高校時代の廣田さん
青年海外協力隊に憧れていた高校時代の廣田さん
この後、かなりショッキングな話を聞きました。
廣田さんはとある事実を知り、悩んだ末にその事実を明らかにすることを選びました。そして結果として、廣田さんは8年間勤めたその福祉法人を退職することとなります。
何事もなかったかのように過ごすことを選ぶ人もいるのでしょう。とりわけ、組織の中にいると、波風を立てることを恐れ、善悪の境から目を背けるようになる人も少なくはないですから。 |
● 「もうここにはいられない」。正しいことをしたのに壊れる信頼

廣田
不正を見つけちゃったの。自分の上司が利用者さんのお金を横領していた。
「こういうときどうしたらいいの? まずはこっそり本人に言うべき? それとも警察に言うべき!?」って、私ちょっとパニックになって。
それで父に相談したら、「正しいことをしなさい」って言われたんだけど、でも「それじゃあ正しいことって何だろう」と悩みました。

パチ

廣田
結局、別の上司に相談して事実を明らかにしたの。
法人が実態調査を行ったんだけど、最初に見込まれていたものよりも金額も遥かに大きくて。でも結局は、弁償で済まされることになったの。
それで、被害に遭った利用者さんのご自宅へ謝罪に行くことになったんだけど、なぜか、親御さんを前に私も加害者である上司の隣に座らされて。それで責任者に「謝りなさい」って言われて…。

パチ
ええ! 廣田さんも謝るの? …まあでも、先方から見たら同じ施設にいる「責任者側」の人か。

廣田
でもそれよりショックだったのは、後で分かったことだけど、どうやら一部の職員には私もグルだと思われていたみたいなの。
釈然としない気持ちだけが残って。組織や同僚への信頼も揺らいで「もうここでは働けないな」って。

パチ

廣田
「お金のことより、今後も施設にいてくれる方が大事だから、大ごとにしないで」って言われたの。
その家にとっては、知的障がいの家族が誰かに面倒を見てもらいながら、自分たちとは離れた場所で暮らせることこそが大事だったみたいで…。
私は「正しさを貫けば解決へとつながる」と思っていたけど、現実はそんなに単純じゃなかった。真実を明かすことでみんなに疎んじられることがあるなんて…。そんなこと、考えたこともなかった。
「正しいこと」ってなんなんですかね。いまもわからないです。

パチ
今の話って、すごく切ない話だよ。
…切ないっていうのは、まずはもちろん廣田さんにとって。でもそれだけじゃなくて。そのご家族にとっても、ご家族を取り巻く社会や、入所施設にとっても。
正しさを追っても、やりきれない気持ちや、底にあるやるせなさからは逃れられない…。

廣田
そう言われると、本当にそうだね…。
ちょっと私、泣きそうだよ。これまでこの話、そんなふうに捉えたことなかったな。
 雑談は、廣田さんの以前の職場からすぐ近くの札の辻スクエア4階にある福祉喫茶「みなと茶寮」で。
雑談は、廣田さんの以前の職場からすぐ近くの札の辻スクエア4階にある福祉喫茶「みなと茶寮」で。
社会福祉法人を退職後、廣田さんは東京へ。
就労継続支援B型事業所の立ち上げ、新しい就労支援ビジネスの構想、ビジコン参加、産休・育休、そして東京労働局の「精神障害者雇用トータルサポーター」として2022年までの8年間、ハローワークで専門職として働きました。
支援を必要とする人と企業の間に立ち続ける中で、廣田さんは次第に違和感を強めていきます。 |
● 仮面をかぶり役割を演じる中で、自分が消えていきそうだった

パチ

廣田
いつの間にか、「ハローワークの廣田さん」としての言葉が、自分を縛ってしまうようになってしまっていたのね。
困っている利用者さんを前にしても、「それ、ひどい会社だね。辞めちゃいなよ」とは言えない。
組織に所属していると、どうしても言っていいことと言ってはいけないことがあるじゃない? ハローワークは行政機関だから、特にね。
それが重なっていくうちに、「私、本当にこの人と向き合えているのかな?」って、「本当の時間を過ごせているのかな」って、空虚さが膨らんでいったの。

パチ
うん。わかる。おれもちょっと近い感覚を持つことがあるよ。
「こんなことを重ねていたら、いつか本当の自分が消え去ってしまうんじゃないか…」って恐くなる。

廣田
最後の1〜2年は辛かったなぁ。どんどん「立場の言葉」が増えていって、本当に仮面をかぶって役割を演じている感覚が強くなって…。「一体これは誰のためになっているんだろう?」と思いながら働いてたな。
組織としてのハローワークの役割は理解してたけど、私が変わってしまったのね。自分の在り方とは大きくズレてしまったのよね。

パチ
それはもう潮時だね。どうしても辞められない状況にいるのでなければ、利用される方のためにも、組織のためにも、そして何よりも自分自身のために辞めた方がいい。

廣田
うん。それでそこから少しずつ「自分がやりたいことを事業としてやろう」って動き始めたの。
「こうしたら喜んでもらえる」「ありがたいと思ってくれる人がいる」という感覚を信じて、実行に移していったって感じかな。
それが形になって「人事のほけんしつ」っていうコンセプトが生まれて、「シチロカ合同会社 ソーシャルデザイン事業部」を本格的にスタートしたの。

パチ
クライアントは企業だよね。廣田さん的には今は「就労希望者の支援」との間にズレは感じないの?

廣田
感じないなあ。本人の可能性が花開くと、結果的に組織も良くなって、クライアントである企業にもすごく喜んでもらえることが多いから。
でもね、それは私にとってはオマケみたいなものかな。私にとっては、「人が持っている可能性や輝きを、もっと発露させたい」という純粋な欲求が満たされることがなによりも嬉しいの。
昨日も、結構大変な「こじらせている人」との面談で、結局今朝までやりとりしていたんだけど、結果的にその人の行動変化が生まれて、本人の喜びと周囲の喜びにつながった。もちろん、私の喜びにも。
…って、ここまで到達するのはすごく難しくて、ヘトヘトになる毎日だけどね。(笑)。
● 定着させるのではなく、「ここで生きたい」を一緒に探す

パチ
「こじらせてる人」って表現、ちょっとわかる。でも何がそうさせてしまうんだろう?

廣田
これまでの障がい者雇用の現場経験から思うんだけど、多くの人が、「自分が大事にしているものを、周りに大切にされていない」と感じているんじゃないかな。
私ね、以前は「どうすればこの人がうまく今の仕事に定着できるだろう」って考えて話を聞いていたの。でも今は「この人は何を大切にしてほしいと感じているのか」って、それに耳を澄まして聞くようになった。
そうしたら、どんどん変化が起きるようになってきたの。私の聞く姿勢が間違っていたのね。

パチ

廣田
私は、「私を認めて! 私を認めて!」って言葉を全面的に受け止めて、まずは徹底的に聴き切るの。
そのうえで、「でも仕事には約束事があるよね。それを踏まえながら、お互いを認め合えるようになるにはどうしたらいいだろうね?」って、可能性を拡げていけるように一緒に探求をしていくだけなの。
そうすると、それまで必死にその仕事にしがみつこうとしていた人が「…ここは、私の居場所じゃないかもしれない」って自分で考えて言い出すようになって。
私も「そうかもしれないね。じゃあ何ができそうだろうか。どんな場所ならいいだろうか」って。

パチ
そうやって見つめていったら、自分に必要なものと、それに対して何ができるかってことに意識が向かっていき、結果的に「退職」は先のことになりそう。

廣田
そうなのよパチさん! 私の中には「定着させる」って発想はもはやないの。
「ここで生きたい」と思える場所を本人が見つけることがゴール。そうやって本人が変わると、組織も変わっていく。結果が定着という形になるの。
私の役割は、「大事にしてほしい」という声を解放すること。そして「ここで生きたい」と思える場所につなげること。それが最高におもしろいの。

パチ
最後の質問を。廣田さんにとって「誇りある就労」とは?

廣田
それね…う〜ん。考えてなかったな(笑)。難しいな。
私にとっての「誇りある就労」は、ピカピカした成功じゃなくて、もっと泥臭く、挫折や葛藤を抱えながら、自分なりの答えを見つけていくこと…だな。そうやって働くからこそ、働くことに誇りが宿るんだと思う。
支援って、ともすればコントロールになってしまいかねないんだよね。「会社に行かせること」が目的になってしまえば、それはただの強制だから。
大事なのは、「理解することを諦めない姿勢」。それが、私にとっての「誇りある就労」の根っこかな。
「パチさん、あれだ。今私、すごくいいことを言ったような気がしたけど、よく考えたらこの『理解することを諦めない姿勢』って、私が大好きなマンガ『進撃の巨人』の調査兵団が掲げている言葉だったね。」
——とのこと。おれ、長い話ってマンガでも苦手で、『進撃の巨人』も10巻くらいで止めちゃったんだよね…。
でも、考えてみれば、この日の廣田さんとの雑談は、最初から「諦めることなく粘り強く真実を理解しようとし続ける」人の話だったんだな。よし! 誰か一週間くらい全冊貸してくれませんか?
(そして貸してくれるあなた、次回の#ソーシャルグッド雑談のお相手になるのはいかが?) |