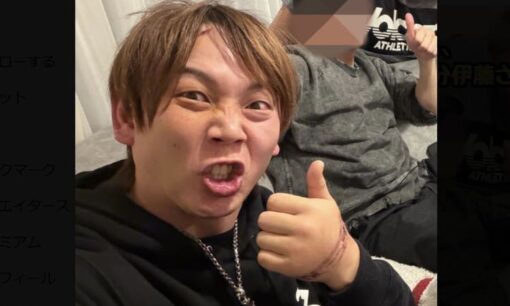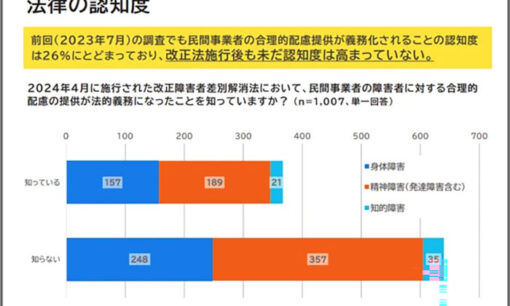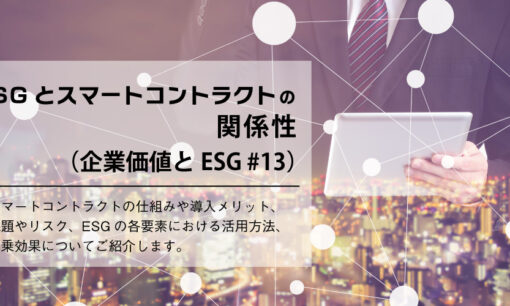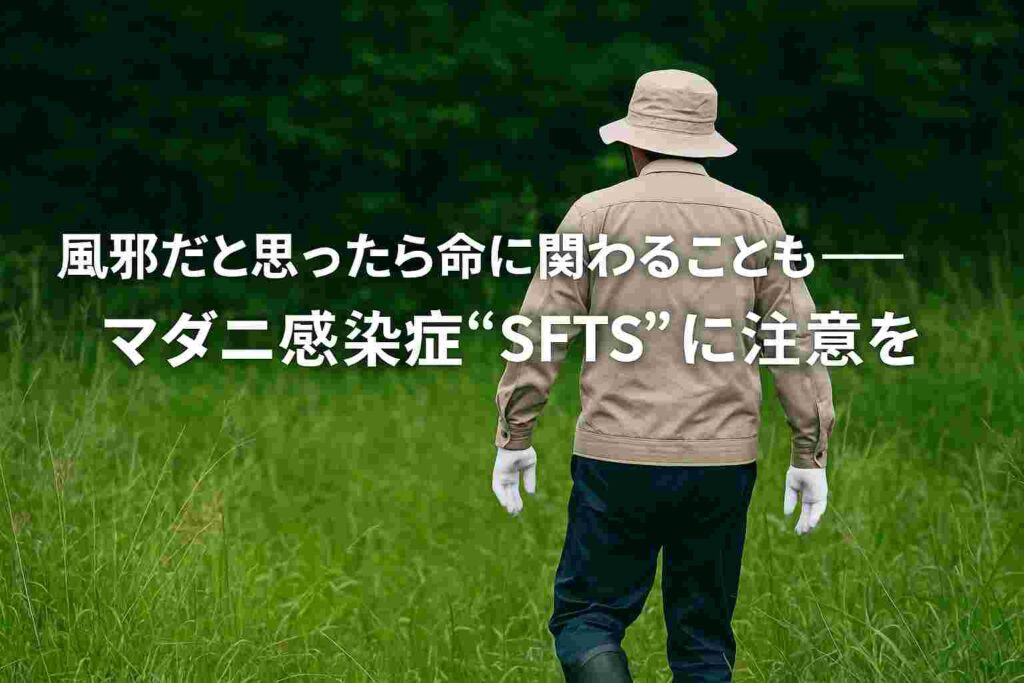
夏になると、草刈りやガーデニングといった屋外作業、キャンプなど行楽の機会が増える。自然と触れ合うこうした時間は、心を整える癒しのひとときだ。しかし、その背後に、命を脅かす感染症が潜んでいるとしたらどうだろう。
近年、「風邪と診断されたが、実は違った」というケースで亡くなる人が相次いでいる。原因はマダニによる感染症、「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」である。小さな虫のひと刺しが、大きな命の危機につながる。
初期症状は風邪そっくり。見逃しが命取りに
SFTSは、マダニに刺されることで感染するウイルス性の病気だ。発熱、倦怠感、頭痛、吐き気など、いわゆる“風邪のような”症状から始まることが多い。そのため、本人も医師も風邪と判断してしまうことが少なくない。
しかし数日経つと、血小板の減少による出血、意識障害、内臓機能の低下など、命に関わる重い症状へと進行することがある。特に高齢者や基礎疾患のある人は重症化しやすく、致死率は1〜3割にのぼるとされている。
7月には、草むらで除草作業をしていた愛知県の50代女性や、静岡県の80代男性がSFTSで亡くなった。他にも香川県、宮崎県などでも死者が出ており、感染の広がりは決して一部地域の話ではない。
マダニはどこにでも潜んでいる
「山奥に行かなければ大丈夫」と考えるのは危険だ。マダニは、庭先の草むらや公園、河原など、日常生活のすぐそばに潜んでいる。特に春から秋にかけて活発に動き、背の高い草の裏側で動物や人が通るのをじっと待っているのだ。
しかもその大きさは1〜3ミリと非常に小さく、服や皮膚に付いていても気づかないことが多い。愛知県の調査では、白い布を草にこすっただけで複数のマダニが付着したという報告もある。見えない敵との闘いには、まず「存在を疑う」ことが重要だ。
予防の基本は「覆う」「防ぐ」「落とす」
マダニ対策でまず実践したいのが、肌を出さない服装だ。長袖・長ズボンを基本に、首元や手首、足首もできるだけ覆う。帽子や手袋も効果的である。草むらに入る際は、防虫スプレーを使うことも忘れてはならない。
作業後はすぐに着替え、シャワーを浴びる。髪の毛や耳の裏、関節の裏側など、マダニが潜みやすい部位は特に入念にチェックしたい。
また、ペットにマダニが付着して家に持ち込まれる例もある。外で遊んだ犬や猫にも注意が必要だ。
刺されたときの対処と、受診のポイント
マダニに刺された場合、自分で無理に引き抜くのは危険である。口器だけが皮膚に残ると、感染リスクが高まる。ピンセットで丁寧に取り除くか、可能であれば病院で処置してもらうのが望ましい。
そしてもっとも重要なのが、体調を崩したときの「自己申告」だ。
「数日前に山や草むらに入った」「虫に刺されたような痕がある」といった情報を、受診時にきちんと医師に伝えることが命を守る鍵になる。
SFTSのような感染症は、医師側にも認識がなければ“ただの風邪”と見逃されやすい。些細な違和感でも、医療の現場では大きなヒントとなる。
命を守るために、知識を共有しよう
SFTSは、まだ広く知られていない感染症である。だが、対策と注意で防げる病気でもある。
屋外作業が多い高齢者、農作業が趣味の人、ペットと散歩する人など、感染リスクが高い環境にいる人には特に注意が必要だ。家族内での声かけや、地域での情報共有が、被害を減らす大きな力になる。
「風邪かと思ったけど違った」と気づくことが、命を救うことにつながる。
自然と上手に付き合うためにも、マダニのリスクを正しく理解し、身近な危険として備えておきたい。