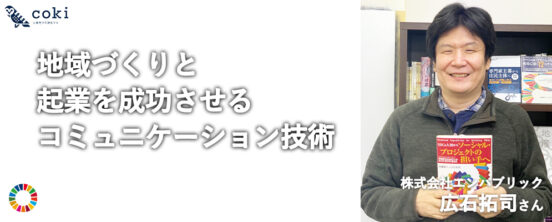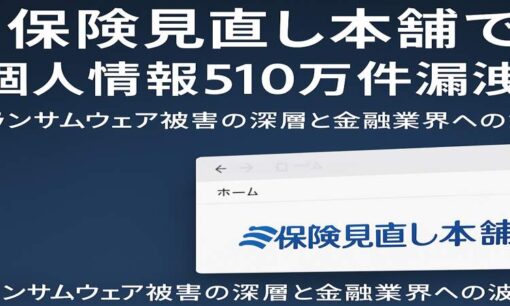真夏の通勤、すでに駅に着いた時点で汗だく。環境省が「熱中症警戒アラート」を連日発表するなか、一部企業が“猛暑日は出社免除”という新たな働き方を模索し始めている。
「熱中症より上司の目が怖い」といった皮肉も聞こえる今、出社文化と柔軟な働き方のはざまで揺れる企業とビジネスパーソン。命を守る働き方改革は、どこまで進んでいるのか。
猛暑日は“外出自粛”なのに、出社は当たり前?
連日の猛暑日。35度を超える炎天下のなかで、スーツ姿のビジネスマンが駅まで歩き、満員電車で会社に向かう。そんな日常に、違和感を覚える人が増えている。
気象庁と環境省が発表する「熱中症警戒アラート」では、「高齢者でなくても外出を控えるべき」とされるほどの危険な暑さが警告されている。だが、その対象には“会社員の出勤”は含まれていない。
エアコンの効いたオフィスが待っているとしても、通勤途中で倒れるケースは後を絶たない。特に遠距離通勤者や自転車通勤者、高齢社員にとっては深刻な問題だ。
“働き方改革”が叫ばれて久しいが、猛暑日における出社リスクへの対応は、企業によって大きく温度差がある。
導入進む「暑さ対策リモート」の実情
こうしたなか、「猛暑日リモートワーク」を導入する企業が現れている。IT系企業、広告代理店、外資系企業などを中心に、前日18時の気温予測が35度以上の場合に、出社を免除する制度が採用されている。
制度の対象は、在宅勤務環境が整っており、業務遂行に支障のない職種に限定されるが、熱中症リスクの軽減という観点からの取り組みとして注目されている。
ある都内のIT企業では、7月のうち5日間が“猛暑日リモート”となった。人事担当者は「社員の健康を守ることが、結果的に生産性向上にもつながる」と話す。
メールやチャットでの業務が中心の部署では、業務効率にほぼ影響はなく、「暑さを気にせず集中できる」という社員の声もあるという。
採用・定着・評価…リモート導入の“もうひとつの狙い”
単なる福利厚生ではない。猛暑リモートの導入は、企業のブランディングや人材戦略にも直結している。
求職者の多くが、企業選びの基準として「柔軟な働き方ができるか」を重視しており、特に育児・介護中の社員や、健康面を意識する中堅社員にとっては、重要な選択材料となる。
「熱中症対策でリモート可」という制度そのものが、会社の“社員ファースト”な姿勢を示すPRにもなっている。実際、採用面接の場で「働きやすそうですね」という反応が増えたという事例もある。
また、猛暑日を契機に、災害時や交通トラブル時にも業務を止めない「BCP(事業継続計画)」の一環として捉える動きもある。今や“柔軟な働き方”は、企業の危機管理力そのものだ。
それでも“出社”が求められる現実
とはいえ、すべての企業が柔軟な対応をしているわけではない。「紙の書類が必要」「ハンコ文化が残っている」「上司がリモートを信用していない」…こうした“昭和的な出社原理”は今も根強い。
また、社内でも制度導入の不平等が摩擦を生む。「営業部はOKで、総務部はダメなのか」「若手は在宅で、部長は出社しろというのは理不尽だ」。公平性の欠如が、逆に不満や分断を生むリスクもある。
さらに、「オフィスのほうが快適だから出社したい」という意見もあり、リモートと出社の“選択の自由”をどう設計するかは、今後の大きな課題となる。
命を守る働き方改革は、誰のためにあるのか
「仕事のために体を壊す」
そんな矛盾が、猛暑という極端な気候の中であらわになっている。
通勤で汗をかき、出社してようやく体を冷やし、午後には疲れが蓄積……。それは、本当に“成果につながる働き方”なのか。
働き方改革とは、本来「生産性を上げる」「多様な働き方を認める」ものであるはずだ。だが実際は「見えること=働いている」という発想が根強く、“リモート=さぼっている”という誤解も残っている。
命を守るという観点から、「猛暑リモート」は単なるトレンドではなく、企業の姿勢を映し出す鏡といえる。
社員が“暑さに耐える力”ではなく、“自分を守る判断”をできる自由。それを認めるかどうかは、今後の企業価値にも直結するだろう。