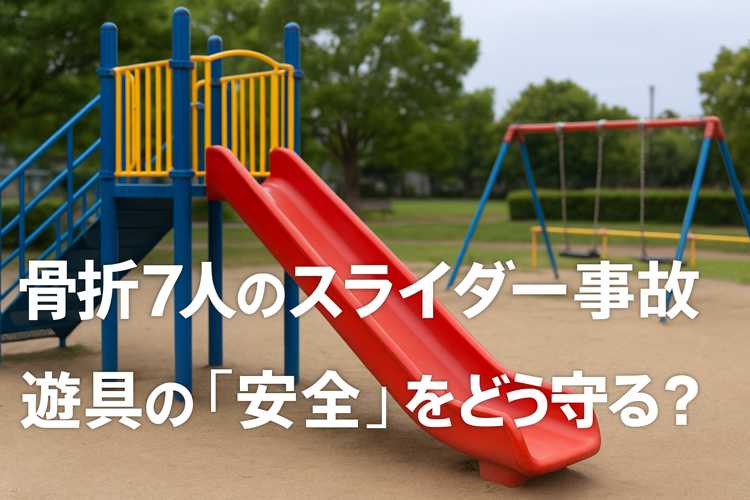
北九州市の皿倉山に設置されたばかりのロングスライダーで、骨折などの重傷者が相次いでいる。設置からわずか2カ月余りで、計7人が骨折。7月2日には新たに60代男性や50代女性ら3人からの申し出が市に寄せられたという。
対象年齢は6〜12歳。だが、現実には観光地という場の性質上、年齢制限を超えて大人も多く滑っていた。設計上のスピードや衝撃の緩衝性が「大人の体重」や「着地の勢い」に耐え得るものだったのか。そこに検証の余地があるのは言うまでもない。
市は6月上旬に利用を停止し、再開に向けて「注意喚起のあり方を見直す」としているが、果たしてそれだけで足りるのだろうか。
「新しさ」は安全の証ではない
今回の事故で注目すべきは、事故の舞台が「新設遊具」だった点だ。老朽化ではない。設計やルールの伝え方、そして利用者の想定のズレが事故を招いた。
私たちは、どこかで「新しい=安全」という錯覚に陥っていないだろうか。実際には、新設遊具であっても、その設計思想と現場の運用、利用者の行動が噛み合わなければ事故は起こりうる。そのリスクは「見えにくい」ゆえに、より深刻だ。
皿倉山の事故は、「安全」は設備の新旧だけでは決まらないことを私たちに突きつけている。
全国で繰り返される「遊具事故」
遊具による事故は皿倉山に限った話ではない。
たとえば東京都では、すべり台に子どもの服が引っかかり、首を圧迫する事故が発生。山形県では腐食したブランコが崩落し、幼児が打撲した。埼玉県ではジャングルジムからの転落により骨折した子どももいる。
こうした事故を受け、各自治体は補修の強化や設置基準の見直しを進めている。だが、すべての遊具に目が届いているとは言い難い。とくに地方の小規模公園では、定期点検が形式的に行われていたり、点検後の対応が後回しにされることも少なくない。
子どもが命を預ける場所であるにもかかわらず、遊具というインフラの多くは“無言で朽ちている”のが現実だ。
「安全基準」はどう整備されてきたか
2002年、国土交通省と日本公園施設業協会(JPFA)は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」を初めて策定した。欧州に比べて四半世紀遅れでのスタートだった。
その後、2014年と2024年に改訂され、最新版では複合遊具やインクルーシブデザインなどにも対応。設置から撤去までの全ライフサイクルを意識した内容となっている。地面の衝撃吸収素材の基準や、木材部材のJAS認証制度なども整備された。
だが、制度がいかに整っても、それを活かすのは現場だ。点検項目の“見落とし”や“形式的運用”は、法整備だけでは防ぎきれない。利用者との接点において、安全が「伝わる」ことが問われている。
「観光遊具」のリスクと責任
皿倉山のスライダーは観光地に設けられた。だからこそ、大人の利用を含めた想定がなされるべきだった。昨今、地方創生や観光施策の一環として、大人も楽しめるような“体験型遊具”が増加している。巨大なローラーすべり台、空中ネット、バンジートランポリン……子どもだけの遊び場ではなくなっている。
そうした施設こそ、設計段階から多様な体格・運動能力をもつ利用者の動きを想定しなければならない。滑る角度、着地の衝撃、滑走速度など、すべてが年齢や体重によって変わる。想定外の行動があっても事故を起こさない「許容設計」が必要だ。
そして何より重要なのは、「対象年齢6~12歳」という掲示だけでは“伝わらない”という事実である。
安全は、誰が守るのか
ここで問いたいのは、「安全とは誰が守るのか」という根本的な問題だ。
設置者に求められるのは、事故の起こり得る条件を想定し、そのリスクを低減する設計とルール作りだ。そして、利用者に求められるのは、ルールを「守る」という姿勢だ。安全は、管理者と利用者の協働によって初めて成立する。
だが、現実には「滑るなと言われなかったから滑った」「自分は大丈夫だと思った」「知らなかった」という声もある。個人の判断に委ねられる場面があまりに多い。
それでもなお、私たちは遊具を残さねばならない。なぜなら、遊具は子どもにとって“育ちの装置”だからだ。全身を使って登り、滑り、落ちるなかで、バランス感覚とリスクへの理解が育まれていく。だからこそ、「安全に遊べる」環境は社会が整えるべき基盤である。
見えないリスクとどう向き合うか
「壊れていないから大丈夫」その感覚はもはや通用しない。
事故は、壊れたときではなく、“壊れかけ”のときに起きる。滑りすぎる、止まりすぎる、着地しすぎるなど、そうした違和感は、設計と現場の接続不全の表れである。
今回の皿倉山の事故を受けて、北九州市は再開前にルールの周知や設計の見直しを図るという。それは歓迎すべき姿勢だ。しかしそれ以上に、全国の遊具を抱える自治体が「自分たちの公園は大丈夫か」と問い直す契機にしてほしい。
安全とは、目に見える看板や柵ではない。そこに関わる人々の想像力と、行動の積み重ねこそが、子どもたちを守る本当の「装置」なのだから。
















