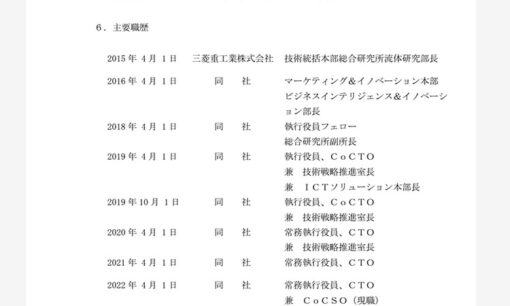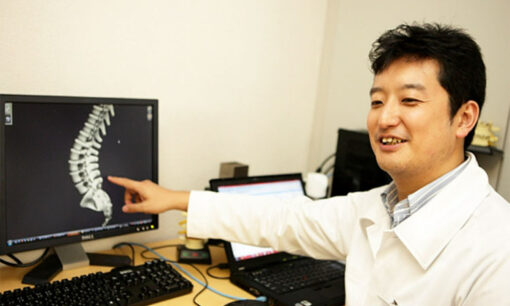オフィスチェアで検索すると必ず出てくる商品がある。背もたれと、座席のクッションがメッシュの椅子だ。ハンモックの様に優しく包みこまれるような着座感は長い時間デスクワークをしていても疲れにくい。そのような、今では当たり前のように販売されている商品も、日本で誕生したのは2000年に入ってからのこと。
「一期一会のモノづくりで世界を変える!」を理念に、愛知県に本社と工場を持つ株式会社ノーリツイス(販社)と東海金属工業株式会社(製造)。1947年に創業し、理髪店の椅子づくりから始まったこの会社は、ひょんなことから、それまで日本になかった背と座がメッシュのオフィスチェアづくりに挑戦することになる。
目の前に立ちはだかる数々の困難を乗り越え、約9年の歳月を経て完成した商品『SF』。そして、SFに改良を重ねて生まれた『SFR』。その誕生秘話をノーリツイス及び東海金属工業の青木照護社長、同社前開発部長で現在顧問の橋本さん、開発部長の丸山さんに伺った。
入社間もない社員の行動から、まさかの製品開発本格化
はじまりは1994年。ドイツで開催された世界最大規模のオフィス家具国際見本市・オルガテックで、アメリカのハーマンミラー社が発表したアーロンチェアを目にしたことに起因する。
世界中のオフィス家具メーカーに衝撃を与えたアーロンチェアは、世界で初めて背と座席のクッションにメッシュを採用したオフィスチェア。ニューヨーク近代美術館(MoMA)のパーマネントコレクション(永久収蔵品)に選定され、いまやオフィス家具チェア業界のレジェンドとも称される製品である。
当時、日本からも多くのオフィス家具メーカーがオルガテックを訪れ、アーロンチェアを目の当たりにして、「これはすごい!」と業界内で話題になっていた。
その頃、ノーリツイスと東海金属の社長を務めていた現在の相談役である青木慶喜さんは、開発畑出身ということもあり、アーロンチェアを目にしてから、背と座がメッシュの椅子の研究開発に着手。しかし、製品化までには至らず、設計もできていない状態が約6年続いた。
そこに、結果的に一石を投じることになる社員が登場する。現在、開発部長の丸山さんだ。
「私が入社した時には、すでに背座メッシュの椅子の開発が行われていましたが、製品化までには至っておりませんでした。入社のご挨拶がてら、あるお客様に開発中の商品についてアナウンスさせてもらったんです。そしたら、『 いいですね。是非、採用しましょう。』と言われまして。ところが、会社に戻り、受注に結びついたことを報告すると、『えっ!どうするんだ』という反応でした」と丸山さんは笑う。
「お客さんを先に見つけて来い」といった張本人の当時社長の相談役のことを、照護社長は振り返る。

その当時に開発部長をしていた現在の顧問橋本さんは語る。
「相談役も、怒った態度はとられていましたが、内心は『やってやるぞ!』と気概を持っていたと思いますよ」。
ナイナイづくしで始まった、前代未聞の製品開発

入社間もない社員による受注から始まった前代未聞の製品開発は、始まってすぐに大きな問題に直面した。製品の肝ともいえるメッシュ素材が見つからなかったのだ。
「メッシュを作る特殊な糸と、それを織ること自体、当時の日本でやっているメーカーはありませんでした」と丸山さん。海外製品の輸入商社や販売業者探し続け、ようやく輸入可能な専門商社と出会い、素材は入手できることになった。これで製品化に拍車がかかる!と思いきや、まだまだ問題は山積みだった。
メッシュの素材は入手できても、それを使ってどうやって椅子を作るのか、歴史ある椅子メーカーのノウハウを持ってしても、難問だったのだ。橋本さんと丸山さんは当時の開発について、以下のように語る。
「人が座った時に椅子が受ける負荷荷重は体重の数倍も想定しなくてはなりません。背もたれと座席にメッシュを支える枠をまず作り、様々な方法でメッシュを固定しようとトライしましたが、座った時の衝撃は、相当なもので、何をやってもメッシュが緩むんですよ」
「いろいろやってみて、アーロンチェアの作り方が一番画期的で理にかなっている優れたものであることはわかりました。でも、それは国際特許が取得されていて使えない。だからどうしても独自に考えないとダメでした」
世界のトップメーカーが辿りついた方法とは別のやり方を探す日々。確かにこれは無謀な挑戦だったのかもしれない。しかし、苦労の末、その方法を見出すことになる。「背もたれと座席の枠にメッシュを一体で成形してみようということになりました」、そう語るのは丸山さん。
しかし、エビデンスもなく、それが正解なのかはわからない。
「最終的に、開発に携わってくれていた相談役が腹を決めて、『これでいこう!』と言ってもらえたので、私たちにとっては、すごくありがたかったです」と、橋本さんはしみじみと感謝の言葉を述べた。
製品の作り方が決まったが、まだまだ問題は残っていた。製品を作るための部品を作る所がなかったのだ。作りたいのは、日本にそれまでにない椅子。それゆえに、そのような椅子の部品を作ったことのある製造業者は日本では存在していなかった。また今度は金型をどう作るかの試行錯誤が始まる。
「日頃からおつきあいのあったサプライヤーさんに相談しました。まったく新しいチャレンジだったので、『これでいけるかな?これはどうだろう』と、サプライヤーさんと相談しながら手探りで進めていきました」(丸山さん)
「大手でない弊社が自社独自でできたのは、近くに地元のサプライヤーさんがあったからです。私たちの想いに意気投合してくださり、互いに行ったり来たりしながら、トライアンドエラーを重ねましたね」(橋本さん)
メッシュ素材やその取り付け方、金型や部品づくりと、苦労しながら難しい問題を解決していく日々。
「アーロン並みの製品を完成させたい!」という想い。それにはもう一つ、クリアにしなければならないことがあった。ロッキングというオフィスワークチェアには必要不可欠な機能だ。
「椅子に座った時に、体の動きや体重のかけ方にあわせて、椅子の背もたれが追随して体を支える。アーロンチェアのロッキング機能は衝撃的でしたね。椅子の構造自体を変えなければできないことで、弊社には前例のないことだったんです。この機能を完成させるのは、それはもうかなりな苦労の連続でした」、橋本さんの口ぶりから当時の苦労がうかがえる。
真似られているのにニコニコする、開発した製品が認めらえたと実感した出来事。
1994年に開発を始め、立ちはだかる問題を諦めずに解決し続けて、ようやく2002年に、背座メッシュの製品『SF』の販売に至った。これでようやく開発が終わった。
そう思っていたが違った。ロッキング機能の角度や背の戻り方に対して、当時の社長の青木慶喜相談役に「納得いかない」と言われたのだ。丸山さんによれば「背の戻り方などについて、相談役は常日頃から品位と表現され、当時のSFについて『品位がない』と言われていました」とのこと。製品に対する並々ならぬこだわりを感じるエピソードである。
それから5年かけて、仕様変更を行い、品位のある椅子にリニューアルした。さらに製品に対する研鑽を重ね、ニーズにも応えながら、2018年にはデザインを含めてリニューアルし、販売したのが現在のモデル『SFR』である。

ノーリツイスと東海金属は、対企業向けに製品を製造することをメインとするメーカーである。
そのため、エンドユーザーの反応を直接聞く機会はないが、製品完成時に、できあがった『SF』の価値を実感する出来事があった。発注してくれた企業が、「これは素晴らしい!」と感激し、自社ブランドとして販売したい!と言われたのだ。
もう一つ、印象的な出来事がある。SFを発売してから数年後、青木社長やその頃の担当者が、海外のオフィス家具展示会に行った時のことだ。会場には聞いたことのない中国のメーカーが出展していて、そのブースにめがけて当時の担当者が走って行った。担当者の視線の先には、SFと全く同じ形状の椅子があった。
「ここも一緒だ!ここも一緒だ!」と製品を覗き込んで確認する担当者。どうやらそのメーカーは、SFを購入し、分解して金型を作り、中国で製品化していたのだった。
「その話を聞いて、すごくうれしかったですね。社内のみんなも『何やってんだ』って言いながら、とってもニコニコしていましたよ(笑)」、そう言う丸山さんもニコニコしている。
「うちみたいな小さな会社の製品が中国に真似られるとは(笑)。悔しさもあるけど、うれしさの方が強い出来事でしたね。ただ、その椅子に座ってみたらメッシュがフニャフニャで、とても座れる代物ではありませんでした。
じつは、弊社ではメッシュに特殊な加工を重ねていまして、それは椅子を分解してもわからないノウハウなんです。だから形は真似できても、座り心地は真似できなかったんですね。弊社としては脅威でもなんでもありませんでした」と語る青木照護社長もニコニコしている。 1994年から始まったノーリツイスと東海金属の画期的な椅子づくり開発。
無謀とも思えたこの挑戦が成功したのは、1947年の創業以来受け継いできた技術力と、モノ一つひとつに思いを込めた、ひとが真ん中の「一期一会」モノづくりを実践してきた結果といえるだろう。『SF』そして『SFR』という製品には、胸が熱くなる物語が隠されていた。
青木社長が伝えたい、100年後の社会に向けたメッセージ

最後に、「働く人たちを支える」をミッションとするノーリツイスと東海金属の青木照護社長に100年後の社会に向けて伝えたいメッセージを伺った。

日本青年会議所の2017年度 第66代会頭を務めた青木照護社長。自社について、社員からも、仕入先さんからも、地域社会からも、地球環境からも愛される、自分自身も愛してやまない「愛すべき会社」に育てることを経営目標としているそうだ。青木照護社長の100年後の社会に向けたメッセージから、日本という国に対する愛してやまない思いを感じた。