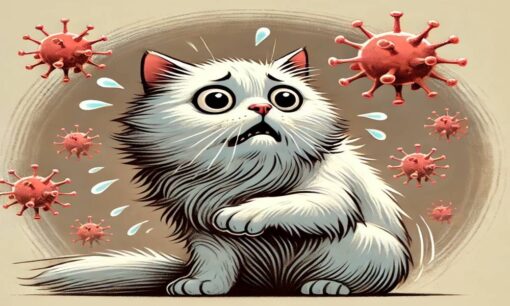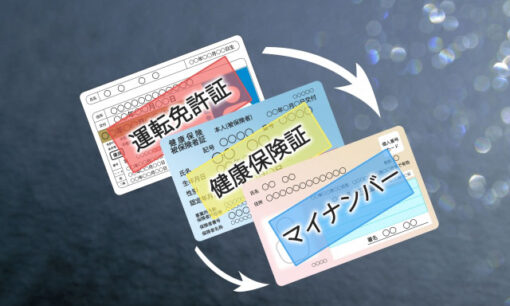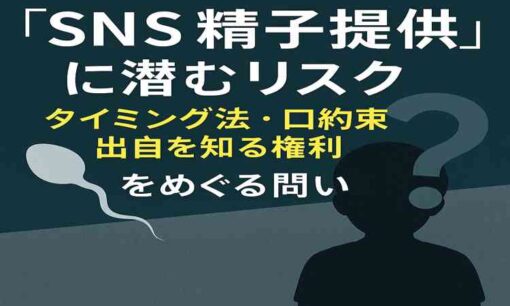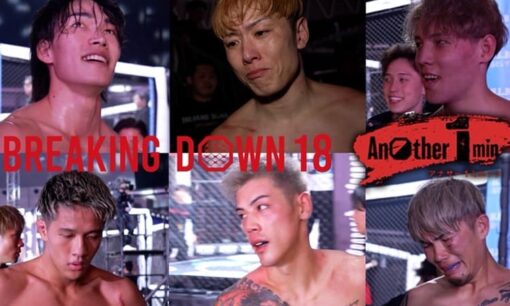進まぬSDGs、17%の達成率に警鐘

国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)。2030年までに貧困や飢餓の解消、気候変動対策、ジェンダー平等の実現など、17の目標を達成しようとする国際的な取り組みだ。しかしその進捗は芳しくなく、国連経済社会局(UNDESA)の2024年報告によれば、目標のうち順調に進んでいるのは全体のわずか17%にとどまる。
日本も例外ではない。地球環境戦略研究機関(IGES)は2025年5月、国内のSDGs実施状況とその課題を整理したうえで、日本政府に対する7つの提言をまとめた報告書を発表した。特にジェンダー(目標5)や環境関連(目標12〜15)分野での停滞が深刻で、既存の政策枠組みではもはや対応しきれない段階にあると警鐘を鳴らしている。
VNRとFURとは何か?
報告書で繰り返し登場するのが「FUR」と「VNR」という用語だ。本報告書においてFUR(Follow-up and Review)とは、各国がSDGsの目標にどれだけ取り組み、何ができていて何ができていないのかを定期的に見直し、改善する仕組みを指す。一方、VNR(Voluntary National Review)は、各国が国連に対して自主的にSDGsの実施状況を報告する制度で、日本もこれまでに複数回提出してきた。
しかしIGESによれば、日本のVNRは「成果報告」に偏っており、進捗が遅れている目標についての分析や政策改善につながる議論が不足しているという。FUR本来の意義である「学習と軌道修正」が機能していないと指摘されている。
進捗を見える化せよ:国内指標とデジタル体制の整備
提言の第一は、目標ごとの進捗を正確に把握し、国民に分かりやすく示す体制の強化だ。現在、日本のSDGs情報は国際指標をもとにした断片的なデータが中心で、何がうまくいっていて何が遅れているのかがわかりにくい。
これに対し、ドイツでは時系列で指標を可視化したオンラインプラットフォームを整備。インドネシアでは国と地方の進捗状況を一目で把握できる「SDGsダッシュボード」が稼働している。IGESはこうした海外の事例を参考に、日本でも総務省や関係省庁が連携して独自の指標を整備し、オンライン上で進捗を「見える化」することを求めている。
FUR体制に信頼と実効性を:第三者のレビューを導入
現状のFUR体制は、首相を本部長とする「SDGs推進本部」が主導し、ステークホルダーの意見を聞く「円卓会議」が設置されている。しかし、会議の実効性には疑問が残る。議論が政策に反映されるケースは少なく、事務局を務める外務省も人材や予算が限られており、継続的な知見の蓄積が難しい。
報告書では、国会による政策検証の制度化や、専門家による独立レビューの導入、そして政府がレビュー結果に対応する仕組みを整えることで、FURに信頼と実効性を持たせる必要があると提案している。
声を政策につなげる仕組みを:形式的参加からの脱却
SDGsの理念は、誰も取り残さないことだ。そのためには若者や市民、マイノリティなど幅広い立場の人々が政策形成に参画できる仕組みが欠かせない。ところが日本では、意見を述べる場はあっても、それが政策に反映されることはほとんどなく、「聞くだけ」の参加にとどまっている。
提言では、各省庁が意見への回答を行う「政策フィードバック・サイクル」の整備や、若者が実質的に関与できるような知識支援や経済的サポートの必要性が強調されている。
縦割り行政を超える:政策を横断的に統合する改革を
省庁ごとにSDGsの目標を分担している現在の体制では、目標間の連携や相乗効果(シナジー)を引き出すのが難しい。特に環境目標は後回しにされがちで、統合的な実装が妨げられている。
IGESは、ドイツが省庁横断の「変革チーム」を設置している例を紹介し、日本でも同様の仕組みの導入を提言。各省の政策提案時にSDGsへの影響を事前評価する制度(SDGsインパクトアセスメント)も必要だとしている。
自治体の格差を埋める:地域からの実装を支援
中小自治体では、SDGsを担う人員や予算が不足しており、十分な取り組みが行えないケースが多い。結果として、地域間での格差が拡大しつつある。
提言では、全国の自治体が共通で使える進捗評価ツールやオープンデータ基盤の整備、自治体職員向けの研修、先進自治体とのネットワーク構築など、地域からの実装を支える制度的支援が不可欠だとされている。
“見えない負荷”への自覚を:日本の国際責任を問う
日本はSDGsの国内達成度ランキングでは上位に位置しているが、自国の消費が他国にもたらす環境・社会的影響――いわゆる「スピルオーバー」への対応は不十分だ。報告書では、海外での人権侵害や環境破壊に加担しないための企業の責任(デュー・ディリジェンス)を法律で明確化する必要があると指摘。
OECDやG20と連携し、多国間協定を通じてグローバルな枠組みの中で責任を果たす日本の役割が問われている。
2030年まで残り5年、報告から行動へ
今回の報告書は、課題の整理にとどまらず、国内外の事例を踏まえたうえで、日本社会にとって実行可能な改革提案を示している。どの提案も、いますぐに大改革をする必要があるというよりも、「小さな試行と改善の積み重ね」で始められる内容が多い。
IGESは、SDGsの実現に向けて、政府や自治体、企業、市民社会がそれぞれの立場から責任を持ち、今こそ「実装」に踏み出すべき時期だと訴えている。
本記事ではIGESの提言の概要を紹介しました。より詳しい分析と提案内容を知りたい方は、ぜひ以下のページからレポート本文をご覧ください。
レポート本文はこちらから