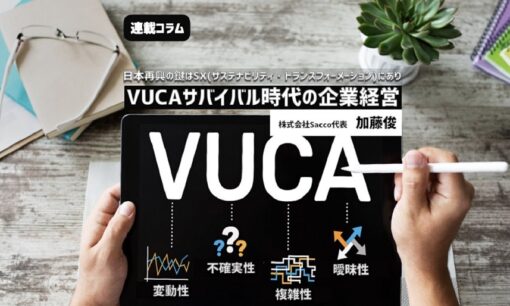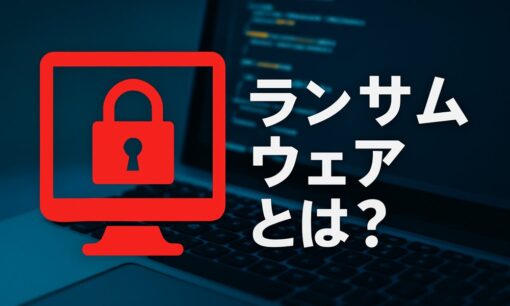文部科学省・気象庁が「日本の気候変動2025」を公表

文部科学省と気象庁は3月26日、日本の気候変動に関する最新の観測結果と将来予測をまとめた「日本の気候変動2025」を公表した。これは、2020年に発表された「日本の気候変動2020」の後継版にあたり、過去からの気象データや現時点での科学的知見を反映している。
同報告書によると、気温や降水量の変化はこれまで以上に顕著になっており、長期的に見た猛暑日や豪雨の増加、冬日の減少が明らかになった。
観測データが示す猛暑日と豪雨の増加
報告書によれば、1898年から2024年にかけて日本の年平均気温は100年当たり1.40℃の割合で上昇しており、特に大都市圏ではヒートアイランド現象も重なり、上昇率がさらに高い傾向がある。これに伴い、猛暑日や熱帯夜の発生が増加し、冬日は減少している。豪雨については1時間降水量50mm以上の事例が増えており、近年の気象災害の背景には温暖化があるとの見方を示している。
2℃上昇シナリオと4℃上昇シナリオの違い
報告書では、将来の気候変動を主に「2℃上昇シナリオ(パリ協定の達成)」と「4℃上昇シナリオ(追加的な対策を取らなかった場合)」に分けて分析している。2℃上昇シナリオはパリ協定で掲げられた目標を達成した世界観だが、4℃上昇シナリオでは年平均気温が20世紀末より4.5℃上昇すると予測されており、猛暑日の増加、豪雨の頻度上昇などがいずれも2℃シナリオより深刻化している。
たとえば4℃上昇シナリオでは猛暑日が年間17.5日ほど増え、冬日は46.2日減少する見通しだ。1時間降水量50mm以上の激しい雨は約3倍に増えるとされており、2℃上昇シナリオの約1.8倍を大きく上回る。温暖化対策の実施状況によって、将来の日本の気候は大きく変化する可能性がある。
海面水位・海洋酸性化への懸念
気象庁の観測では、過去100年間に日本近海の海面水温は世界平均の約2倍のペースで上昇している。報告書でも、4℃上昇シナリオでは日本近海の海面水温が最大3.45℃上昇し、沿岸の海面水位も0.68mほど上昇すると予測されている。これにより、高潮や高波のリスクが増し、沿岸地域の浸水被害が深刻化する可能性が高まる。
一方、二酸化炭素の排出増大は海のpHを下げ、サンゴや貝類などの骨格形成に悪影響を及ぼす「海洋酸性化」を進行させる。なかでも4℃上昇シナリオでは、21世紀半ば以降、日本の南方海域でサンゴの成長が厳しい水準に達するとみられ、海洋生態系全体への影響が懸念されている。
気候変動情報を生活者視点で伝える
同報告書は膨大な科学的データを含むが、日常に直結する視点を交えることが重要といわれる。猛暑日や豪雨の増加は体感しやすい気候変化であり、自宅周辺の浸水リスクや高波の影響なども、より具体的に示すことで危機感が高まるだろう。特に、4℃上昇と2℃上昇では被害の規模に大きな差があるため、対策の有無が将来像を左右することが伝わりやすくなっている。
まとめ
文部科学省と気象庁が公表した「日本の気候変動2025」は、猛暑日・豪雨・海面水位上昇などの増加傾向がデータで示されており、地球温暖化の進行が日本に与える影響が一段と明確になった。パリ協定の2℃目標を念頭に置いた場合と、追加的な対策が進まず4℃上昇へ向かう場合では、生活環境や災害リスクの大きさに差が生じる。今後の温暖化対策と連動した社会の取り組みが大きく問われる局面といえそうだ。