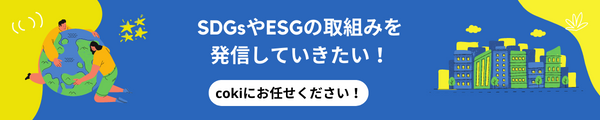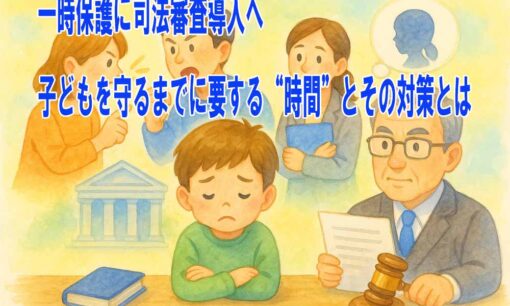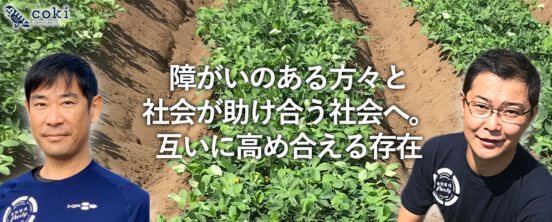若くしてAdecco Group JapanのSDGsの責任者となった小杉山浩太朗氏は、社会をより良くするチェンジメーカーとしてビジネスを通じたSDGsの実現を通じて 社会変革企業を目指す。
企業の目指すべきサスティナビリティとは何か、働きがいとSDGsとの関係とは何か、氏の進める社内外の取り組みを伺った。
小杉山さまのご経歴と業務の内容をお聞かせください。
小杉山
わたしはサスティナビリティ・トランスフォーメーション(以下SX)の責任者を務めています。
Adecco Groupが世界で約40の国と地域で行うグローバルインターンシッププログラム『CEO for One Month』を実施しているのですが、2018年にこのプログラムにチャレンジし日本法人のCEOに付いて1か月間のインターンシップを行ったことが縁で、2020年Adecco Group Japanに入社しSXへの取り組みを行っています。
この2年は中期経営計画としてSDGs、サスティナビリティを業務に反映させ社会的価値を最大化するため、Adecco Group Japanとして人材がいきいきと働く「適財」になるためにどのように働きかけていくか、企業が「適所」となるためにどのように変化すべきか、また両者をどのようにマッチングさせるのかという3つの軸で社会課題について考え、SDGsをどう達成していくのかを社内外の関係機関や組織と共にコラボレーションしてすすめていくのが、わたしの役割です。
また、グローバルサスティナビリティの機能に対するレポーティングの他、グループの人材派遣・アウトソーシング事業を展開するサービスブランドであるAdeccoのグローバル・プレジデントに対する諮問委員として2022年9月までの1年半の任期を務めています。
早速ですが小杉山さんにとって、サスティナブルな社会とはどのような社会なのでしょうか? また、Adecco Groupのパーパス「Making the future work for everyone」を通してご自身どのような未来を描いていらっしゃいますか?
小杉山
サスティナブルな社会というと、環境を思い浮かべる方が多いと思いますがサスティナビリティには3つの軸があると言われていて、それは「人の観点」「環境の観点」「経済の観点」です。
わたしたちが日本で行った市場調査では、仕事に対して「働きがいを感じている」人は4人に1人に過ぎず、7割以上の人が仕事はしなければならないものとして感じていることがわかりました。
自分は何をやりたいのか、やりたいことが分からない状態は、ウェルビーイングの観点からも課題があると捉えています。
そこで、自分自身のビジョンや目標、思いを実現する手段として仕事を選択することができるようになれば、働く人がいきいきと働き躍動している状態「人財躍動化」になると考え、そのような職場環境や状態を支援することを目指す中期事業計画を2021年に策定しました。
SDSsの8番の「働きがいも経済成長も」という目標の詳細項目5番の「すべての人に働きがいのある人間らしい仕事を」という部分にコミットすることになります。
「Making the future work for everyone」というAdecco Groupのパーパスに対して日本においては「『人財躍動化」を通じて社会を変える。」というビジョンを掲げています。
わたしたちは、社会変革企業を目指して社会的価値を最大化したときに、そのバリューチェーンに関わるすべての人が幸せであるべきと言う根本的な視点からサスティナブル、SDGsは系統化されているべきと考えています。
SDGsをビジネスに組み込み変革を起こしていく上で、御社の3つの柱→ダイバーシティ&インクルージョン、オペレーションエクセレンス、環境サスティナビリティについてそれぞれ具体的にどのような活動をしているのか教えてください。
ダイバーシティ&インクルージョンについて
小杉山
Adecco Group Japanでは、グループ内のエコシステムを活用した様々な人材サービスを提供しています。多くのソリューションを掛け合わせた提供が可能であり、そのためにも社内での対話の機会は非常に重要であると考えています。
社員の意見の多様性が担保されていることは、顧客へ高い価値を提供するためにも必要不可欠です。
1.ジェンダーイクオリティ(男女平等、女性活躍)
環境サスティナビリティについて
小杉山
Adecco Groupが目標とする2030年カーボンニュートラルの実現に向けた行動を実践しています。
私たちは、プロダクトを生産する事業ではないので、環境への関わりという部分で大きなインパクトを与えることはできませんが、現在の事業のなかで何から着手できるのか、環境サステナビリティワーキンググループを発足し検討・実行しています。
温室効果ガス排出量分析データにもとづき、社用車の削減およびハイブリッド化、オフィス使用紙の削減及び環境適応製品への変更、オフィスビルにおける消費電力削減などを効果的に行うことで脱炭素社会の実現へ向け、すでに取り組んでいます。
また、契約書類の電子化により、ペーパレスを実践し、取引先企業の契約業務に関わる業務の負荷軽減・効率化を推進しています。
2018年対比で環境負荷を13.5%削減することを目標に活動しています。
オペレーションエクセレンスについて
小杉山
社内のDX化を進めています。また、社員の課題解決力をつけるためにeラーニングなどプログラムを提供し、ロジカルシンキングなどの思考法を学び業務の効率化を促進しています。
その他に社内にSDGsを浸透させるプログラムなどはありますか?
小杉山
全社員に対しSDGsについての理解浸透を図るための対話やワークショップなどを行う「SDGsダイアログ」を行いました。
これは、1年間をかけて約2500名の社員を対象に行い、①SDGsを理解する、②SDGsと経営戦略がどのように繋がっているのかを理解する、③SDGsが一人ひとりの業務とどう繋がっているかを理解する、という3段階のアプローチで伝えていきました。
「SDGsダイアログ」は経営側からのアプローチであり、それだけでは社員の自分ごと化にするには十分ではありません。
そこで、同時にボトムアップからの活動として各部署から「SDGsアンバサダー」を有志で募り、より時間をかけて具体的で発展した内容の講習を行いました。
アンバサダーは、所属部署にレクチャーした内容を持ち帰り、SDGsの浸透を図るプロジェクトをリードしてくれています。これらの活動によって、社内全体にSDGsが浸透してきつつあると思います。
例えば、顧客に対するSDGs目線の提案や、業務以外での保護猫の活動など、幅広い自分なりのSDGsアクションを投稿することでSDGsを身近に捉えることができます。
どこかSDGsを遠いものに感じたり業務に関連付けにくかった部分を自分のこととして結びつけるきっかけになっています。
社内のS DGsに直結したお取組み、社外に展開しているお取組みを教えてください。
小杉山
前述した、ビジョンマッチングを通じた「人財躍動化」への取り組みは、事業に紐づいた取り組みです。
また、SDGsの4番「質の高い教育をみんなに(教育機会の提供)」ということに対しては、Adecco Groupとしても、2030年までに世界500万人の人々のリスキリングとアップスキリングを行うことに取り組むことを明示しており、日本においても、2025年までに30万人への教育機会の提供をするという目標があります。
教育に関する新しい取り組みとしては、昨年から「ぷろぐライク」という、小学生向けに プログラミング的思考(論理的思考)を育むコンテンツを地域や周辺の教育機関と共同で実施しています。
これまでのリスキリングとアップスキリングの主な対象者は求職者や転職者でしたが、今後はより幅広い年齢層にも拡大していくことが必要だと思っています。
また、少し違う角度からの活動としては、Adecco Groupでは2010年から『Win4Youth(ウィンフォーユース)』という社会貢献への取り組みを行っています。
これは、働く人のウェルビーイングを目指すと共に貧困などの環境的要因やその国が抱える社会的な問題によって、教育などの機会を得ることが難しい若年層への支援活動です。
社員のみならずステークホルダーとともにスポーツを通じた目標走行距離や時間の達成に応じて寄付金を国際的な支援団体に寄付しています。
SDGsを社内で実行していった中で、実際にどのような変化がありましたか?
小杉山
大きな変化の一つに、社員の意識変革があげられます。
正直なところ、1年目でここまでの変化につながるとは思っていなかったため、驚きではありましたが、非常に心強いスタートになりました。
ある社員からは、「自分が担当した人材が、ビジョンマッチングにより働いたあとも躍動感に溢れている状況で、就労先の企業からのフィードバックも良い、これまでに感じたことがないやりがいを得ている。」というコメントがありました。
社員のアプローチが変化したことにより、提供するサービスの質が向上したことが示唆されています。こうした経験を重ねることで、社外への変化も広がっていくことを期待しています。
小杉山さんが考える人材サービス企業の価値や今後の展望について教えてください。
小杉山
それは、「人財躍動化」に集約されています。
根本は自分が何をしたいかを考え、その実現のために学ぶ、働く。いつかそのような社会が実現することを願っています。
わたしは、これまでにさまざまな国に住んできましたが、ある国で、すごくワクワクして働いている人に出会いました。
その人が一般的な社会的成功者ではなくても、ただその人にとっての、「自分は幸せになれるためには、それを実現するためにこんなことをしている」ということが明確になっていれば、その人の幸せはとてもすばらしい、それが躍動化という言葉に集約されていると思います。
日本でそういった感じで人生を送っている方は少ないと感じます。その違いはなんでしょうか?
小杉山
個人的に感じるのは、学校教育の早い教育の段階で、自分自身に焦点をあてて何をしたいのか、さまざまな社会に触れる機会をつくることが大切だと思います。
ビジョンを持った状態で学生が進学先を選択する、就職先を選択する、住む国を選択するといったことが可能になります。
今、こうした選択ができるようにビジョン実現プログラムを開発し、若年層を中心に体験をしてもらっています。
私たちは仕事だけでなく、ひとりひとりの人生に寄り添い、人財を躍動させるための取り組みとして、このような教育プログラムの提供も行っていきたいと考えています。
ありがとうございます。 他に強調したいことなどはありますか?
小杉山
サスティナビリティ責任者というと一見ビジネスとつながりがない、と思われることが多いのですが、企業のサスティナビリティはビジネスと直結しているべきだと思っています。
わたしたちが社会に何かを行ったときにポジティブな価値が生まれ最大化しているかを考えるのが企業の責任であり、その実現のために経営戦略や社内のメンバーが目標をもつべきです。
◎プロフィール